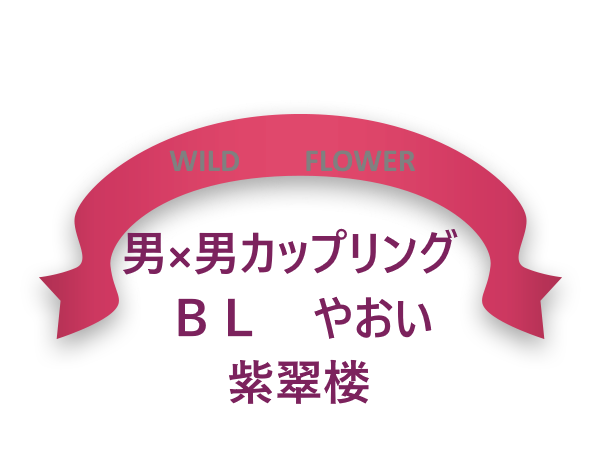箱庭の庭園本好きの下克上
フェルディナンド×ローゼマイン
カツンカツンと乾いた靴音が反響するのは、そこが石造りの地下であるからだ。
普段の色とは違い、漆黒の髪に黒い簡素な衣装を身にまとったフェルディナンドは、まるで闇を具現化したような印象を与える。
「お久しぶりでございます、クインタ様」
どう見ても堅気には見えない男が、恭しい仕草で挨拶をする。
数字を意味するそれが、貴族然とした男の本名とは思っていない。あくまでも偽名だろうとは思っているが、敢えてそこを突く気はなかった。
「客の入りはどうだ?」
「それはまぁ、貴族の女を好きに出来るとあれば、それなりに需要はございます」
特に、今まで貴族の横暴に耐えてきた商人の中には、嬉々として通う者もいる。
「とにかく、商品は死なせなければそれで良い。あと、上には知られぬように気をつけろ」
「承知しております。アウブは下々にも理解を示してくださいますが、お優しい方ですからな」
「ああ、魔力供給だけではな。せめて自分の食い扶持ぐらいは稼いでもらわなくては」
貴族なのだから、魔力供給は義務だ。それで衣食住を整えるのでは、こちらの持ち出しになると、フェルディナンドが感情の籠もらない声で言う。
このアレキサンドリアでは、神殿での花捧げは全面に禁止したが、売買春が古来から存在する職業であることもローゼマインは理解していた。
だからこそ、歓楽街の整備に着手している。
貧しさから身体を売るしかない女達がいるなら、それは領政治の問題なのだと。
ただやみくもに禁止すれば、その手の組織が地下に潜り、余計に女達の扱いは劣悪になるだろう。
だから、認可制にするとローゼマインは言った。
認可を受けた店以外での売春は取り締まる。そして、認可を受けるには、商品である女性をきちんと管理しなくてはいけないと。
きちんと食事と休息を与え、月に一度の健康診断をうけさせること。契約で働く拘束期間を定めること。
その代わり認可を受けた店には、アウブの名で許可証を発行し、貴族の魔力を封じる魔術具を貸与すると。
「仮名として『花街』と呼びましょうか。そこでは、貴族であってもただの客です。最上位の『花娘』には、客を選ぶ権利を与えるというのはどうでしょう?『花娘』にも階級をもうけます。美しさだけでなく、貴族並の教養や接客も優れている者を上位に置き、そんな上位を目指して下位の者達は努力する。そういう環境を作り、客側も金や身分を振りかざすだけでは呼べない『特別な存在』を作る。最上位の『花娘』を呼ぶことが出来るのはお金だけでなく人脈と人柄、趣味も良いという保証だと、そういう価値をもたせたいのです。第一、疲れてやつれた表情の女性が接待するより、にこやかで美しい女性に接待される方が男性も気分が良いでしょう?」
「アウブ!」
周囲の男性が血相を変えるが、今更だろうとローゼマインは冷めた表情を見せる。
「わたくしはエーレンフェストで孤児院長もしていたのですよ。灰色巫女には、貴族の愛人になれれば貧しさから抜け出し、贅沢な暮らしが出来ると考えている者もおりました。嫌がる者に花捧げを強要することは許しませんでしたが、自ら愛人になりたいという者を止めることもしませんでしたよ」
ローゼマインが考えているのは、せめて彼女達にも選択肢を与えたいということであり、搾取されて捨てられるだけにならないように、規制をかけたいということだ。
「身体を売るにしても、年を取れば続けるのが厳しくなるでしょう。ならば、せめて読み書きと計算が出来て、客あしらいが上手ければ、買われた先でも使用人として働けるかもしれないし、辞めた後、何人かで集まってお店を開くことも出来るのではないかしら?」
妓楼に望むのは女達の待遇の改善であり、教育だ。
モデルはもちろん江戸の吉原であり、京の島原の太夫だ。
島原の太夫は貴族と同格の地位を朝廷より認められ、吉原の花魁達は大名を顧客に持ち、江戸城にあがることも許された。
もちろん、華やかなばかりではなく、線香一本の時間で身売りする切り見世女郎の待遇は底辺で、花魁や新造とて客をとれなくなった遊女はどんどん格下の見世に払い下げられ、死ねばまとめて無縁墓地にいれられる。
田舎の訛りをごまかす為の郭言葉、塀の外のには出ることが出来ない籠の鳥。
だが、花街は文化と流行の先端であり、一目会うだけで男達は大金を積む場所だ。
汚らわしいと見て見ぬフリをするのではなく、きちんと組み込み税をとりたい。
そして、彼女たちには娼婦を辞めた後の生活基盤となるものを与えたい。
でなければ、年期があけても、また日陰の世界に戻るしか無くなる。
契約で縛れば、逃亡を意識した過度な折檻は必要ない。
本人に学ぶ意思があれば、読み書き計算、立ち居振る舞いに貴族の常識を教える灰色神官を派遣し、楽曲に関しては貴族院で学ぶスタンダードな曲に加え、ローゼマインが十数曲渡した。
まあ、こちらの基準だと日本の曲の多くは歌詞がかなり破廉恥になるので、逆に花街の女性にはちょうど良いだろうと思ったのと、演歌によくある不倫系や別れても待っています系の歌詞は、客の訪れを待つ彼女達にも共感しやすいだろうと思ってのことだ。
さすがに「殺したい」という歌詞は修正が入ったが。
独特の節回しと、今までに無い直裁な歌詞に最初は戸惑っていた彼女達だが、それぞれがアレンジを加えて客に聞かせる売りになった。
食事に関しては、お手軽な揚げ物系を提案し、一定の温度を保つフライヤーを格安で貸し出した。
揚げ物系は極めようと思えば奥が深いが、音を確認しながら時間を計れば、一定レベルでは仕上がる。
塩、柑橘系の絞り汁のお手頃から、これも提携先格安販売のタルタルソース、ウスターソースの提供と、熱々の揚げ物には冷やした酒との相性が良いと、冷蔵庫の魔道具も低価格で貸し出した。
認可を受けることで、店が抱える女達の扱いに領主から派遣された役人の査察が入るものの、売上をあげるための付加価値も提供することを示し、領都の外側に歓楽街を作った。手軽に売買春だけの店もあれば、上級貴族の娘並に教養を身につけた娘が接待をする店や、楽曲が得意な者が新しい曲を奏でてそれを酒を飲みながら楽しむ店など、客の懐具合に合わせた店の種類も増えた。
そしてこの花街でトップの『花娘』は下級貴族と同等の地位を与えられた。
税を納めることで、自分達はアレキサンドリアに貢献しているという自負と、領主管轄の庇護を得て、最底辺にいた彼女達も貴族の横暴に泣き寝入りはしなくなった。
彼女達の環境は以前に比べて劇的に良くなったのだが、それでも闇が消えた訳では無い。
より濃く、深い闇が光の外側には存在する。
ただし、それをフェルディナンドはローゼマインに見せないようにしていた。
皆が皆、ローゼマインのように善意で他者を救いたいと思う訳ではない。
ただ己の嗜虐を満たすために他者を傷つける者がいる。そして、それは相手が自分よりも弱者だと考えているからだ。
シュミルがどれほど刃向かったとて、ザンツェには致命傷にはならない。
貴族にとって平民がそうだった。上級貴族にとって下級貴族がそうだった。
何を言っても、何をしても許されると思えばこそ、どんな横暴な行為も出来る。
だが、それは魔力というアドバンテージであり、家格という形のない権威があればこそだ。家格を失い、魔力を封じられれば、彼らは強者ではいられない。
まぁ、騎士の一部は武力で対抗できるかもしれないが、手段を選ばない者達が数で押せばそれもさほどのことではない。
フェルディナンドはランツェナーベを引き入れた旧アーレンスバッハ貴族家のうちから、ゲオルギーネ派閥でやりたい放題してきた者達の魔力を封じた上で、この下層に放り込んだ。平民達の不満のガス抜きとしてであり、ランツェナーベで身内を殺された者達の怒りや復讐心をローゼマインに向けさせない為の贄として。
泣いて許しを請う彼等に、平民達の復讐者は下品な笑い声をあげる。
そんな部屋の様子を無表情なままフェルディナンドは一瞥して、交換用の魔力封じの首飾りをここを仕切っている頭領の男に渡す。
怪我を負った者には回復薬と癒やしの祝福で治療を施すのは、けっして優しさからではない。傷だらけの顔や身体では客の付きがよくないからだ。
下賤な者と蔑んでいた者達から見下ろされすのはさぞかし腹立たしかっただろうが、それも痛みを伴って繰り返されれば心が折れる。
魔力が封じられてシュタープが使えなければ非力な存在で、矜持を失った者はすでに貴族ではなく、ただ蹂躙されるだけの弱者となる。
神々との約束故に殺すことはしない。
特にこのアレキサンドリアでは大規模施設がいくつも稼働していて、魔力供給はないよりあるほうが良い。
だが、彼等のような輩を、客人のように礼遇する気は欠片もなかったし、魔石としても使えない。
かといって、放置すればローゼマインを害そうとする輩に利用されるかもしれない。
ならば、魔力を供給させながら、不満分子をあぶり出す撒き餌となってもらう。
この手の輩は皆どこかの貴族と繋がっているものだ。
こやつらを通して、『貴族が飼われている』という話がどこまで流れるか、試させてもらおう。
廃棄処分するにも、できるだけ再利用しなくては、勿体ないではないか。
地上では灯火が煌めき、華やかな様子だが、地下は紅い灯りと嬌声と悲鳴が厚い壁に反射している。
地下組織を束ねる頭領は、決して顔を見せない黒髪の青年の前で深く頭を下げる。
威圧という訳ではないのが、ヒンヤリとした冷気が彼から漂っている気がする。
多分、彼も貴族なのだろうが、ここで飼われている貴族達を見る目は、まるで検品ではねた二級品を見るような目だ。
回復薬も癒やしも、勿体ないという体で、仕事だから仕方が無くやっているという風に見える。
癒やされる側は最初の一、二度こそ感謝していたが、助けてくれとどんなに懇願しても答えがなく、侮蔑の視線で見下されて反発した態度を取る者が大半だった。
「貴様も貴族だろう!」「どうして私を助けてくれないのです!このような不当な扱いをする輩を早く捕まえて罰しなさい!」そう叫んだ相手にも顔を顰めただけで一言も発しない。
何を言っても、問いかけても、答えはない。
そして、彼に癒やされれば、また客の前に出されるのだと理解するにつれ、怪我以上に彼の訪れを恐怖するようになった。
怪我が治れば休めないのだ。また、平民に、客に罵倒され、嘲られ、嬲られるのだと。
許してくれと足下にすがって懇願する彼等を睥睨しながら、彼は癒やしを与え、無理矢理回復薬を飲ませると、「仕事の時間だ」と薄く笑む。
見えぬインク魔法陣を描いたローブとフードを目深にかぶり、素顔をさらさぬフェルディナンドは、ここではクインタと名乗った。
本来であれば、こんな闇の中で朽ちるはずだったのだと、そんな自戒も込めてフェルディナンドはユストクスにまかせず自ら足を運ぶ。跡をつければ殺すと言外に釘をさされた頭領は、分をわきまえて何も聞かない。
下手に弱みを握ろうなどと欲を出せば、自分も破滅だと本能で理解していた。
何も言わず何も聞かず、ただ彼の命令を諾々と受ければ、金が転がり込んでくる。それで納得するしかない。
彼の身元を探ろうとした先代は、その取り巻きともども消されたのだから。
そして、彼のような男を手の内に持つ新しいアウブとその婿に尊敬を覚える。
ただ顔がお綺麗なだけの領主ではない。闇は闇として、統率の手を緩めない。
華やかな表の花街は、さっそく他領から訪れる商人達の間で噂になっている。そして、彼等が落とす情報を報告することを花娘と店の者達には暗黙の了解として義務づけられている。金と情報に価値を見いだす新しいアウブ。
聖女を支える婚約者殿は、貴族院時代『魔王』と呼ばれていたとか。
できれば、もっと早くその気になって欲しかったというのが本音だが、これも星の巡り合わせというやつなのだろう。
あの青く輝く海原を見たとき、沈むランツェナーベの船を見たとき、空に輝く巨大な魔法陣を見たとき、確かに貴族の力を実感して背筋が冷たくなった。
どうあがいても埋めきれない差を自覚した。だからこそ、どうして今までの領主や貴族達は俺たちを助けてくれなかったのかと恨めしくも思った。
女神の治める土地アレキサンドリア。自分達など貴族から見れば取るに足らぬ塵芥だろうが。
「また、来る」
「お待ちしております」
日が差さぬ場所でしか生きられない者もいるのだと、あの麗しいアウブは知らなくて良い。ここは、自分のような者達こそがふさわしい、闇が支配する場所だ。