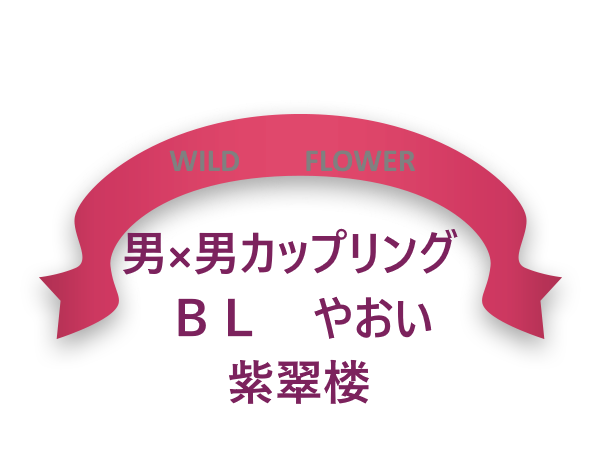箱庭の庭園6本好きの下克上
フェルディナンド×ローゼマイン
本人は本気で自分がツェントに相応しいと信じていたが、外から見れば外敵であるランツェナーベを引き入れたのは外患誘致であり、貴族院襲撃はツェントの簒奪でしかないディートリンデの行為は、アーレンスバッハを廃領地にする理由としては十分なものであった。だからこそ、未成年者であってもグルトリスハイトを授ける女神の受託代行を担い、礎を奪って新領地アレキサンドリアのアウブとなったローゼマインにアーレンスバッハの者達が縋ったのは当然だった。
名捧げをした者はことごとく高みにのぼったが、ゲオルギーネやディートリンデと距離を置いていた者達や、主流派から外された者達、まして庶民にとっては自分があずかり知らぬ大罪の連座など納得できるはずもない。
それでも、皆が皆、最初からローゼマインに忠誠を誓った訳ではない。
外見は成長して麗しくなったものの、未成年であることには違いがないし、そもそも貴族院での評判はディートリンデとその取り巻きによって随分と歪められている。
虚弱であることや、神殿育ちのせいで領主候補どころか貴族としてふさわしからぬ言動や行動をとると。フラウレルムなどは貴族の出自など真っ赤な嘘で、卑しい平民の身食いだと思っていたことから、ことさら貶める言い方をしてきたので、それを信じていた者もいる。
フェルディナンドは神殿にいたことでディートリンデはあからさまに蔑む態度だったが、流石にアーレンスバッハで統治責任を果たしてきた彼を軽んじる実務担当者はいない。
どちらかと言えば、直接の関わりが少ない上級貴族やギーベの方が、フェルディナンドを侮る輩がいる。
ただし、ローゼマインが行った大規模な祝福で、土地の再生が叶った地方のギーベは、領主としてのローゼマインをうけいれた。
土地が痩せていくばかりで放置するアウブより、魔力を注いで豊穣をもたらすアウブの方が良いのは当然だったからだ。
ローゼマインがアーレンスバッハの城でまず最初に行ったのが食事の改善だった。
富貴の証と、砂糖でコーティングされたような、口の中でジャリジャリ砂糖の味がするお菓子も、これでもかと香辛料を投入した料理も口に合わない。それにここまで香辛料がきいていては毒物を混ぜられてもとっさに判別がつかない。
毒殺に対する警戒もあって早急にフーゴらを呼び、自分達の料理はアーレンスバッハの料理人には任せない方法をとったのだが、これは勿論城の料理長を筆頭に反発と不満を生んだ。
わかりやすく料理対決を開催し、ローゼマインとフェルディナンド、レティーツィアと旧アーレンスバッハの貴族たちを審判役に大試食会を開催した。
フーゴとエラが用意したのは、定番のダブルコンソメに、フワフワの白パン。ポテトサラダを添えた温野菜のサラダ。ドレッシングにはお酢に少量の香辛料と砂糖を入れて、さっぱりとした甘酢風味に。白身魚のポワレはワインを生かしたソース、厚みのある肉を使ったカツレツには重めのグレービーソース。デザートには冷菓のリッチミルクのアイスに砂糖で煮詰めたラッフェルのソースをかけたものと、フルーツと生クリームをたっぷり使ったクレープシュゼット。
今回の料理対決は、ローゼマインとフェルディナンドが好む料理を出すのが正解だと、二人はいつも作る味付けに多少香辛料をきかせる程度で用意した。
レティーツィアなどは嬉しそうに料理を食べ、側仕えの者達がいささか残念そうな顔をしている。
城の料理長であるベルダ達が用意した料理は、ゆで汁に旨みを捨て、色が変わるほどに香辛料を使った料理で、一口で舌が麻痺して味覚が飛ぶと、ローゼマインは小さく切り分けた一口がせいぜいだ。
判定の採決を取ると、圧倒的多数でフーゴに票が入った。
新アウブであるローゼマイン様をおもんばかってのことだと、ベルダは顔を真っ赤にして不服を申し立てたが、フェルディナンドは口元をナプキンで拭ってから冷たく睥睨する。
「何を勘違いしている?アウブであるローゼマイン様が好む料理を作る者が、城で食事を用意するのは当然であろうが」
「アウブとあろう者が、そのような貧相な料理を美味と言っては、他領に対して恥をかきますぞ!」
「あなたが作る素材の味がわからぬほどに香辛料まみれにした物を高級料理と呼ぶなら、わたくしは貧相な料理で良いわ。それに、フェルディナンド様の食事が進まぬことを知りながら、メニューを考えようとしなかった、独りよがりな料理を作る者に任せる気はありません」
もともと食事を疎かにする傾向のあるフェルディナンドだが、アーレンスバッハで領主代行ともいえる執政を行っていたとき、本当にまともな食事をとらせるのに苦労したそうで、ローゼマインと食事をとるフェルディナンドにユストクスとエックハルトがほっとした表情をみせた。それほど食べないというのに、この城の料理人達はフェルディナンドが好む味付けを尋ねもしなかったそうで、その点もローゼマインは気に入らなかった。
「それでは、オレは職を辞させていただきます!」
ここまで馬鹿にされて我慢できるか、と叫んだベルダに、ローゼマインは頷いてあっさりと了承した。
「今までご苦労様でした。あなたの作る料理を好む新しい職場に移りなさい」
ベルダだけでなく、城に勤める料理人のうち、見習い達を含めた3分の2を引き連れて辞めてしまい、フーゴは蒼褪めたが、ローゼマインだけでなく、フェルディナンドも平然としていた。
今なら、職を失った料理人はすぐに見つかるだろうから、しばらく耐えろとユストクスに言われる。
実際、名捧げで高みに上った者の家などは、実質取りつぶしに近いし、ランツェナーベの襲撃を受けた者や、当主達が白の塔に送られた家などもかなりの数に上る。
その家の料理人が職にあぶれているので、新しい料理を覚える気がある者と、ユストクスが選定してもすぐに辞めた者達の数は集まった。
もともと、ベルダ達はディートリンデが重用していた料理人で、ランツェナーベの者達への料理も作っていた。
そして、エーレンフェスト出身のフェルディナンドやローゼマインが好む薄味を、貧乏人の舌だと馬鹿にし、自分が高貴な者に相応しい食事がどういうものか教えてやるのだと嘯いていたものだから、ユストクスの心証は最悪で、とっととその首を飛ばしたかったのだ。
どうせ味もわからぬと手抜き料理をフェルディナンドに出したこと、香辛料を控えて欲しいと言っても無視されたこと、ユストクスだけでなくエックハルトも忘れていなかったからだ。
そして、新しく雇い入れた料理人達にローゼマインとフーゴが新しいレシピを教え込む。
最初は配膳の者達の数も足りなかったので、料理の提供はビュッフェスタイルで、とにかく料理人たちに作ることに慣れさせ、城の者達に新しい味を広めた。
自分の好みの料理を好きなだけ盛り付けられるビュッフェスタイルは、運動量が多くて健啖家が多い騎士達には人気で、朝と晩はこのスタイルが定着する。
苦味、辛味、甘味、渋味、酸味、旨味、舌で味わうことと、目で楽しむこと。皿に盛りつけるのは、料理人の自尊心ではなく、食べる人が美味しいと笑顔になってくれることを願ってのもの。
フーゴとエラはローゼマイン様とフェルディナンド様が美味しいと思ってくださる料理を作るのが、自分達の仕事だと胸を張った。
そして、ローゼマインはアーレンスバッハの料理を伝える必要性も無視することなく、香辛料をきかせた料理を提供するレストランを開くことを考える。
勿論、他領の者の口にも合うようにアレンジをした「なんちゃってエスニック料理」のお店だ。
自分達が集団で辞めたら困って、慌てた城から呼び戻されるだろうと考えていたベルダ達は思惑が外れて焦った。
ランツェナーベとの国境は閉ざされ、今までのように香辛料や砂糖が入ってこないのだから、富貴のために食べられない程大量の香辛料を使った料理より、美味しいと感じる程度の少量の香辛料を使用した料理を広める方が経済的だとローゼマインは主張し、実際、香辛料は引き立て役だという料理を振舞ってみせ、これからアレキサンドリアの料理はこれが主流になると示したからだ。
香辛料を大量に使うことを前提に、前処理である下拵えなどほとんど行ったことのないベルダ達では、ローゼマインのレシピを再現できなかった。
城勤めというのは名前だけかと、最初は歓迎してくれた貴族家もベルダ達が作った料理を口にすれば顔を顰める。
そして、神殿に預けられていた貴族の子弟から料理人を志す者が現れて城に入り、アレキサンドリア料理が確立されていくほどに、ベルダ達は立場を失っていった。
誰が食べるのか考え、新しい料理を学ぶ気概があれば、違った道もあっただろうに、と思う。貴族達が関心を惹きたい相手の筆頭であるローゼマインの不興を買った料理人を雇う貴族家などなく、下町の庶民相手の食堂ぐらいしか彼等を雇ってくれる店などない。
そのことに、ユストクスとエックハルトはにんまりと笑って溜飲を下げた。
フランとザームは早々にローゼマインが買い取ってアレキサンドリアにつれていった。神殿と孤児院の差配に工房運営を理解している筆頭側仕えであり、補佐をしていた二人はアレキサンドリアの神殿と孤児院改革を任された。
ローゼマインのやり方を良く知っている二人だから、しばらくはエーレンフェストにいる孤児院長に就任してまもない不慣れなフィリーネの補佐にと考えていたのだが、アーレンスバッハの神殿が予想以上にひどかった。
ここは神殿ではなく娼館かと青筋をたてて怒ったのは、ハルトムートだ。
女神のおわす神殿に相応しくないと、叩き壊す勢いで貴族を迎える淫靡な部屋を使えないようにして閉鎖していった。
花ささげで衣食住をまかなうと考えている灰色巫女はひとまとめにして、クラリッサが懇々とローゼマインに尽くす巫女のあるべき姿を説いて聞かせた。
孤児院はエーレンフェスト以上にひどい有様だった。
世話をされずに放置され、汚物にまみれた部屋にうつろな目をした幼子達。
初めてその光景を目にしたローゼマインの側近達の中でも未成年者は、口元を覆って目を逸らした。
ローゼマインを聖女と崇め、ローゼマインがいなくなることに怯えるエーレンフェストの灰色神官達、その心情がようやく理解できたのだ。
たしかに、『ここ』には戻りたくないだろう。
女性であるフィリーネが孤児院を預かったように、アレキサンドリアでもレティーツィアを孤児院長に据え、神殿にも関わらせるつもりだった。
だが、アーレンスバッハの孤児院には、ランツェナーヴェの襲撃で身寄りをなくした者と、領主夫人であったゲオルギーネが高みに登ったことで、魔石に変じた名捧げの身内がいた。
ゲオルギーネが生存の頃、名捧げの方が勢威があり、ランツェナーヴェに襲撃を受けた方はゲオルギーネから距離を取って中枢から離れていた者達で、あなどられがちではあった。
しかし、立場は逆転し、貴族の親族だけでなくランツェナーヴェに親を殺された平民の子達からも憎悪を向けられる名捧げ組の幼い子供達は、亡くした親を悲しむことも許されなかったが、側近を失ったレティーツィアも、ランツェナーヴェを引きいれた身内には複雑な心境だった。
ただ、レティーツィア自身は、フェルディナンドを害そうとしたことをフェルディナンドとローゼマインに許された身だから、あからさまな態度はとらなかったが。
神殿を取り仕切ったハルトムートとクラリッサだが、あまりにも側近の数が足らない状況では言動はともかく能力的には優秀な文官二人を神殿に張りつかせておくことはできず、こちらもフェルディナンドの差配を受ける時間が多く、なかなか神殿と孤児院に目を配ることが出来ない。
そこで、フランとザームが呼ばれたのだ。
本当に大変だと思うけど、お願い助けてとローゼマインは二人に頼んだ。
神殿から出た事がないので、外の世界で生きていく自信はないと言ったフラン。それでも、もう置いていかれるのは嫌だと、アレキサンドリアに移動するほうを選んだ。
ローゼマインもフェルディナンドも、いくら待っていてもエーレンフェストの神殿には帰ってこないのだ。必要だとローゼマインが言ってくれるなら、そしてそれが神殿であるなら、自分も少しは役に立てるだろうと。
ハルトムートが不在の時は、代わりに神殿を差配する次席に就いた。ローゼマインが買い取ったことで、灰色神官からは離れ、青色でも灰色でもないとアレキサンドリアの色である紺色の神官服をローゼマインから与えられた。
二人は正式にローゼマイン様から任命された神官であると、フラン達を灰色と見下した青色神官達はハルトムートにより神殿から追い出された。
ローゼマインの役に立たぬ者は必要ない、ましてやローゼマインから信任を受けた者を蔑ろにするなど許しがたいと、青色神官達の弁明を一切聞かなかった。
無能で怠惰な者が嫌いだと、自分の周囲や重要な役職から遠ざけるフェルディナンドに対して、ローゼマインの役に立つか否かで判断して不要となれば排除するハルトムートの対応はアレキサンドリアでより顕著になった。
この青色神官達は優秀だから実家に戻すのではない。心得違いをした役立たずを神殿に置く気はないから、実家が責任をもって再教育しろ、二度と神殿に入れるなと親族たちを神殿に呼んで突き返したのだ。
もともと貴族となるには魔力が足りずに神殿に預けられ、アーレンスバッハ時代はまともな教育も受けていなかった者達だ。
神殿だから青色として偉そうな態度もできたが、実家に戻れば貴族にも慣れぬごく潰しでしかない。飼い殺し確実な上、新アウブであるローゼマインの不興をかったとなれば温かく迎える家などない。すでに忌々しそうな視線で、自分達の息子や娘を見ていて、その視線を受ける青色の神官服を脱いだ者達は顔色を青褪めさせている。
それと知っていながら、ハルトムートは追い出したのだ。これで彼らが居場所を失い、実家からも追い出されて路頭に迷っても構わない。
貴族院にいっていない青色達はシュタープをもたないから、平民を魔力で害することはない。アーレンスバッハの神殿でのらりくらりと過ごしてきた彼等は生活の糧を得る知識も技術もない。実家の援助がなければ生きていけない。それは青色からの下げ渡しに頼る以前の灰色神官達と同じ暮らしだ。
ローゼマインの初期からの側仕えとして働いてきたフラン達を馬鹿にしたのなら、その方ら自身は灰色とは違うと示してみせろと、薄い笑みを浮かべて彼等とその親族を神殿から追い出したのだった。
絵師として買い取られたヴィルマや、プランタン商会が主軸になりつつあるギル、孤児院の食事を担当するニコラ達もローゼマインに買い取られたことで灰色から離れ、紺色の神官服で神殿や孤児院に滞在することになる。
身内が貴族であろうが平民であろうが、ここでは等しく孤児として扱うこと、満足のいく食事が欲しければ科せられた労働を果たす事。
知識を身につけることで、『選択』が生まれる事。蔑まれるのが嫌ならば、力をつけろとギルは言った。
「ローゼマイン様はお優しい。だが、ただ施しを与える方ではない。『働かざる者、食うべからず』勤労に対して報酬を下さる。灰色ならば貴族に召し抱えられても大丈夫なように、知識や立ち居振る舞いを身につけることは必須だ」
やはりここでも、死にかけていた平民の孤児達の方が改善された生活を手放すまいと貪欲だった。
カルタや絵本、トランプを与えられ、平民の子供達が文字や数字を覚えていくのに、貴族の遺児達は茫然とした。
知識に身分は関係ないと、そう言われてもどこか見下していたのだ。
それなのに、貴族である自分達より流暢に文章を読み、加減算を行い、神々の名前をソラで言える。貴族の子なのに出来ないのかと、逆に問われれば、唇を噛むしかない。
貴族の子供達には、やる気と資質があるならば、親の罪は問わず奨学金という形で貴族院への進学を補助する。優秀者に選ばれれば、翌年の貴族院でかかる費用の半分、最優秀であれば全額を免除するとローゼマイン様よりのお言葉だとハルトムートが言った。
もちろん、シュツーリィアの盾で選別を行い、面談はするが、素質のある子は貴族院にいかせた方が良いとローゼマインがフェルディナンドを説得したのだ。
このあたり、メスティオノーラの書もあれば、素材も回復させればいくらでも都合がつくのだから、魔力をためておく道具はツェントに頼らずとも自作すれば良いと考えてのことだ。
本当に幼い者達には弱いと、蟀谷を指で叩きながらフェルディナンドはメリットとデメリットを秤にかける。
ハルトムートほどの信者ではなくとも、ローゼマインを裏切らぬ基礎力のある貴族が増えるのは確かにメリットだった。
今は大人しくしていても、いずれローゼマインを甘くみてアーレンスバッハの頃のように自分の思うまま出来ると不正を行う輩も出てくる。
今までの不正を許す気もないので、おいおい首を挿げ替えていくつもりではあったが、その子供達が成長し、家を継がせる形で入れかえていくのもありだと計算をした。
冷静に判断しているようで、ローゼマイン様の頼みを実現するために理論武装を組み立てていると、ユストクスなどは笑う。
それでも、機会を与えられると知った子供達のうち、中級下級の子達や、兄弟姉妹がいる者達は食いついた。
エーレンフェストの子供部屋ほどアーレンスバッハの子供部屋では勉強が推奨されておらず、身分差から下の子ほど上級貴族の子供達の無体に耐える日々だった。
それがここでは教材が与えられ、共有とはいえ数台の子供用フシェピエールも置かれて指導を受けることが出来た。
最優秀は無理でも優秀賞が取れれば費用の半額は免除になる。入学前は紙作りや本作りでお金をため、入学後は写本や情報集めれをすれば買い取ってもらえる。
親の援助がなくても、貴族になれると、その可能性を見出した子供は目の色を変えた。
今までの生活との落差が激しい上級貴族、特に富裕層の子供程神殿での自活を前提とした生活に馴染めなった。
紺色の神官服を着た者は、貴族の子弟であっても等しく接した。無礼だと咎めても、彼等は態度を変えなかった。
お菓子や石板、書字板、新しい衣装など平民の孤児に与えて上級貴族の子供達に与えないことがあった。
自分達の親がゲオルギーネ様に名捧げをしていたから差別するのかと貴族家の子供達が怒って訴えれば、首を横に振り、これは頑張った者に対してローゼマイン様がくだされるご褒美なのだと言った。
孤児院にいる限り、最低限の生活の保障はされる。だが、身分に関係なく、勤めを果たさぬ者にローゼマイン様が『ご褒美』が渡されることはないと、彼等は自分達の名前が刻まれた、使い込まれた書字板を見せる。
「己が身の不幸を嘆くだけで、命を救ってくださったローゼマイン様に対して何の貢献もせぬ者に渡す『ご褒美』はありません」
「誰も救ってくれなんて言ってない!」
「慈悲深い聖女だと、女神の化身だというなら、どうして父上を助けてくれなかった!」
「不満だというなら、出ていきなさい。あなた方がいなくなれば、それだけ食費が浮きます」
相手が子供であっても、フラン達は容赦なかった。
この孤児院で保護されることが、どれだけの温情なのか理解せぬ愚か者は、ここから出ていけば良いと本気で思っていた。
ランツェナーヴェに襲われたのは反対派の貴族達だけではない。身内を殺されたり、妻や娘を連れさらせそうになった平民も多い。
そんな彼らの元に、シュタープを持たぬ外患誘致の貴族の子供が姿を見せれば、孤児院のように庇ってくれる者はいないのだ。
自分達は貴族なのだと訴える子供には、貴族院を卒業していなければ貴族ではないと突っぱねた。
「自分達の魔力を誇りたければせめて小聖杯を8つ、一日で満たしてから口にしなさい。ローゼマイン様は貴族院に入学どころか洗礼式前でも鐘一つとかからず満たされました」
この頃のローゼマインはフェルディナンドと一緒に奉納したことは言わない。
「そんな…女神の化身と比べられても…」
「ええ、出来ないなら、アウブであるローゼマイン様にとって、あなた方の魔力はいくらでも代替えがきく程度、あなた方がどうしても必要な存在という訳ではないということです」
他者に必要とされたいなら、努力が必要なのだ。
ローゼマインもフェルディナンドも、フラン達が努力すれば報いてくれた。
だが、裏を返せば努力をせねば彼らについていくことは出来なかった。
それが分らぬなら、ローゼマイン様には不要だとフラン達は子供達を睥睨した。
神殿の孤児が一気に増えた状態なので、紙すきの道具と印刷機は早急に納品してくれるように手配をし、ハルトムートとクラリッサが率先してもとからいた青色神官と新たに青色神官となった者達を教育した。
貴族の血に縋るだけの役立たずは必要ないと、実家に関係なく仕事(ローゼマインへ)の貢献度で序列を定めた。
レティーツィアが孤児院長になり孤児院にはいったことで、孤児院の運営費の予算も別につけたから青色の実家の援助を当てにせずともやっていける状態で、今のうちに稼ぐ手段を身につけるようにとエーレンフェスト組は指導する。
お金を稼げば、それだけ食事の品数が増え、技術を学ぶ機会が増えるのだと知っている。
そして、ローゼマインは神殿や孤児達に対する偏見を少しでも改善しようと、神殿学校を始めたが、なかなか偏見は根深くて、思うように広めるのが難しい。
「平民の両親が働いている間幼い子供を預かる保育所のような場所をつくって、子供達へ神話の読み聞かせをしたり、子供達のトランプ大会やカルタ大会を開催して街の子供達との交流を広げたり、貧民街への炊き出しとか廉価の薬草園とか、もっと外に開かれた神殿を目指すのはどうでしょう?孤児達に同じ色の服を着せて神に捧げる歌を歌う『聖歌隊』とか作れば、もう少し周囲の見方もかわりませんか?だって、庶民は娯楽が少ないのですもの、毎週土の日に神話の読み聞かせと聖歌隊の合唱を披露して、参加者にはクッキーとか配れば神様に関心がない者達も釣れると思いませんか?」
原型はあちらの世界であった教会の日曜学校だ。
一応本気で考えた事業案を見せるローゼマインにフェルディナンドは眉間に皺を寄せた。
「話を聞きに来ただけで君のレシピの菓子を無償で配ると?君は馬鹿か?持出が多すぎるだろう!」
「えっと、えっと、だったら、小売するとか?」
はぁっと大きく息を吐き出したのは、気持ちを落ち着かせるためだ。
「神殿学校の件は、時間をかけることで君も納得しただろう」
「そうですけど…でも、神殿の者達が馬鹿にされるのは悔しいのです。うちの子はみんな優秀なのに」
肩を落とすローゼマインに、側近達が気遣わしげな視線を向け、フェルディナンドはいつものようにトントンと自身の蟀谷を指で叩く。
「君が盛大に祝福を溢れさせ、土地や海が回復する様をその目で見ていれば、神事がどういうものか、認識は嫌でも変わる。もう少し待ちなさい。…ただ、洗礼式では聖典ではなく、絵本の簡易な文体で読み聞かせるのは良いだろう。聖歌隊は歌を聴かせるのか?演奏ではなく、歌であれば孤児達でも何とかなるか。洗礼式や星結びの際に祝福の後で披露すればよかろう。神を讃える曲は用意出来るのか?」
「書きます!10曲でも20曲でも!子供達が歌うミニコンサートにすれば、目新しさから今まで神殿に来なかった人達も足を運んでくれるかも!そうだ絵本!フェルディナンド様、ヒルシュール先生のところにあった映写機、講義用の魔術具を作ってくださいませ。神殿の壁は白いので、そのまま仕えます。ヴィルマに絵を描いてもらって、それを写しながら神話を語れば、もっとわかりやすいはずです!」
「落ち着きなさい!」
ローゼマインの頭の中にあったのは、紙芝居だ。白い壁面に写しながら、読み聞かせが得意な神官に臨場感をもたせて語らせれば、子供達の興味を惹けるのではないか。歌も賛美歌を元にすれば、短くて覚えやすいだろう。合唱で有名な大地を讃える歌は、主旋律外のパートがうろ覚えだが、高校時代の合唱大会で練習したから大体は覚えている。
こちらでは、合唱という歌い方を聞いた事が無い。
皆同じ旋律を歌うのだ。ならば、ハモったり歌詞を掛け合ったりというのは、なかなか斬新ではないだろうか。
よし、神殿のイメージアップの企画を詰めようとヴィルマとロジーナをローゼマインが呼ぶのに、フェルディナンドは深々と溜息をついてから、仕方がないという風に苦笑した。
結婚式やクリスマス定番の賛美歌をロジーナに聞かせ、2声から3声の合唱に編曲させる。初めて聞く作り方に面食らいながら、ロジーナは楽しげにフシェピエールで和音を鳴らしながら合唱曲に編曲した。
ヴィルマは印刷用の白黒ではなく、色彩豊かに描いて良いと言われて喜んだ。
まだまだ色インクは高い。それに普段は印刷を考えて、あまり細い線や細かい描き込みはしないのだが、今回は背景も含めて、きっちり描き込んで良いと言われたのだ。
物語を絵で表現するというのに戸惑ったが、ただ立ち姿を描くのではなく、表情や仕草、描く角度や陰影で表現するのだとローゼマインに言われ、試行錯誤で何枚も描いたがまったく苦にならなかった。
ヒルシュールが扱えるようにと作った映写機は、普段フェルディナンドが作る魔術具に比べれば、消費する魔力はさほど多くない。
ローゼマインの要望により、拡大して投影されるように改良された。
白い壁に絵が映し出されればライムントなどは目を輝かせ、ザックは似たような物が出来ないかと思案している。
洗礼式では本物の祝福が領主様から贈られるのが庶民の間でも広まり、かなり遠隔地からも子供を連れてやってくる家族が増えていた。
そして、レティーツィアが緊張しながら式を進行させていたが、子供達のメダル登録が終わると今までの古めかしい言葉での神話ではなく、壁に映された神々の姿に、子供だけでなく親達も驚きの声を上げる。
孤児院で子供達に読み聞かせをしていた灰色神官が、声音を使い分けて絵本の易しい文体で語るのに合わせて次々変わる絵に子供達は釘付けだ。
レティーツィアの式進行が無事に終わると、孤児院の子供達が白に紺色の縁飾りのおそろいの衣装で登場し、『いつくしみ深き』のユルゲンシュミット版を披露する。
最後にローゼマインが盛大な祝福を贈れば、大歓声があがった。
よしっ!と密かに握りこぶしを作ったローゼマインは満面の笑顔で、「皆に良き未来が訪れますように!神に祈りと感謝を!」と両手を挙げるのに合わせて、神殿の神官達と孤児達も唱和をすれば、キラキラと祝福が舞った。
ちゃっかりと神殿の出口付近では、神話絵本やフィッシュアンドチップスを孤児達で屋台売りさせている。
ローゼマインは安価な庶民の食べ物の意識だったのだが、油が庶民には高価なので、フライというのは庶民の食べ物ではありませんよと、ユストクスに言われて慌てた。
フェルディナンドに本気で「君は馬鹿だろう」と呆れられたが、お祝いだから良いのですと押し切った。
カルフェ芋を櫛形に切って油で揚げて軽く塩を振った物と、白身魚の切り身を卵と水で小麦粉を溶いた液にくぐらせて揚げる。
大きめの葉に包んで大銅貨2枚。油が高いが、店舗と人件費がタダだから出来る価格だ。
そして、普段揚げ物など口にしたことがない人達が、おっかなびっくり食べて美味しいと驚く客の姿に自分もと注文する。
最初はぎこちなかった売り子の孤児達が、だんだんと嬉しそうな顔になって「ありがとうございました!」「神の祝福がありますように!」と声を出せるようになっていく。
「やはり、地元住民との交流って大事ですよね」
楽しげに笑うローゼマインが、少し形の崩れた白身魚のフライをフェルディナンドに差し出す。
卓につくことなく、立ったまま食べることに顔を顰めつつ、魔物討伐の折には回復薬を飲みながら戦闘を続けるのが当たり前なので、フェルディナンドは渋々という風に口にする。
フーゴやイタリアンレストランが用意するタルタルソースのかかったサクサクとしたフライに比べれば、こちらは油がべたつく。だが、不思議と不味いとは思わなかった。
「不思議ですね。決して美味しいものではないのに、なぜか『お祭り』で食べると美味しいと感じるんですよ」
「君は何を言っている?」
「フェルディナンド様と一緒に食べると、何でも美味しく感じるという話ですよ」
「ほう?わたしが処方した薬でもか?」
「改良してください。ブレンリュースがこちらで手に入らないのなら、切実にお願いします!」
「ほう……」
「ご自分でも毒と間違うような味は改善すべきです!」
確かにフェルディナンドの薬は味を犠牲にして効果を優先しただけあってよく効く。だが、薬とはあんな風に覚悟を決めて飲むものではないと思う。
普段、人前で取り繕う女神の顔で楚々とした態度とは違い、フェルディナンドに甘えているような、じゃれているようなローゼマインの態度に側近達は顔を見合わせて笑った。
こんな日常が続けば良いと願いながら。