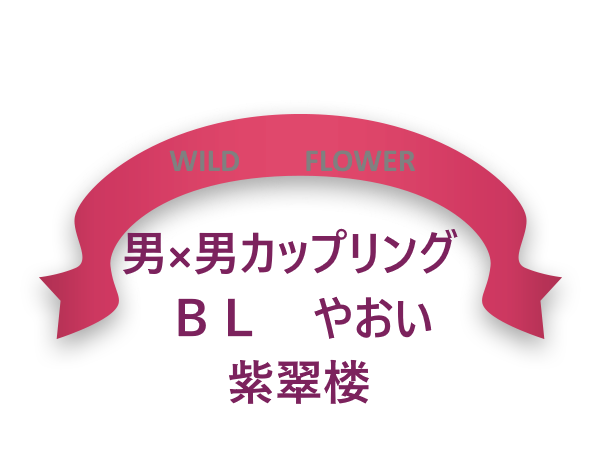箱庭の庭園1本好きの下剋上
フェルディナンド×ローゼマイン
真新しい白い建物の大広間には300人を超す貴族が並んでいた。
1段というより、5段ほど高い場所に、薄い水色の薄衣を重ねた衣装を身にまとい、艶やかな夜色の髪に月のように煌めく金色の瞳をした夜の化身のような女人が立っている。
そのすぐ側には昼の空を思わせる青い髪に、太陽を映したような強い輝きを放つ瞳の男性が。
玲瓏とした美貌ながら、まだ幼さを残した女人が、貴族たちを見降ろし、二コリと笑った。
「繰り返して言います。今後、私の統治するアレキサンドリアにおいて、平民を酷使し使い潰すような貴族は必要ありません。いくらこの地を魔力で満たそうと、土地を耕し、種を撒き、収穫する農民がいなければ、日々の食事は口に入りません。糸を紡ぎ、機を織り、服を仕立てる平民がいなければ、まとう衣装もありません。もちろん平民が貴族を軽んじても良いと言っているのではありません。貴族が魔力を注がなければ実りがないことを周知徹底し、相応に敬意と感謝をはらうべきだと知らしめます。ただ、貴族と平民はこのアレキサンドリアを支え、発展させる両輪であり、どちらか片方では成り立たないと理解してください。私があなた方に求めるのは、『高貴なる者は義務を負う』という自覚です。義務を果たすからこそ、特権が許され、尊崇を集めるのです。義務を果たさぬ者はこのアレキサンドリアでは貴族を名乗る事を許しません。私は今後、アレキサンドリアを豊かにするために魔力を注ぎ、神に加護を祈り、産業を興しましょう。私に従い、私を助ける気がないのであれば、身元保証の一筆をいれますから、それを持って近隣のブルーメフェルトなり、中央なりコリンツダウムなりに向かえばよろしいでしょう」
新領主の言葉にざわめく広間にいる貴族たちは顔を見合わせる。
上級貴族に名を連ねる一人が、我々貴族を不要と言い、軽んじられるのかと声を荒げれば、新アウブである女人ではなく、隣に立つ青年が冷ややかな視線を向けた。
「何を心得違いをしている。アーレンスバッハはユルゲンシュミットの人間を魔石としか認識していない外敵であるランツェナーベを引きいれ、領主一族はその資格もないのにツェントの簒奪を企て、元領主夫人であるゲオルギーネはエーレンフェストの礎を狙っての侵犯の末、返り討ちにあった。すでにアーレンスバッハは更地になって当然な大罪を犯しているのを、アーレンスバッハの礎を奪った新領主たるローゼマイン様の尽力と新ツェント・エグランティーヌ様の慈悲にてアレキサンドリアとして生まれ変わることで存続を許されたにすぎぬ。更地にするほうがよほど簡単であるものを、どれだけの負担と面倒を引きうけて存続させていると思っている」
「ですが、我らがおらねばそのアレキサンドリアとてたちゆきますまい」
「別に私とローゼマイン様の二人でこの地を魔力で満たすことは可能だ。多少時間はかかるだろうが、回復薬があれば問題ない。それにディートリンデらの愚行を止められなかったその方たちアーレンスバッハの貴族など、ただ魔力を注ぐ存在として生涯鎖につないだところで、殺さぬという女神との約束を破るわけではないから、なんら支障はおきぬ」
面倒なら、新たに分割して小領地をいくつかつくれば済む話だ。忘れているようだが、今のツェントはグリストハイトを持っているから領地の引き直しが可能だと、現状の把握が甘い貴族に対して、薄い唇に冷笑が浮かんだ。
「文章を書き、計算をするのに魔力は必要ございません。予算をたて、計画立案をおこない、企画遂行して修正するのに魔力の大小は関係がありません。行政能力がない者を文官として重職につけることは致しません。私や私の大切に思っている者に害意をもつ人間を傍近くに置く事はいたしません。上官の指示に従い規律を守れぬ者は、いくら強くとも軍の上官には就けません。アーレンスバッハではどうであったかは存じませんが、ここはすでにアレキサンドリアです。アレキサンドリアの為に自身の魔力を捧げ、私の方針に従って平民と協力する姿勢をとることが出来ぬというのであれば、十日以内に申し出てください。アレキサンドリア貴族であるという身元保証書を用意いたします」
自分が有能であり、アレキサンドリアでの待遇が不満だというのであれば、それを持って、中央なり他の大領地、もしくは元王族の領地なりに仕官すれば良いと新アウブ言い放った。
もちろん、身元を保証するだけで推薦するとも仕官先をあっせんするとも言っていない。人柄などをきちんと把握できていないのに、推薦などできるはずがない。
正直、どさくさに紛れてアウブに就任したようなものだし、最近地位が上がったとはいえ下位領地だったエーレンフェストの領主候補生で、成人どころかいまだ貴族院に通う未成年なのだから、アーレンスバッハの貴族全てが心服するなどローゼマインとて考えていない。
だからこそ、最初が肝心なのだと思っている。
とにかく、少数精鋭で、多少なりとも信頼できる者で固めなければ、それこそフェルディナンドが過労死してしまうという危機感が強い。
『ノブレス・オブリージュ』の思想がこのユルゲンシュミットには存在しないと理解している。だが、このアレキサンドリアはローゼマインの遊び場として好きにして良いとフェルディナンドは言った。失敗しても気にすることはないと。
ならば、財産、権力、社会的地位の保持には 責任が伴うことを指す『高貴なる者は義務を負う』という言葉を定着させたい。貴族であるということは、ただ搾取することが許されるのではないのだと、この地とこの地に住まう者たちを守り豊かにする義務が貴族にはあるのだと刷り込みたい。定着するには、世代交代ほどの時間がかかるだろうが、種はまきたいのだ。
宰相の位も考えたのだが、領主の補佐に『国王の補佐』を意味するその肩書をつけると、ローゼマインがツェントを目指していると誤解されかねないと思い、『城代家宰』という役職を新たに作り、その地位にフェルディナンドを就けた。
アウブである自分が不在時には、アウブの代理として領内政治における決済権と軍を動かす統率権を有し、ローゼマインが城にいるときはアウブを補佐し、助言する役職だと説明した。
ローゼマインが貴族院を卒業して星を結ぶまでの間、婚約者だからアレキサンドリアの執務を行うのではなく、行政官のトップだから決済権があるのだと、公的身分を与えた。
これに伴い、フェルディナンドは強権を発動する。
今まではアーレンスバッハにおける身分が、領主候補の婚約者でしかなく、客人の立場だったから提案はできても決済権がなく、強制できなかった。
特にディートリンデはフェルディナンドからの諫言を無視する傾向があったし、母親であるゲオルギーネはどれほど現場が混乱しても領内政治に関わらない姿勢をとっていた。
そして魔力不足をエーレンフェストが助力を拒んだという風にもっていき、反感をエーレンフェストに向けさせていたが、領主不在で領主候補生は領内統治の決済を面倒がるのでは実務を行う末端ほど作業が止まる。
だからこそ、実務を理解する上位者であったため、籍はエーレンフェストにある婚約者にすぎなかったはずのフェルディナンドに仕事が集中したのだ。
それが、ローゼマインは新たに領主に次ぐ地位を作ってフェルディナンドを任命し、領主代理である証として、『アウブ・アレキサンドリア之印』と飾り文字で刻み、特殊な色インクを用いて自分とフェルディナンドしか使えない魔術具の御璽を作って与え、フェルディナンドの立場を強化し、彼の命令は自分の命令に等しいと周知させた。
フェルディナンドは大きく方向転換を迫られた貴族たちが結託してローゼマインの統治に逆らう前に、組織の改編を進めた。
ローゼマインが思いつきで言った省庁を参考に、行政部門を8つに分け、司法を司る部署はアウブ直下の文官であり上級下級、役職の身分を問わず、不正に対して調査・摘発を行い、直接アウブであるローゼマインに申告できるとし、フェルディナンドがアレキサンドリアを私物化しているといわせぬ為の布石とした。
ローゼマインが口にした『夢の世界』の宣誓書の文面から起こした『私はユルゲンシュミットとアレキサンドリアにて発布された法規定、その他の諸法規を忠実に擁護し命令を遵守し職務に優先してそれに従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従って公正に、与えられた地位にふさわしい態度で職務の遂行にあたることを厳粛に誓います』という契約書に城で働く者、土地を託されるギーベ全てに署名をさせた。
契約書としてはかなり緩いもので、ローゼマインに従うことを強制するのではなく、今後はアーレンスバッハではなくアレキサンドリアの人間としてふるまえという自覚をうながすものだ。
最後の頃は大分外面の仮面が外れかかっていたが、それでも対外的にはキラキラしい笑顔と柔らかな物腰、洗練された所作などで取り繕ってきたため、婚約者であるディートリンデに対して献身的で優しい人という印象が強かった。
正直、フェルディナンド自身はディートリンデには見切りをつけていたので、おざなりな態度だったのだが、直接知らぬ者からすれば、年下の婚約者に頭が上がらず御せないと判断されていた面もある。
それだけにフェルディナンドの強権発動に周囲は驚愕した。
しかし、対ランツェナーベ戦や中央での戦闘指揮を目の当たりにした軍の者達はようやく貴族院在籍中、文官・武官・領主候補生の三コースで最優秀を獲り続け、ツェントの剣を自負するディッター狂いのダンケルフェルガー相手に負け知らずで今なお『魔王』と呼ばれることの意味を知った。
そして、ランツェナーベの侵攻を許した雪辱を果たす機会を与えられたことに感謝もした。
フェルディナンドは自身の力によって軍の主力を統率し、ランツェナーベ事変の折、アーレンスバッハの文官はなんの功績もあげていないことを指摘しつつ魔力差による威圧によって、城内の文官達を締めあげた。
怠惰で無能な輩は嫌いだと公言し、処分されて当然の身を救われたにも関わらず、アウブ・アレキサンドリアの役に立たず、全身全霊をもって仕える気がない者に用はないと言い切った。
ここでアレキサンドリアとして生まれ変わったことを示さねば、この先この地に生まれる者は皆、外敵を引きいれた犯罪者の末と蔑まれることが分かっているのかと。
「愚かなディートリンデの機嫌を取るだけで阿諛追従するしか能の無かった者をローゼマイン様の傍近くに置くつもりはない」
そう言い、貴族院でローゼマインに仕える者達もフェルディナンドが厳選した。
ローゼマイン自身は、内心どう思っていようと、きっちり仕事をしてくれるならそれで良いと考えていたが、フェルディナンドの心配がそれで減るならば、と特に逆らうこともしなかった。
実際、ディートリンデとその取り巻きに陰口を叩かれていたのは知っているので、擁護するほどの関心がなかったのだ。ただでさえやる事が山積みなのに、側仕えに気を回すゆとりがなかった。
そんなことよりも呼び寄せたグーテンベルクの受け入れと、念願の図書館都市の運営と本づくり事業の推進で頭がいっぱいだったし、そうなるようにフェルディナンドが誘導した。ある程度、城内に出入りする者達を篩にかけおわるまで、未成年アウブであるローゼ マインが表に出ないようにしたかったのだ。
領内が落ちついていない今年は無理に順位を上げる必要はない。
ただし、君は最優秀をとりなさいとフェルディナンドは貴族院にローゼマインを送りだした。
そして、ローゼマインが貴族院の図書室に行くために、今年も最短での一発合格を目指すと想像できるエーレンフェスト出身者達は、今までの空白時間を埋めるために必死で予習をし、試験に不合格で領主であるローゼマインにおいていかれる側仕えや護衛騎士など役立たずにも程があると、間違いなくフェルディナンド様に解任されると元アーレンスバッハの生徒達に忠告をしたため、新しく登用された者達も顔色を変えた。
実際、すでにアウブに就任している君が護衛や側仕えを連れずに出歩くなど認められるわけがない、在学中は学生たちの面倒ぐらいはみてやりなさいと言われていたので、自身の図書館ライフを満喫するために座学は最短での合格を目指しましょうね、とにっこり笑って脅した。
婚約の印にフェルディナンドが送った首飾りは、マーキーズカットとドロップ型の虹色魔石を24個使い、中央に大輪の花を配して首筋に沿って蔦がからむ豪奢なデザインで、より強力なお守り仕様になっている。
糸造りの花簪に添わせる形の虹色魔石の簪も、洗練されたデザインに凶悪な反撃の魔法陣を組み込みつつ装飾品としても一級品だ。
フェルディナンドの魔力を金色の細い綱にし、交差する箇所にビーズ状に加工した虹色魔石を通して網状にしたそれは手の甲から肘までを覆う。
敵意と悪意からローゼマインを守り、神々からの干渉も拒絶するために造られた装飾品を形にしたお守りの数々。
これだけでフェルディナンドにとってのディートリンデとローゼマインの扱いの差が顕著だが、ローゼマインもまたフェルディナンドに全幅の信頼を寄せている事を周囲に示した。
そして自分が留守の間もきちんと食事をとって休むように、と何度も念を押している様は周囲には微笑ましいと思える。
ただ、ローゼマインが貴族院に移った後、城に勤務する文官達のフェルディナンドから振られる仕事量は増えた。ローゼマインが留守中に雑事は片づけ、領主会議に臨むと言わんばかりだ。
情報収集と分析に優れたユストクスはフェルディナンドの指示で外に出ている事が多い。エックハルトは護衛として側にいるが、文官仕事もこなす。レティーツィアが孤児院長に任命され、ハルトムートが神官長に就任したが、現状信頼できる文官を遊ばせる余裕はなく、彼もフェルディナンドに招集されて城に詰め、新組織にまだ馴染んでいない者達を『ローゼマイン様の統治するアレキサンドリアに相応しい官僚』とするべく教育している。
星結びがまだで、籍もダンケルフェルガーにあったクラリッサだが、フェルディナンドの秘書として、スケジュール管理と各部署あげられてくる報告書の一次チェックを行い、不備があれば再提出と突き返す。
その際、「報告書もまともにかけないなど、どれだけアーレンスバッハの文官は質がさがったのでしょう」と溜息をついてみせ、「女神の化身であるローゼマイン様の足を引っ張ることだけは、断じて許しません。あの方の役に立てないならさっさと職を辞して魔力だけ奉納しなさい」と脅すのも忘れない。
その後、夏にそうそうハルトムートと星結びを行って、アレキサンドリアに籍を移したが、これはローゼマインの神事を体験するのは自分だというかなりどうでも良い理由からで、ダンケルフェルガーに話を通したのはローゼマインとフェルディナンドだ。
エーレンフェストに嫁入りすると押しかけていたのに、直前でアレキサンドリアに変わったことへの了承だったが、エーレンフェストの時は神殿にはいるなどどんな失点をおかしたのかと、反対したクラリッサの両親が、アレキサンドリアに嫁入りは諸手を挙げて賛成したのが意外だった。
やはり神官長を務めてもらうのだけど、と言ったが、文官でありながらアーレンスバッハの礎を攻める戦にもランツェナーベ戦にも参加したことが好印象になったらしい。
ローゼマインとフェルディナンド個人を高く評価していたダンケルフェルガーの領主夫妻が貴重なパイプと全面的に後押ししたのも大きかったが。
今では他領出身でも、ローゼマインとフェルディナンドに忠実で有能であれば取り立てられる見本として扱われている。
もともと警戒心の強いフェルディナンドのこと、信頼できる優秀な者達は仕事に忙殺されるので、早々にラザファムを召しだし、側仕えに任じた。
自分の魔力が少なく、家格が低い事を気にしたラザファムだったが、ローゼマインが直々にフェルディナンドに休憩と食事をとらせるようにと命じて注意を吹き込んだシュミルの魔道具とお守りを手渡した。
放っておくとまともに食事をとらないと見越して、ふわふわパンをつかったサンドイッチに具だぐさんのミネストローネのレシピをおいていった。
スープもマグカップにいれれば片手で手軽に食べられるし、具材を変えることで味の感想を聞きたいと言って出せば、つまむぐらいはしてくれるだろうと。
ただ10日もすれば、新作サンドイッチの組み合わせを考えなければならないフーゴは、ウンウン唸りながらはさむ具材の組み合わせをひねり出し、変わり種のサンドイッチも増えていたが。
艶消しをして鈍く光る金色の三段スタンドに白いプレート皿を載せ、サンドイッチとキッシュ、口金を注文して作った絞りクッキーと市松模様にしたアイスボックスクッキーに彩りも美しいフルーツタルト、しっとりしたスコーンを盛り付けると、ホイップしたクリームとジャム、脂肪分が多めでクリームより濃厚なクロテッドクリームもどきを添える。
これは、やっぱりアフタヌーンティーセットは3段よね、というローゼマインの記憶による。
直接手でつまんで食べるなんて、という人向けにフォークで食べるキッシュを用意し、指を洗うフィンガーボウルも準備した。のせるものでバリエーションを作りやすいタルトだが、カスタードクリームは一口食べただけでは真似することはむずかしい。よしんば材料がわかっても、火加減とタイミングが肝なのでそうそう同じものは出来ない。
だから今年いっぱいお茶会のお菓子はタルトで回せるだろうと。
一応、試食という名目でフェルディナンドにも出してみたが、書類を見ながらつまめるサンドイッチは気に入ったようだ。
甘みがあまり得意ではないので、小さめに作ったタルトレットぐらいがちょうど良いらしく、燻製肉を使用したホワイトソースとチーズのキッシュが口にあったようで。こちらもできたてでも、冷めてからでも食べられるので、仕事の合間に食べるのに適しているのが気にいった理由らしい。ローゼマインはフェルディナンドを食いしん坊だと認識しているが、食事がおいしいのだと教えたのがローゼマインなのだ。
もともと毒物を警戒するせいで、鋭敏な味覚はもっていた。それでも栄養がとれればそれで良い、他人が作ったものなど怖くて食べられないというのがフェルディナンドの認識だったのを、フェルディナンドの表情や食べるスピードから、彼の好みを考えてローゼマインが用意した食事。もともとは美味しい料理をだせばレシピと交換でお小言が減るかな?という程度のことであったが、それでもフェルディナンドにすれば自分のために美味しいと思える料理を用意されるという経験がない。
「美味しいですか?」「私の料理人は優秀なのです」と嬉しそうに誇らしげに笑って、フェルディナンドのためにいくつもの新作料理を用意し、アーレンスバッハに移動してからもこまごまと調理された料理に回復薬のための素材、レティーツィアへのご褒美用のお菓子など、フェルディナンドの立場を思って送られてくる気遣いの数々。
他領に移った者は捨て置けと言いながら、ローゼマインから与えられる好意にどれだけ助けられていたのか、神々に招かれたことが分からないまま途切れたあの時思い知った。
大切なモノは奪われるばかりで、だからこそエーレンフェストにおいていったのに、側にいなければもっと簡単に失ってしまうのだと知って。
供給の間で毒を浴びたあの時、本来であれば死んでいた。ならば、ローゼンマインに拾われた命なのだから、今後は彼女の為にこの知識も力も全て使おうと決めた。
彼女を守るため、彼女の望みをかなえるため、彼女が笑って暮らせるように、邪魔なモノは全て排除しようと。
彼女は慈悲深き女神の化身。ならば自分は畏怖される魔王で良い。王族であろうと神々であろうと、この手から彼女を奪うことは許さぬ。
そう思い定めて、彼女の婚約者になりおおせたのだから。自分が彼女に相応しくないことなど骨身にしみて知っている。それでも、ローゼマインが必要としてくれるならそれで良い。
もともと、フェルディナンドはその生い立ちのせいで、自分が必要とされなければ自身の存在理由を見失う傾向がある。
ローゼマインが甘やかしすぎだと呆れるほどに、ジルヴェスターから振られた仕事は全て引きうけた。義父からの信頼を得るため、ヴェローニカに攻撃の口実を与えぬため、役に立たねばこの地で生きていけないという刷り込みは、それほどに強かった。
そして今、ローゼマインの無茶ぶりに頭を痛めながら、どこか安心している。彼女には自分が必要だと思えるからだ。
年が離れていようと、未成年アウブを支える為には、実務ができる夫が必要で、本狂いで前世である夢の世界の記憶があるローゼマインの施策を理解し、実現可能なものに落とし込むことが出来て、彼女と魔力が釣り合う領主候補生の男など、そう簡単には見つからない。少なくとも、領主候補者の成人か成人間際の男にはいない。
彼女が成人するまでの二年間で、アレキサンドリアの地位を確立するとともに、フェルディナンド自身の存在価値を内外に示さなくてはいけない。自分以外に彼女の手綱がとれる者などいないと知らしめなくてはいけない。
だからこそ、フェルディナンドはローゼマインの希望をかなえるために全力を尽くす。彼女が自分にとって全ての女神であるように、フェルディナンドもまた彼女にとって全ての『男』でありたかった。