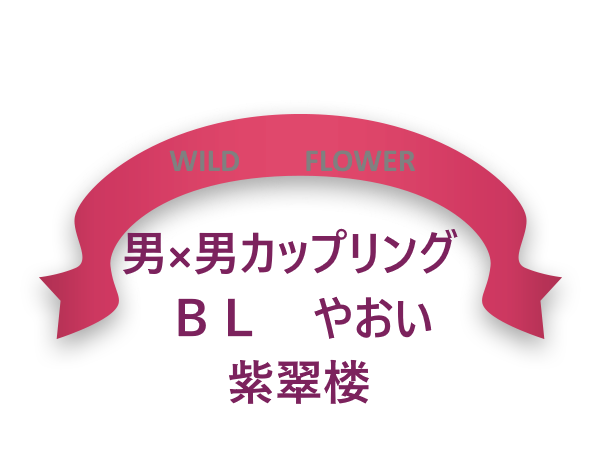鳴らぬ綾鼓 背中合わせに絡める指先1名探偵コナン
新一×志保
やれやれという風に新一達が戻ってきた。
騒ぎが拡大しなかったので、予想していた事件ではなかったらしいと、志保が安堵の溜息を漏らす。
「取り敢えず、糖分を補給したら」
そう言って、志保がケーキを乗せた皿を新一に向かって差し出した。
カスタードクリームとオレンジが乗ったタルトと、三種ベリーのムース、レモンのスライスをいれたアイスティーだった。
「サーバーに入っているコーヒーだと、どうせ口に合わないでしょ」
糖分とクエン酸補給とばかりのそれに、新一と降谷は苦笑いする。
真純が器にシーフードリゾットを盛って差し出してくれた。
それらを受け取った新一達に、赤井が説明が欲しいと促す。
悲鳴があがったのは、パーティーに参加していた客の一人が喉を詰まらせたからだそうだ。異物が気管を塞いで、明らかに様子がおかしいと周囲が慌て始め、急いで背中を叩いたそうだが、吐き出さない。
気道に詰まった物を吐かせようと、ある者が背中から抱きかかえるようにして圧迫したのだが、それをまどろっこしいと医者の一人が手持ちのグラスを割り、そのガラスの破片で喉を切ったため、悲鳴があがったのだという。
「割ったグラスの破片で気管切開をしたのね」
「ああ、軟骨を避けて、綺麗に筋肉組織だけ一発で切り開いていたらしい」
「良い腕だと思ったのだが、それを見た他の医者が、派手なパフォーマンスだと」
「まあ、そう言うわね」
「どうして?だって、切開しなかったら、息が詰まって死ぬかもしれなかったのに」
蘭と園子はまるでテレビドラマのようだったと、幾分興奮気味で、冷めた反応の志保の態度に不満げな表情を見せる。
「その喉を切られた人、日本人だった?」
「いや、ドイツ語を話してたから、バイエルンの関係者か、学会出席者じゃないか?」
慌てて救急車を呼ぶスタッフに対して、側にいた者に話しかけていた言葉はくせの強い英語とドイツ語だったと降谷が言い添えれば、志保は肩を竦めてみせた。
「それじゃ、その人病院で切開された喉を縫合する治療費全額自己負担か、煩雑な保険手続きしなきゃいけないわね」
「そんなの」
命を優先すべきでしょう!と蘭が志保に反論するが、志保は冷静な態度と口調を変えない。
「ここにあったグラスでしょ?雑菌による感染症のリスクは通常の処置室での切開より高いし、背中を叩いても吐かないから抱きかかえるようにして吐かせようとした人がいたのでしょう?なら、その人も医療系だろうから、何とか吐かせようとしたんでしょ。これ以上呼吸が止まったままはまずいと思って切開したのならともかく、吐かせるのがまどろっこしいで切られたら、患者にならずに済んだところが患者にされたようなものでしょう。切らずに済むなら、切らないほうが良いに決まってるわ」
呼吸困難を軽くみている訳ではない。酸素不足は脳障害を引き起こす危険もはらんでいる。だが、ここには医療従事者が多く、限界の見極めは出来るだろう。喉を切開したとなれば、消毒して終わりという訳にはいかない。外科的治療が必要になるのだから、患者には負担になる。
異国の地でもあり、患者の負担が少ない方を選ぶべきだろう、というのが志保の考え方なのだが、冷静な態度と口調が冷たい印象を与えてしまう。
実際、蘭達は、宮野さんはその場にいないから、当事者じゃないからそんなことが言えるのだと批難した。
そんな蘭達に志保は肩をすくめて、受け流してしまう。
切開して気道を確保したとしても、その異物はまだ残っているので、除去作業の必要性は残っている。皮膚一枚を切ったのでなく、切開したとなれば、縫合しても治癒には時間もかかる。
これで明日の仕事に差し障りが出たと、傷害を訴えれば警察案件だ。
医療行為と言えなくもないが、拗れる可能性だってある。善意のつもりが、そうではない事態を引き起こす可能性だってある。
割ったグラスでの切開など、そもそもの異物を除去出来ていないし、自分で最後までフォローしていないのだから、一時しのぎで自分の技量を誇示したいためのパフォーマンスだと言われても仕方がないと、志保は言う。
「どうしてそんな酷いこと言うの?」
蘭は眉尻を下げ、志保の言動に対して悲しげな表情をする。
蘭や園子は苦しげだった男の表情が、回復していく様を見ていた。適切な処置もしていたように思えるし、それはまるで医者ドラマのワンシーンのようにドラマチックだった。
凄腕の外科医だと周囲の人達も噂していた。
志保の物言いは、彼の善意を曲解して、ひどく捻くれているように聞こえたのだ。
「彼は苦しんでいる人の命を救ったのに、どうして悪く言うの?」
「……見解の相違だわ」
蘭は善意で良い面しか見ない。それを知っているから、志保はそれ以上は言わなかった。
「宮野、肉とってきても良いか?」
空気を読むのか読まないのか、新一が腹が減ったと志保に言えば、「ロースとカルビは不可、赤身もも肉か鶏肉ならかまわないわ」と答える。
嬉しそうに新一が鉄板焼きをしているコーナーにむかっていくのを志保が見送った。
「まだ工藤君の食事制限続いているんだ」
最近はサッカー部にも顔を出しているし、お弁当も量が増えているから、制限が外れたのかと思っていたと、世良が鶏肉のクリーム煮を食べながら、焼き上がりの順番を待つ新一に視線を向ける。
「ええ、管理はしているわ。タンパク質とカルシウム重視だから、ビタミンB群とCも必須。でも、そんなことを一々考えて食べても美味しくないでしょうしね。食事がストレスになっても可哀想だし、隠れて食べられたら余計に困るし」
これがアスリートであれば、食事も仕事のうちだろうと言える。だが、普通の高校生であり、べつにサッカーでプロを目指している訳ではない新一が、顔を顰めながら食事をする光景は、志保の想像でもためらいを覚える。
博士のダイエットが上手くいかない一番の理由は、志保に隠れておやつを食べているせいだと解っている。ただ厳しくするだけでは駄目だと、志保も学習したのだ。
栄養素に関しても、熱に弱いとか、水に溶けるとか、吸収率を高めるとか、いろいろ考えながら食材の組み合わせだけでなく調理法を考えるのは正直面倒だ。
自分の分だけならそこまで考えないのだが、工藤君を元の身体に戻すためと思えば手を抜けないと、志保が苦笑いを浮かべる。
「早く工藤君に好きな物を食べて良いと言いたいのだけど」
数字の改善はみられるものの、骨密度はまだ要注意。コナンであった頃のような、アクロバティックなターボ付きスケボーでの追跡は間違いなく自殺行為、強化シューズも足の甲や踏ん張る踵の骨が耐えきれるか不安だから使用禁止。
新一に戻ったものの、機動力と戦闘力いう点ではコナンの時よりも落ちている。
もっとも、高校生の新一が一般道や歩道をあのスピードでスケボーを走らせたら、人身事故が起きる可能性が跳ねあがるし、あの改造スケボーは道路交通法的にアウトだと降谷にくぎを刺されているので、移動は交通機関を使うようにしているが、時々スケボーが使えないことに苛立ちを覚えている風なのがわかる。
今の新一の方が、警察に協力はしやすくなった反面、戦闘力と機動力は落ちた。
やはり、全てが上手くはいかないものだ。
基本的に、新一は志保が作った物以外は口にしなくなった。何が入っているのか分からない物は怖くて口に出来ない、というのは降谷のような者達にとって職業病のようなものだが、毒殺された被害者を散々見てきた新一も、作り手や素材が分からない物は躊躇してしまう。
蘭が新一を害する料理を作るとは思っていないが、知らず入っている可能性はあると思っている。それに、善意からよかれと思ってやった事が、逆の結果になることは十分考えられた。
普通に作ったとしても、新一の好物だから、この方が美味しいから、そう言って1食分のカロリーが簡単にオーバーしそうだなと思う。そして、新一が料理を残そうものなら怒りの鉄拳が飛んできそうだ。
一食ぐらいなら問題ないかもしれないが、それは他の二食で補うのが前提の話だ。
だが、蘭の場合、せっかく作ってあげたのに、というのが先に立つ。
志保は新一の食事の様子を見て、体調をはかる。食欲が無いのなら、あっさりしたものが良いのか、喉ごしが良い物に変えようか、香辛料をきかせてみようか、献立の変更を考えはしても、無理に食べろとは言わない。吐いたら余計に体力を消耗するから、無理をするなと言う。
新一が喜ぶと思ったのに、そう言いながら期待する反応が返ってこないと怒る蘭の態度は、新一を疲弊させる。
食事をしながら、血なまぐさい事件の話をしても(顔を顰めてはいるが)、話題がどこに飛ぼうが、志保は話題についてきてくれる。
思考が事件に飛んでいる新一に、呆れはしても、自分の話を聞いていないと怒り出すことはしない。新一の意識が戻ってきてから、改めて話を振る。
そんな志保の間合いに慣れれば慣れる程、蘭との距離が難しくなる。
蘭が志保の作る弁当や、三度の食事に複雑な顔をしていることは承知しているが、蘭が工藤邸に通って料理を作ることを受け入れる気はなかった。
一度でも承諾すればなし崩しになるのは分かっていたし、ようやく数字が改善しはじめた所なのに、蘭の自己満足に付き合って悪化させるつもりはなかった。
今のまま、思うように動けないのは本当に困るのだ。
だから、自分の食事は志保の管理下にあることを、たびたびアピールするようにしているのだ。
蘭のことは好きだった。大切に思っていた。
それでも、これから先、探偵として生きたいと願うなら、蘭との間に線引きをしなくては駄目なことも分かっていた。
彼女はまだ、理解していない。日常の重み、非日常の危険、それは常に表裏一体で新一の生活だ。
それなのに、彼女は未だ夢見ている。自分が新一の特別であることの意味をはき違えたまま、自分の側に新一がいて、自分を守ってくれることを。
蘭のことを嫌いになった訳ではない。それでも、これ以上は無理だと思った。
彼女を血なまぐさい事件に関わらせたくないし、理解できるとも思えないからだ。蘭の理想の『工藤新一』ではいられない。そのことに、早く気がついて欲しいと、最近はそれを強く願っている。
新一が鉄板で焼かれた赤身の牛肉と野菜をもらい、志保達の元に戻ろうと向きを変えた瞬間、パンッと乾いた音とともに、ガシャッとグラスが崩れ割れる音が、壇上に近いエリアで響いた。
咄嗟に新一が振り向いた先、スーツを着た男が、拳銃を構えて左腕で人質の首を羽交い締めにして「下がれ!」と叫んでいる。あちこちで悲鳴が上がり、逃げようとする客達と、警備を呼ぶ怒声が入り交じる。
駆け寄ろうとする足を無理矢理止め、新一は出入り口に視線を向けた。
拳銃を所持している男達はざっと見て3人。その内、2人は人質をとっている。
日本語だけでなく、英語とドイツ語が入り混じり、我先にと出口に向かう客と、オロオロと慌てるスタッフの姿、カシャンッガシャンッと皿やグラスが落ちる音。
人込みに押されて、転んだ男性客に手を差し出し助け起こす。
犯人側を振り返って一体誰だと、表情を厳しくする新一の視線の先、逃げようとする客の集団から離れた志保が前に出た。
「その人は心臓に疾患があり、持病をもっていて定期的な薬の投与が必要なの。人質なんて精神的負担が高い状況になれば、発作をおこすリスクが高まるわ。だから、解放して。人質が死んだら、あなた達も困るのでしょう?」
「志保!」
「志保さん!」
赤井と降谷は咄嗟に一般客の安全確保と避難誘導に身体が動いていたため出遅れ、志保を引き戻そうとするが、彼女がまた一歩踏み出す。
「お前は誰だ?」
「彼の主治医よ。そして、彼に死なれると、私の社会的立場も無くなるの」
「……だったら、お前が代わりの人質になると?」
「彼を解放してくれるなら。それに、彼がドイツ語で何か叫んでも、あなた達はそれを理解できるのかしら?」
「……わかった」
『シホ!駄目だ!』
先ほど、志保がサー・ウォーリックと呼んだ初老の男を解放する代わりに、近づいた志保が羽交い締めにされ、壁沿いまで下がった犯行グループの3人は、他は出て行けと叫んだ。
『大丈夫ですか?サー・ウォーリック』
『私は大丈夫だ。それよりもシホを助けてくれ!』
『勿論です』
解放されたウォーリック氏を引きずるように犯人側から引き離しつつ、新一が力強く頷いて、回廊側まで退避させると、同じく客達の退避を誘導した降谷と赤井が、一端ツインタワーの会議室へと客達を集めていた。
警察にはすでに連絡がいっているだろうから、とにかく従業員に向かって会場にいた客と関係者を集めるように依頼していた。
「ボウヤ」
「新一君、サー・ウォーリックは?」
「取りあえず、あちらで休んでもらっています」
「志保が彼の主治医というのは?」
「大嘘です。別に持病もありません。ただ、お孫さんがもうすぐ生まれるそうで、今晩にでも成田からイギリスに戻る予定だったとか」
その赤ん坊が未熟児で、帝王切開手術になる可能性が高いので、祖父として、父親として娘の出産時には側にいたいというのを志保が知っていたらしい。イギリス人であるサー・ウォーリックはドイツ語に堪能ではない。それでも犯人側も英語は理解できてもドイツ語を理解できる日本人は少ないだろうと、はったりをかまして逃がしたようだ。
人質になり、焦ったサー・ウォーリックが犯人側を刺激する危険も考慮したようだが。
溜息をついたのは、新一だけでなく、赤井と降谷もだ。
そして、会議室から出て行こうとする赤井を降谷が呼び止めた。
「何処へ行くんです?東都大大学院生の沖矢昴さん?」
「ちょっと知り合いに連絡を」
「大使館の知り合いですか?」
「……この距離でしくじるとでも?」
「日本警察にもSATはいる。必要と判断されれば投入される。ただの大学院生が何をするつもりです?」
この国を治外法権と思っているわけじゃないだろうな?と降谷が視線に力を込める。
いい加減、FBIが好き勝手に日本で銃を使用するのは辞めて欲しいものだ。痕跡をもみ消すのがどれだけ大変だと思っているのか。
(もっとも、こんな台詞を部下の風見あたりが聞けば、降谷さんも自分の行いを少しは省みてくれと嘆息しそうだが。)
700ヤード(640メートル)先の的を狙える赤井の腕なら、宮中庭園もしくはツインタワーの部屋からレストラン内部の犯人を狙うのは難しくはないだろうが、降谷は自分の前でそれを許す気はなかった。
そもそも、日本の大学院生は実弾のライフルを所持していない。
そして、人質は志保だけではない。鈴木財閥の代表でもある園子の父親もまた、人質になっているのだ。
赤井の勝手を許せる訳がなかった。
サイレンを鳴らし、警察車両が到着すると、ツインタワーの出入り口も一端封鎖され、エレベータで上がってきた警察官達が会議室に入ってくる。
お馴染みの一課3係の目暮班のメンバーだけでなく、多数の警察官も入室してきた。
今回、このパーティーの司会進行を担当していた鈴木財閥系列のファルシアの社員がオロオロしながら事情を説明している間、机の上にノートパソコンや機材などが設置され、避難してきた客達に警察官がそれぞれ身元確認をしつつ各が見た状況の説明を求めている。
見知った顔を見つけた高木刑事と佐藤刑事が、新一達に近づいてきた。
「工藤君、どうしてここに?」
「園子に招待されたので、皆で来ていたんです」
「ああ、園子さんも今回は大変でしたね」
「ええ、父は大丈夫でしょうか?」
「我々も人質救出を最優先で対応いたします」
「よろしくお願いします!」
縋るような表情で頭を下げる園子に、高木達は痛ましそうな顔になる。彼女もよく事件現場に遭遇するが、どちらかと言えば当事者というより観客のような態度でいることが多い。
それが、今回は自分の父親が銃を持って立てこもる連中の人質になったのだから、さすがに顔色が悪かった。
そして、園子の母親の朋子と姉の綾子、相談役である次郎吉も到着すると園子はほっとしたような表情になって泣き出した。
「園子、お父様は大丈夫よ」
「警察の方を信じて待ちましょう」
「お姉様ぁ…お母さまぁ……どうしてぇ……」
園子の肩をさする親子達をおいて、次郎吉は「警察は何をやっているのか!さっさと犯人どもを逮捕せんか!」と怒鳴る。
「まぁまぁ、落ち着いてください」
と高木刑事が宥めるとともに、悪意を持つ者に心当たりは無いかと尋ねて、余計に次郎吉は怒りを募らせ「鈴木財閥を敵に回せばどうなるか思い知らせてくれる!」と拳をテーブルに叩きつけた。
「高木君、別室にお連れして」
と佐藤刑事が促し、高木刑事が次郎吉を隣の小会議室へと案内すると、他の警察官達がほっとした表情になる。
警察が不甲斐ないと、怪盗キッドの逮捕を生涯の目標に掲げ、なまじ財力と権力があるせいで、なにかと警察の指示を無視して独断で動く気のある次郎吉は取り扱いが難しい。
警察に任せておけないと、彼が勝手に動くことのないように見張りを付けようと目暮が指示を出した。
「おや、工藤君だけでなく、安室君と沖矢君もかね」
「ご無沙汰しています、目暮警部」
「僕もこんなところでお会いしたくはなかったのですが」
「全くだ」
いつものラフな格好に比べて、三人ともフォーマルな装いなせいか、普段よりも華やかな印象だが、顔つきは随分と怜悧なものになっている。
どうして探偵ばかりがという雰囲気をにじませてはいたが、素人は黙っていろといっても、退かないのだろうと、どこか諦め顔の目暮に、当然とばかりに新一達が頷いた。
実際、警察がくるまで、一般客を避難誘導するとともに、会議室に会場スタッフ達を集めるなど、段取りを整えてくれている。この辺は、場慣れと言いたくはないが、やはり手馴れている感はある。
園子の側には蘭がついているからと、真澄はレストランスタッフ達の側に控え、身元や事情を尋ねる警察とのやりとりを聴いている。
「取りあえず、現在で分かっていることをお知らせしましょう。白鳥君」
目暮がそう言うと、朋子に向かって白鳥警部がメモを読み上げる。
主犯と思われるのは、元警察官で退職後警備会社に再就職していた日高義人。このビルの警備を請け負っている鷲尾警備の社員で、今日は来客が多いのでヘルプとして参加していた。
他のメンバー2人は今調査中だが、単発バイトでレストランの配膳のヘルプや車両誘導でこの場にいた人間、犯行グループの目的は未だ不明。
とにかく、出入り口を押さえているが、持久戦も覚悟して欲しいと言った。
それを聞くと、覚悟を決めたのか、朋子と綾子はしっかりと頷いた。
「あと、鈴木財閥や鈴木史郎さんに恨みを持つ人の心当たりはありませんか?」
「申し訳ありませんが、漠然としすぎていてわかりません。取引を停止した先もございますし、入札でうちが取った案件もございます。不動産や株で損をした方もいるでしょうし、系列会社を含めれば、どこで恨みを買っているかなど、わたくしどもでは把握できません」
たしかにその通り、としか言いようがないが、今のところ日高義人と鈴木財閥や鈴木史郎との接点も見つからない。
「目暮警部」
「浅輪君か」
「はい、今回こちらのサポートに入るようにと」
「わかった。くれぐれも勝手に動かないでくれ」
複雑な表情の目暮に対して、高木と同年代ぐらいに見える人の好さそうな男が、穏やかに笑う。
彼の後ろには5人ほど控えていたが、すぐに各々が動き出している。
「特捜班が出張ってきたか」
「特捜班?」
園子達に話しかけている浅輪という刑事に視線をやりながら、降谷がつぶやくと新一が聞きなれぬ名前に問い返す。
「ああ、元一課の9係がメンバーで、初動捜査から起訴まで迅速に行うために創設された警視総監主導で創設された部署だが、失敗したら責任を押し付けるつもりだろう」
犯罪発生の増加にともない、9係が創設された。とにかく扱いにくい人間の集まりだったが、少数体制でありながら検挙率は断トツだった。そのメンバーをそっくり移したのが特別捜査班。今回、鈴木財閥がらみの案件で、救出に失敗は許されず、怪我でもさせれば問題が大きくなる。警察は精一杯やったというアピールと何かあった時に責任を押し付けるために投入されたという面もあるだろう。
「もともと9係の係長が変わった人で、上意下達の警察にあって、部下が自分で考えて動けるように指導した人だ。はっきり言って彼が仕切った方が効率が良いだろうに、いちいち部下に考えさせた。工藤君はすぐに解答を教えてしまうが、彼は部下が行き詰まったり、迷走しかけたらヒントを出して誘導しても、自分から指示を出さない。違和感をどうして感じるのか、本人が落とし込んでいかないと経験にならないという方針だったようだね」
コナンだった時もそうだが、新一は犯行現場で早急に犯人を逮捕することを優先する。犯人を逃がしたり、証拠が消されることを恐れてなのだが、解答を聞くだけでは問題の解き方は理解できない。だが、目暮警部も迅速な逮捕を望むので、眠りの小五郎や工藤新一が語る『解答』を受け入れてしまう。その点、問題を解くには反復し、自分で考えなくては身に付かないと、その9係の課長は部下自身に考えさせて、捜査をやらせる人だったらしい。
「まあ、まったく指示がでないことについていけない部下もいたけど、残ったのは皆優秀で、少数でありながら機動力は一課随一、取りこぼしがなく起訴率の高さも抜きんでていた。ただし、上の指示にも従わないことでも有名だったけど」
上からストップがかかっても、捜査を続行すること数知れず。それでも、犯人を逮捕し確実に起訴まで持ち込めるまで揃えるから、その検挙率と実績から不問に付されることが多かった。
3係の目暮班は外部の探偵を名乗る一般人の推理を重く扱い過ぎるという向きもあったが、逮捕までにかかる時間の短さと、かろうじて眠りの小五郎が元警察官であることから黙認されていた。
少なくとも、小説家の工藤優作や、キッドキラーとマスコミに書かれる小学生に比べれば小五郎の方が数段ましだと。
「その9係が特別捜査班に?」
「係長の加納さんをこっちに呼んだから、しわ寄せもあるかな」
ある意味、苦労が多い割に評価されない貧乏くじを引きたがるキャリアがいなかったとも言える。
「変人呼ばわりされてるけど、元々加納さんは優秀で、仕事に縄張り意識持ち込まない人だから、内閣テロ対策室に来てもらっていてね。それで残された部下を守る人も、無茶を止める人もいないから、不祥事の責任押し付けられて一旦は解散させられたんだよ」
2020年のオリンピックに向けて、警視庁、公安に検察庁の官僚、民間の警備会社や空港や列車などの輸送機関、いろいろな人間が集まる部署だけに擦り合わせが難しい。
警視庁からアドバイザーとして参加しているが、加納倫太郎は所属する組織に遠慮もしないし、威圧的な態度もとらず、忍耐強く言葉を重ねるので、調整役として適任で、少なくともオリンピックまでは返すに返せない。面子も大事だが、テロを防ぐ事以上に重要なことはないと、軸がぶれないので彼の言葉と態度は信頼されるのだ。黒の組織殲滅戦では、公安のスタンドプレーだと批判する警視庁と官僚を宥めてもくれた。
それだけに、自身が不在の間に9係を解散させられたことに思う所が無いはずはないのだが、彼らはどこででも警察官としてやっていけるからと言った。
目暮警部や高木刑事は最初の頃こそ小学生であるコナンが事件現場にいるのを気にしていたが、だんだんとコナンが表情を変えたり、首を傾げる仕草をすれば何か気が付いたことがあるのかと尋ねる様になった。
コナンである新一にすれば話が通りやすくなって助かったのだが、降谷から見れば、どんどん警察官としての察知能力が劣化しているように思えた。
ただ、事件の長期化、特に凶悪犯罪の場合はマスコミに叩かれるし、独自取材と銘打った『容疑者らしい』とマスコミが報道するために起きる二次被害を考えると、目暮達が迅速な犯人逮捕を望むのもわかるのだが。
それでも自分で考えず、他人に頼ることが当たり前になれば、指摘されるまで犯人側のミスリードに気づかず、初動捜査を誤ることになるだろう。日本において捜査権は警察にしか許されていない。そのことの意味を理解して欲しいと思うのだが、降谷自身も事件現場に居合わせると、つい自分から解答を示してしまうのは、降谷自身が早期解決と迅速さを求めるせいだろう。もともと説明の足りない降谷についてこれる部下は少ないが、最近は特に降谷の命令に疑問を差し挟まないように要求するせいで、部下を育てることが出来ていないような気がする。
このあたり、迂遠にも思えた加納倫太郎のやり方が、部下の個々の能力を上げるためだったと解る。
実際、何を考えているかわからないと、新任当時は振り回されていた浅輪刑事だが、自分の頭で考えて動けるようにまでなった。
犯人逮捕という面において優秀ではあるが、風見のように上の指示には意味が解らなくても飲みこんで従うということをしないので、上層部や管理官にとって扱いにくいというのが元9係のメンバーに対する評価だ。
彼らが出てくると、多分、目暮や上の指示に黙って従うことはしない。それが今回は吉と出るか、凶と出るか。
上手く誘導できれば良いのだが、彼等の場合、根回し下手だから、後始末が厄介なことにならなければ良いと思ってしまう。