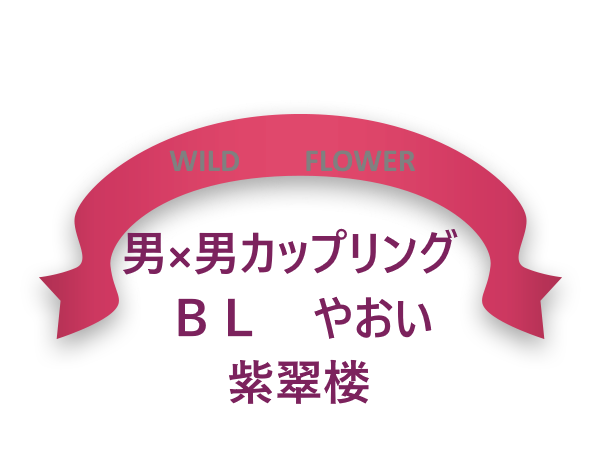触れぬ指先 恋の淵4名探偵コナン
新一×志保
パーティー当日、15分前に会場の入り口で待ち合わせると、真純と新一が先に来た。
新一はネイビー色のスーツだが、ベストはペイズリー柄のワイン色で、学生服には見えない。
真純は女性物だがボルドー色のパンツスーツ。まあ、ドレスを着たくなかった真純が、エスコート役が新一だけだとバランスが悪いだろうと言うのを言い訳にしたのだが。
女性陣である園子と蘭はメイクと髪のセットで身支度に多少時間がかかると連絡が来ていた。
高校生の場合、制服が正装扱いなので、普通公式の場は制服ですんでしまう。
ピアノなど楽器の演奏をする者ならば、発表会やコンクールでドレスなどの正装をすることもあるだろうが、一般の高校生なら親族の結婚式に参加する時にフォーマルワンピースを着る程度だろう。
立場上、パーティーに参加する機会が多い園子は、昔から蘭を誘う時は自分のドレスの中から貸したり、会場のホテルなどで借りたりするのが当たり前になっており、蘭も自分でドレスを毎回買うのは無理だと、借りることに抵抗はない。
園子は友人を呼ぶ感覚、蘭は友人である園子に呼ばれてちょっときらびやかな世界を垣間見る程度の感覚で、会場で有名人に会えると興奮し、大人の世界を見ることで、クラスメイトに対する少しばかりの優越感を感じるので、パーティーに出るのは嫌いではなかった。
新一はなまじ両親が有名人だったせいと、子供時代から優作達はシッターに任せて家に新一をおいて出かけることはなく、一緒に連れて行く代わりに場にあわせた態度を教えていたので、この年になればTPOに合わせて相応に振る舞える。
真純も上の兄が"太閤名人"と呼ばれる天才棋士の羽田秀吉なため、数は多くないが公式の場に出る機会はある。
普段、あまり会う機会はないのだが、タイトル戦の時の前夜祭や、スポンサー企業や後援会主催のパーティーで、花束を渡す役目で呼ばれることがある。
下手な相手に頼んで週刊誌のネタにされるよりはと、妹の真純を呼ぶのだ。
絵的にも、妹が応援やお祝いのために駆けつけたという図は、周囲の反感を買いにくい。
真純自身が棋士を目指している訳ではないので、棋士とその関係者ばかりの会場では場違いだと感じることも多いのだが、真純の無知と恥は秀吉の評価を下げると理解しているので、挨拶はきっちりとするように心がけ、言質を取られる事が無いようにそつなく振る舞う。
逆にそれが出来ないなら公の場に出るな、と母親のメアリーに釘を刺されている。
このパーティーは棋士・羽田秀吉の仕事の場、場を乱す人間が出て良い場所じゃないと。
最低限、パーティーの趣旨と、主催者や当日の招待客について調べてから参加するのが新一や真純の常識なのだが、園子は自分は財閥とは無関係という意識から無頓着で、蘭はそもそも知る気がなく、コナンだった時も子供扱いで事前に聞ける情報は少なかったが、今も園子から新一達に情報がほとんどおりてこない。
「何か聞いたか?」
「とりあえず、鈴木財閥の医療系部門のファルシアが、アメリカの企業を買収しようとしたけど、他社の横やりが入って、合同出資での再建に落ち着いたらしい。今回のパーティーは、その互いに握手をした3社が再建に向けて研究所を作るっていう発表の場みたいだね」
「ふ~ん、お互いに手打ちで納得してれば良いが、内心大荒れって?」
「どうだろうね。会場の空気でそのあたりは分かるかな」
「人間関係面倒くさそうだな。ここは園子の言うとおり、自分は分かりませんって顔でひたすら食べるか」
「ご飯が美味しいと良いね」
そんな会話をしているとき、園子と蘭が「お待たせ」と姿を見せた。
園子はパステルイエローの柔らかなシフォン生地を重ねたワンピースドレスに同色のコサージュをつけていた。蘭は光沢のあるサテン生地で、裾がアシメントリーになっているマリンブルーのワンピースドレスだった。
どちらも派手すぎず、若い二人には良く似合っている。
真純がボルドー色の細身のラインがすっきりとしたパンツスーツに華やかなドレスシャツを着ているのを見て、宝塚の男役みたいだと蘭と園子がはしゃぐ。
「宮野さんは?」
「ああ、別口で参加するって。オレと一緒だと事件に巻き込まれる予感しかしないし、オレと世良の二人だとエスコート役が足りなくてあぶれるからってさ」
自分は他に当てがあるから、新一と世良は蘭と園子をエスコートしてやれと言ったと。
「ほらほら拗ねない。でも宮野さんがちょっとうらやましいかな」
「そうだよ、あっちが世良をエスコートすべきだろ」
「それだと、男三人で女四人、やっぱり一人あぶれるじゃないか」
いい加減諦めろと真純が呆れるが、新一は不満顔だ。
「宮野さんは誰かと来るの?」
「まあね。アメリカから来たしつこい追っかけを追い返すのに、工藤君だと弱いからね。身の程をわきまえない奴に釘をさすなら大人の男の出番でしょ」
「あの人達だと相手の頭に、釘じゃなくて銃弾ぶち込みそうだけどな」
「日本だから、そこまであからさまにはやらないよ」
アメリカの大学の関係者がしつこく志保に会いたがっているというのは、結構学校で出回っていて、志保の情報を流さないように、怪しげな外国人には近づかないようにと注意もされている。
「宮野さん、何かやったの?」
どこか不信の混じった声で蘭が問えば、新一と真純が溜息を吐く。
「やったというより、やらないから文句を言われてる。宮野の残した研究を引き継いだのは良いけどクリスフォードとか言う奴が手に負えなくなって、呼び戻そうとしたのにあいつが了承しない。条件を釣り上げるつもりかと誤解して、文句をまくしたてたかと思えば、どんな条件なら戻ってくるのかと下手にでたりで」
「今更、高校生活なんて時間と才能の無駄遣い。君の才能はもっと世の中の大勢の人のために使われるべきとか言って、囲い込みたがっているのがバレバレ。下心が高校生に見透かされるってどうなんだろ」
「あいつ同年代と過ごした経験がほとんどなくて自己評価低いし、面倒くさがりだからなぁ。多分争うのが面倒とかで、問題無く単位をくれるならと自分の論文や研究レポートを簡単にくれてやってたんだろ」
「それが誤解されたと。強く出れば言う事を聞くと思っているから、あんな大声で怒鳴るんだね。だったらやっぱり、工藤君よりあちらに任せた方がいいよ」
「分ってるよ!高校生じゃなめられるんだから、向こうに預けるしかないってことぐらい!」
感情は納得していないと丸わかりの態度に、真純がヤレヤレと言う風に肩を竦めてみせた。
宮野さんは頭が良い、と周囲の噂でも聞いていたが、園子と蘭はそれをいわゆる『勉強ができる秀才』と呼ばれる範疇で認識していた。だから、大学関係者が志保に会いに何度も来ていると聞いたときも、大袈裟だと思っていたのだ。
それなのに、新一と真純の会話だと、本当にアメリカの大学関係者が志保に会いにきているのだと驚いた。
「ええっと、先に会場で待っていよう。遅れる訳にもいかないし」
園子が皆を促して、パーティー会場にはいる。
今回の会場は、臨海部に建つ地上35階建ての隣同士二つのビルを繋ぐ場所に設けられた空中庭園の中にあるスカイレストランだ。
回遊式の庭園はガラス張りの温室に近く、南方の低い樹木や色鮮やかな花も植えられている。
低層階は店舗フロア、高層階はオフィスフロアのツインタワーは、鏡面仕上げの真新しいビルで、見上げれば空、周囲を見渡せば空中庭園と西側に夕日が沈む海が見えるドーム型円形のレストランは結婚式場としても人気だ。
受付をすませて中に入ると、園子の言うとおり外国人が多く、客層はスーツを着た三十台以上がほとんどで、二十代はちらほらといる程度。どこから見ても未成年の新一達はあきらかに浮いている。
たしかにこれでは園子一人だと居心地が悪いだろう。
「料理は美味しいはずだから、好きな物を食べて」
もともと創作フレンチのレストランだが、今回はビュッフェ形式で料理を並べている。
生ハムやサーモン、色鮮やかな野菜と鰻のテリーヌなどの冷菜だけでなく、リクエストを受けてから焼き始める黒毛和牛のステーキやエビにホタテの海鮮、有機野菜の鉄板焼き実演を行うシェフも待機している。
アルコールだけでなく、ソフトドリンクもパック入りのジュースではなくカットしたフルーツが並べられている。
盛り付けが華やかな海鮮ちらしとフライヤーでその場であげる天ぷらは、外人向けの和食ブースらしい。
もちろん冷めないように湯を張ったチェーフィングディッシュも置かれ、アルコールランプが灯された銀色の器には舌平目とリコッタの白ワイン蒸しや、穴子とマイタケのポワレなど、通常のビュッフェでは見ないようなパーティー料理が準備を終えて並べられている。
デザートはまだ並んでいないが、こぶりなタルトレットやガトーショコラ、和三盆のクッキーに抹茶のロールケーキなど、可愛らしいお菓子も用意されていた。
最初の挨拶だけ行ってくると園子が席をはずし、新一達はジンジャーエールやオレンジジュースなどのソフトドリンクを手にビュッフェの近くに固まっていた。
壇上の三人の挨拶と、客達の会話から、今回のパーティーはアメリカの製薬会社の一つを鈴木財閥が援助し、EUとアメリカの企業と提携して合同出資で研究所を運営していくことをお披露目する場らしい。
もともと今回三社が救済のために援助を決めたホワイトフェザー社というのは、会社規模は大きくないが、新薬や特許の数が多く優良企業と思われてきた。
ところが、不祥事で経営者一族がのきなみ逮捕され、帳簿を精査すれば多額の使途不明金が発覚。分割して売却の案も出たが、この会社が持つ研究所には優秀な研究員が多く、分割するのはもったいないと、鈴木財閥の医療系部門ファルシア、ドイツEU系企業で医療機器のシェアが大きいバイエルン、ユダヤ系アメリカ企業で製薬会社のブリトリア、の三社がそれぞれ30%、30%、35%の株を取得し、業務提携することに合意した。
丁度、時期的に千葉県でがん治療に関する国際学会が開かれていたので、会社関係者だけではなく、三社とつながりのある医療関係者も多く参加している。
そのせいで、交わされる会話は専門用語が飛び交い、日本語よりも英語のほうがよく聞こえる。
会場は華やかというよりは落ち着いた雰囲気で、穏やかな懇親会という感じで皆食事と会話を楽しんでいる風だ。
特に人が多いあたりは、どうやら有名な医者達と医療系企業の面子らしく、挨拶に入れ代わり立ち代わり人々が訪れている。
普段、園子が蘭達を呼ぶパーティーのようにテレビでよく見るような著名人のゲストはおらず、ほとんどが30代以上の医療従事者か医療系企業とあって、どうしてこんな子供がという視線をあびる蘭は居心地が悪そうだ。
園子が戻ってくると、あからさまにほっとした表情を見せた。
「ごめんね、蘭。放っておいて」
「ううん。だけど、なんか場違いな感じがして」
「私もだよ。英語は勉強してるけど、専門用語が多くて何を言っているのか、よくわからないし、おじさんばっかりだし」
せめてミニコンサートとかイケメンの俳優とかいれば、少しは楽しめるけど、と愚痴をこぼす園子に真純は「映画の完成披露パーティーじゃないんだから」と苦笑する。
逆にそんな人間がゲストで呼ばれたら、もっと場違い感があるだろうに。
鈴木財閥の後継者候補と言われても、園子は『お嬢様』としか扱われない。まだ未成年で事業に直接関わっていないことが大きく、こういう場では一言二言の挨拶を交わせば、相手は両親しか見ない。
だから、誰も自分を見ていない場所にいるのが辛くて、蘭達を同伴に誘うのだが。
「オヤ?ダレのゴシソクかな?」
独特のイントネーションで話しかけてきたのは、柔らかなブラウンの髪にライトグリーンの眼をした外国人だった。
園子が自己紹介をして、新一達を友人だと紹介すると、彼の隣にいた金髪の男も納得顔で頷いた。
「スズキのゴレイジョウでしたか。スミス・ピボットといいます。どうぞおみしりおきを」
「アーデルベルト・ホフマンです」
「お二人とも日本語がお上手ですね」
20代後半だろうか、会場では若い部類にはいる青年達に、園子や蘭は親しみを覚えたようだ。もちろん、白人系の整った顔立ちというのもあるだろうが。
「私達も若いですが、お二人もここでは随分とお若いですね」
「そうですね、ワタシタチなど、ここではシタのシタですから」
「えっと、ニホンゴではシタッパ?です」
「本当に日本語がお上手です」
嬉しそうに笑って、園子が「どの料理がお口にあいました?」と尋ねると、「ハモのテンプラ」と返ってきて、蘭も笑う。
彼らは千葉の学会に出ていたが、発表する側ではなく、教授の御伴で、自分達が所属する研究室にバイエルンが出資してくれているので、教授と一緒にこのパーティーに参加したと話した。
一介の研究員の収入は多くなく、おいしいご飯が食べられるとあって喜んで参加したとスミスが冗談めかして言う。
自分がやりたい研究は、教授のものと少し違うが、スポンサーを見つけないととても自力で研究は出来ない。だけどお金だけ出して、好きに研究をさせてくれるスポンサーなどなかなか見つからないとアーデルベルトは苦笑いする。
「やはり、リエキがでないケンキュウにカイシャはオカネをださないからね」
「それは仕方がないわ。企業はボランティア活動ではないもの」
「ええ、ワカッています。だからこそ、トウシしてもよいと、キギョウのキョウミをひくケンキュウロンブンをかかなくてはいけないのだと」
それなのに、教授の雑用に追われて論文を書く時間がとれないと二人は嘆く。
蘭と園子は二人の青年との会話を楽しんでいたが、新一は入口のほうをしきりに気にして、真純もお皿の料理をつまみながら入口に視線をやる。
ザワリと会場の空気が揺らいだ。
どこか周囲を伺うような、そんなざわめきが会場に広がっていく。
園子達と話していた二人も、ざわめいた空気の方へと視線をやると、驚きに目を見開いて何事かを小さくつぶやいた。
蘭達も振り返ってみると、そこには学校の制服姿の時とは随分と雰囲気が違う志保がいた。
明るい赤みがかった茶色の髪をハーフアップにしているが、艶があり綺麗にセットされ、艶を消したゴールドにバロックパールをあしらったヘッドドレスで飾っている。
薄くメイクをしているのか、翡翠色の瞳が強調され、ローズレッドの唇が華やかだ。
照明に映えるシャンパンゴールドのドレス。布をたっぷりと使い、前裾はくるぶしが見える丈で後ろは床すれすれ。レンタルではなく、ヒールを履いた時に合わせて仕立てられたとわかる衣装だが、気おくれしている様子はなく、綺麗に着こなしている。
落ち着いた物腰はとても高校生には見えない。そんな志保を守る様に、両サイドに二人の男性がつき、近づいてくる相手を捌いているようにみえる。
その二人の男性の顔に見覚えがあった蘭と園子は、二重の意味で驚いた。
ポアロでバイトをしながら小五郎の弟子を名乗る安室透と、新一の家でしばらく暮らしていた東都大学工学部に通う学生の沖矢昴の顔だったからだ。
ただし、二人ともいつもと恰好が違う。安室が着ているのはシルバーのストライプが入った細身のグレーのイタリアンスタイルのスーツで、華やかなドレスシャツを着ている。金髪に褐色の肌と相まって、一歩間違えばホストと間違われそうな身なりだが、軽薄さがない雰囲気と隙の無い美しい立ち姿で、モデルのように見えた。
普段、蘭達の前での沖矢は穏やかな物言いと27歳という年齢で大人の落ち着きを感じさせたが、無造作に髪を流し、ジャケットを羽織っていても全体にラフな格好で気安い印象がある。
その彼が綺麗に髪を撫でつけ、かっちりとしたブリティッシュスタイルのスーツを着ていると雰囲気が一変した。黒に近い濃紺はフォーマルのようにも見えるが、ボルドーのネクタイと柄の入ったポケットチーフが良い意味で崩している。インドア派に見えていたが、肩幅と厚みがあって細いフレームの眼鏡も理知的に見せ、場馴れした雰囲気はエリート然としたエグゼクティブの様相だった。
「ウソ、あの二人凄い格好いい!」
「本当!」
京極真と付き合ってはいるが、元々イケメン好きで顔の良い男性は見る分には楽しいと思う園子がはしゃいた声をあげれば蘭も同意する。
スーツを着こなす大人の端正な色気は、見た目が良くてもまだ学生である京極など同世代のそれとは違い、どうしても人目を惹く。
アポロでもファンが多い安室だが、周囲に馴染むいつもの様子とは違って存在感があるし、普段目を細めていつも笑っている印象の沖矢は、笑みをうかべつつも青い瞳が相手を観察している。
その二人が志保にナイトのように付き従っているのだ。
着ている衣装は王道ともいえるプリンセスラインのドレス。ウエストまですっきりとしたボディにたっぷりと布を使ったスカートがふんわりと広がったシルエット。
シャンデリアの光の下、光沢のあるシャンパンゴールドの生地の質感はシルクだろうか。
園子の柔らかなシフォンや蘭のサテンの可愛らしいワンピースドレスに比べて、デザインこそシンプルだが、そのせいでずっと高級感のあるフォーマルに近いドレス。
そして、二人にエスコートされている志保もまた、年配の男性達に対して、物慣れた対応をしている風に見える。
「つくったなぁ、二人とも」
「うん、あんなにキラキラしいのは僕も初めて見るよ」
「まあ、隈のあるいつもの眼付きの悪い悪人面じゃ悪目立ちして浮くだろうし」
「工藤君、何かあの人に含むものがあるのかな?」
自分の兄に対して『悪』の字をそこまで重ねるとは、と真純がニコニコ笑って工藤を見る。
「別に、含むもんはねぇよ?」
ああしている二人の姿は護衛には見えず、志保のパートナーにしか見えないのが、ちょっとムカッとするだけで。
年を重ねた二人が醸し出す自信と存在感は、経験の浅い高校生の自分が太刀打ちできるものではないと解ってはいても、釈然としないのだ。
「流石は鈴木財閥。まさか『an empress without a crown』を引っ張り出してくるとは」
「誰だ?」
新一達が振り返ると、そこには三十代の日本人サラリーマンの姿があった。
「失礼、私はバイエルンの日本支社に在籍している樋口と言います」
「私はブリトリアの日本法人に勤める坂上です、どうぞよろしく」
二人とも仕立ての良いスーツを着ており、エリートサラリーマン風だ。
新一達が未成年とわかるせいか、自己紹介に名刺を差し出すことはなく、手にしたワイングラスを軽く掲げて挨拶をする。
改めて園子が名乗り、新一達を紹介する。
「『無冠の女帝』って宮野さんのこと?」
園子が尋ねると、二人だけでなく外国人の二人も「おや?」という顔をした。
「そう、ドクター・シホ」
「彼女の両親も優秀な研究者だったから、区別するためにドクター・宮野は父君の宮野厚司、ドクター・エレーナが母君、そしてドクター・志保と名前で呼ばれて区別されている」
「尤も、彼女の両親は優秀だったが、異端で学会を追われたから、今ドクター・宮野といえば彼女をさすがね」
「それで『無冠の女帝』ってどういう意味ですか?」
本当に知らないのかと、スミスとアーデルベルトは顔を顰めるが、日本人の二人は苦笑するだけにとどめた。
「15才で大学に入学した天才、アメリカのエルヴィン教授の秘蔵っ子という触れ込みだったが、これといった発表もなければ、学会にも出てこない。さて、名前だけの天才かと言われていたんだが」
「エルヴィン教授の研究チームから先天性の心臓疾患など内臓疾患に対する新薬の研究レポートが次々発表された。ところがだ、学会などで数字の矛盾や疑問をぶつけられると、エルヴィン教授やメインスタッフであるはずのクリスフォードは答えられず、持ち帰って検討した上で回答すると答える」
「この業界、意外と狭くて発表された最先端の研究レポートは皆が読んでいるし、情報が回るのは早い。滅多に表には出てこず、出てきたときは厳重なガードがついているから話かけるのも容易ではない、子供のような外見と、見た目を裏切る知識量。同種の研究をしている海外の研究者への問い合わせや、たまにポロッと新薬に対する疑問に答えるものだから、これは彼女が研究の中心だとすぐに知れた。エルヴィン教授達が、彼女の研究を自分の名前で発表しているなと」
「直接問い合わせた者もいたようだが、彼女が訴えなかったからな。それで悪役宰相に実権を奪われ利用される女王様、という意味で『an empress without a crown』いずれ彼女は自分の玉座を取り戻すだろうと言われていたのに、卒業したあと噂を聞かない。これはつぶされたかと思われていたら…」
「1か月前、突然『宮野志保』の名前で遺伝子疾患に対する治療法について論文が出された。最初に読んだとき、荒唐無稽だと思ったが、今は無理でもいずれ可能だという確信が文面から読めた。彼女の中では、すでに完成までのプロセスが見えていると」
「本社の連中も急いでエルヴィン教授に問い合わせたが、言葉をにごした返事しかかえってこない。直接彼女とコンタクトをとろうと、ブリトリア本社の連中が躍起になっているというのに、こんなところにいるとはね」
「ファルシア、というより鈴木財閥は彼女を今度の研究所責任者に据えるおつもりでしょうか?」
探るような視線の樋口と坂上に、園子は困ったような表情をする。
「私、家の事業については何も知らないんです。彼女は同じ高校に通っている知人で、それでこのパーティーにも誘っただけなので」
「はぁあ?」
「高校って?」
「帝丹高校です」
「そんなバカな!」
『今更、日本のハイスクールに通って何をするんだ?』
『学生ごっこか?ありえない!』
園子の答えに研究職であるスミスとアーデルベルトは母国語で叫んで信じられないと頭を振り、樋口と坂上は園子の言葉に呆然とした表情だ。
ただし、外資系企業に勤める日本人の二人は立ち直りも早かった。
「それでは、彼女はファルシアとすでに契約を交わしたわけではないと?」
「多分…工藤君は何か聞いている?」
「いや。もっとも、アメリカの大学関係者がしつこくて鬱陶しいと言ってたから、どこかに入るかもしれないけど」
新一の言葉に、樋口と坂上が得たりと頷いた。
「挨拶にいかれないのですか?」
「いえいえ、私のような下っ端が拝謁するのは。そちらはどうなのです?」
「もう少し後でないと、私も睨まれそうです」
身なりの良い、初老の男性を筆頭に志保の周りに人垣が出来ている。
良いことを教えてもらったと笑顔で二人は新一達の側を離れた。
どうやら、志保がフリーだと伝えに、上司のもとに向かったらしい。
「『an empress without a crown』ね…」
皮肉の響きが滲んだスミスの言葉に、アーデルベルトも「ガッコウセイカツをたのしみたいとはヨユウでうらやましいことだ」と苦さが滲む。
「何が言いたい?」
視線を険しくする新一に対して、スミスは肩を竦めてみせた。
「タシカにカレらは『an empress without a crown』と呼ぶ。だが、ワレワレのアイダでは『Pandora』のナでとおっているよ」
「『パンドラ』?」
「カノジョによって、ジブンのケンキュウをゼンブヒテイされて、こころがオれたケンキュウインがつけたナさ。ゼンブヒテイしたあとで、ヒトスジのキボウをのこすから、あきらめきれない。ジブンのリロンをすててしまいたいのにすてられない」
今まで自身の人生をかけて取り組んできた研究を、子供の彼女に完膚なきまでに全否定されるのだ。志保を認めることは容易ではない。
「カノジョをミカエシタイと、ジブンをミトメさせたいとねがって、あがきつづけるレンチュウがつけたナだよ」
否定するかと思えば、違うアプローチを教えたりするから、自分の理論の正しさを志保に証明しようとする。
「カノジョ、ナマエはおぼえていなくても、ロンブンはおぼえているからな」
よほど頻繁にやりとりがないかぎり相手の名前は覚えていないが、興味を持った論文の内容は覚えている。志保にあなたの論文を覚えていると言われて喜ぶのは、普段、志保のことを子供だの天才など買いかぶりが過ぎると口で言っている連中のほうだったりする。
二人が志保を見る目には羨望と嫉妬と、どこか諦めの混じった複雑な感情が宿っていた。
彼等から聞かされる予想外の話に、園子と蘭は戸惑うが、新一は悔し気な顔をして、志保の方に向かうから、あわてて園子達も後を追った。
今晩、志保が着ているのは、フサエ・キャンベルが志保のためにデザインしたドレスだ。
コンセプトは『デビュタント』正式に社交界にデビューし、一人前のレディとして認められる最初の舞踏会に着るドレス。
通常は白のゆったりと膨らんだイブニングドレスだが、フサエはあくまでもイメージとして捉えてこのドレスを作った。
蚕の繭から厳選した最高品質のグレード6Aの絹糸で織られたシルク生地は、光沢のあるシャンパンゴールドの輝きと艶。襟や袖には機械織では再現できない、繊細なアンティークレースを使用した。
本物のレディであれば、男性は身をかがめてその手を取る。
本気で請うなら、膝を折って請う。男達に跪かせる価値のあるレディになりなさい。
少女から大人のレディへと花開く、その瞬間を輝かせ、大人の世界への不安と緊張を抱えながら、堂々と一歩を踏み出すその手助けとなる、美しいドレス。
形はシンプルでいながら、丁寧に時間と手間をかけ、志保を美しくみせるためにシルエットに拘って作られた、フサエブランドの中でも店頭に並ばないオートクチュールに類する高額ライン。
最初は借りるつもりだったので、誂えると聞かされて辞退したのだが、これは志保以外に着られないと押し切られた。
ちなみに安室と沖矢がエスコートすると聞いて、これもフサエが志保との釣り合いを考えながら見立てたスーツだ。
もともと、この二人の場合、拳銃をホルダーで吊るしても目立たないデザインのスーツを着るので、基本オーダーメイド。役に合わせて吊るしの2着3万円程度のスーツを着ることもあるが、体形的に既製服だと合わないことが多く、『合わない服を着る』というシチュエーションが必要な時以外は着ない。
降谷と赤井の名前と姿で、身バレすると困るというのが大きいが、悪意がなく、純粋に志保を飾ることに熱心なフサエとそのスッタフに逆らえず、この際メイク道具のレクチャーと降谷は割り切り、赤井は諦めた。
二人のスーツ姿にフサエとスタッフも興奮し、外には出さないイメージフォトとして志保と志保をエスコートする二人を思う存分写真に撮った。
念のため、安室と沖矢の顔は出さず、背中や手だけという徹底ぶりだったが、フサエ達は大満足だった。
会場入りする前に、いい加減ケリを付けた方が良いと、沖矢がアメリカ資本の外資系ホテルに呼び出した。高層階にあるスイートルームに通され、ソファのおかれたリビングスペースに支度を終えた志保が座り、沖矢の顔を作った赤井と人当たりの良い安室ではなく剣呑な気配を色濃くした降谷が出迎えた。
クリスフォードに対処したのは赤井というより、沖矢の方だ。目つきが悪く威圧感のある風貌は、護衛としてなら有効だがあの手の男には権威の方が効果がある。
志保と親しく、インテリ然とした身内として対応した方が良いと、身内がFBIだと赤井の肩書を利用し、しどろもどろに言い訳と弁解をするクリスフォードに対して、どこまでも冷静に今後は志保の側には近づくなと書面にサインをさせた上で念を押した。
これ以上付きまとうなら、志保の在学中に書いた論文の件、公の場で争うと言われて、クリスフォードは逃げるように部屋から出て行った。
志保は赤井に任せて無言で通し、安室が淹れてくれたコーヒーを飲んでいたのだが、クリスフォードが出ていくと、大きく息を吐き出した。
やはり、はったりは見た目が大事だ。
どうにも志保は危機管理が低すぎる、やはりアメリカで保護証人プログラムをうけたほうが、と赤井は勧めたのだが、降谷は鼻で笑った。
志保が薬学を目指す限り、名前を変えても意味はないと。
外見というより年齢が大きく違うコナンや哀の時とは違う。宮野志保が消えても、同じ年頃の女性が出てくれば、どうしたって疑われる。志保が黒の組織で『シェリー』のコードネームと研究室を与えられていたのは、両親が黒の組織に属する科学者だったから、という理由だけではない。
彼女自身が実績を積み、自分の才能を証明してみせたからだ。特に休癌剤とも呼べる新薬は、がん細胞を死滅させるのではなく、活動を止める効果がある。進行がすすみ、複数の転移でもはや切除手術ができない患者の延命に利用される。
通常の抗癌剤は正常な細胞も破壊し、副作用もきついものが多いが、志保の作った薬は治すのではなく、一定の条件で癌細胞の進行を止める効能を高めたもので、痛みや嘔吐も少ない。
遺伝子細胞治療に関する研究の第一人者、だからこそ、黒の組織は志保に研究室と資金を与えた。志保が別人として暮らすなら、薬学は出来ない。研究を発表すれば、名前を変え、顔を変えてもすぐに正体はばれる。
「それに、子供が簡単に銃で撃つことができるアメリカで、どうやって志保さんの身柄を守るんです?FBIが24時間警護を請け負うと?」
以前に比べて治安が悪くなったとはいえ、日本のほうが安全だと降谷が言えば、相手が撃つまで攻撃できない、いちいち発砲許可を求める日本警察に守れるとは思えないが?と赤井が言い返す。
「第一、学閥の老人達でかたまった日本の大学で、志保がやりたい研究を自由にできるはずがない。クリスフォード達のように研究の成果だけを取られるか、妬まれて嫌がらせを受けるのが目に見えている」
才能のある者に援助する、という文化はアメリカやヨーロッパに比べて日本に根付いていない。それどころか、権威主義者には女性を下にみる輩が多いと赤井は指摘する。
これからは志保の好きに生きれば良いと、言うのは簡単だが、志保が薬学に進み研究に身を捧げることを望むなら、彼女に潤沢な資金と設備を与え、周囲から守るだけの力がある者が必要になる。
だが、それは研究室に閉じ込めた黒の組織の行いとさほど変わらない。
世間から隠し、隔離しなくては危険なのが、志保の才能だった。
普通であれば、1000を試して1の売れる新薬ができれば儲けもの、と言われる新薬開発。
それを可能にするのが、志保の才能だ。
APTX4869を元にして、志保が発表した新しい論文は業界を震撼させた。これをきっかけに遺伝子疾患にたいする新しい治療の道が開くかもしれないからだ
普通に一般人として暮らすなら、名前を変え、違う道を選ぶ方がより安全だ。
それでも、贖罪という言葉の重しをつけておかないと、志保はすぐに自分のことを粗末に扱う。
APTX4869を作った罪悪感を引きずり、人を助ける薬の開発を望むなら応援してやりたいと思っているのだが、なかなか難しい。
赤井のほうは、上司を通して本国アメリカの企業からも志保の進退に対する問い合わせがはいっている。
日本にあったメインホストは破壊され、志保のもつ知識とデータを欲しがる日本の上層部に対して、降谷は警戒を強めている。
だから、時間があれば、どちらかがエスコートしてくれないか?という志保の滅多にない申し出に二人が揃って手を取ったのだ。
志保を物理的に守る盾にはなれても、彼女の立場を守る権威は足りない。
彼女が自分の価値を理解するまで、彼女の庇護する者が必要だという認識だけは一致している。
ただ、その基準が男達の間で差があるだけで。
「両手に花ならぬ、両側にハンサムなナイスガイで気分がいいわ」
珍しく傍で分かるご機嫌な様子で、志保が安室と沖矢のそれぞれの腕に両手を回して見せる。
全体の割合から言えば少ないが、女性客もおり、彼女達の視線が志保ではなく、ダブルエスコートをしている二人に向き、そのあと志保を嫉妬と羨望の視線で見る。
新一などは気づかないが、この二人はちゃんと周囲の視線に気が付くので、ことさらナイトを演じて志保をお姫様のように扱う。
志保にすれば、降谷と赤井の貌を知っているから、余計に今夜だけの一幕芝居と割り切って楽しむことができた。
『久しぶりだね、シホ。近頃、名を聞かなくなっていたから心配していたが、元気そうだ』
『サー・ウォーリック、ご無沙汰しています。遅くなりましたが、ナイトの叙勲おめでとうございます』
頭髪は白髪の混じったグレー、口ひげを綺麗に整えた紳士然とした初老の男が志保に声をかけると、志保は嬉しそうに挨拶を返す。
リチャード・ウォーリック、イギリスで免疫学の権威であり、後進を育てることに熱心な人物だ。
『まあ、くれるというからもらったがね。シホがイギリスにいれば、君こそデイムの称号を得ただろうに』
『サー・ウォーリックの言葉なら、お世辞とわかっていても嬉しいです』
『世辞ではないのだがね』
年から言えば、祖父と孫ぐらいの開きがあるが、イギリスの学者はにこやかな笑顔で志保との再会を喜び、警護のように付き従う男二人にチラリと視線を流した。
『君の論文を読んだよ。……シホ、神の摂理に逆らい、その領域を侵すつもりかい?』
遺伝子治療は遺伝子の解明に繋がり、優秀な遺伝子を望む者によって歪になる可能性をつねにはらむ。日本ではそれほど感じることはないが、キリスト教世界では聖書の教えに反すると進化論を否定する人間はまだいるのだ。
命の設計図ともいえる遺伝子を、人の手で書き換える。そのことに反発と不快感をもつ者は少なくない。
科学に身をおく者の中には、敬虔に神を信じる人間が意外と多いのだ。
『私のモットーは、《命は金銭で買えないけれど、治療は買える》です。医療とは、神の与える試練に立ち向かって発展してきたのではないのですか?患部を切り、血管を縫合することは、ただ腐り落ちていくのを止めるため。衰弱して死を迎える時期を遅らせるために、薬を飲む。《死》は神の摂理、ですが治療は神の試練に諦めず立ち向かう意志です』
『宮野志保』として生きることを選んだ時から、迷わないと誓った。
異端だと学会を敵に回した両親の研究、それを引き継いだ時から覚悟を決めていたのだ。
『…女帝は自らその宝冠を手にしたか……』
以前はどこか張り詰めた雰囲気をまとい、彼女を他者と接触させないように見張っているような護衛達もどこか不穏な空気を醸し出し、近づきにくかった。
それが、なんと誇りと自信をたたえた顔をしていることか。
『シホ、イギリスの医療特区にできた研究所に来ないかね。私もできるだけのバックアップをはかろう』
EU離脱を宣言して、イギリスから多国籍企業が出て行き始めている。すでに、大量生産大量消費の時代ではなく、原価と人件費を考えればアジアやアフリカの新興国にはとうてい太刀打ちできない。過去、イギリスの植民地だった地域は、今では目覚ましい発展をとげ、イギリスは新しい産業形態の構築を模索している。
雇用と収入を守るために、最先端医療の研究に特化し、関連の企業を集約した医療特区を作った。その施設に志保を誘う。
『抜け駆けはずるいですよ、サー・ウォーリック』
ゲルマン系の特徴である背が高く、筋肉質の体形に切れ長の大きな瞳をした壮年の男がウォーリックを遮るように話しかける。
『お久しぶりです、ドクター・シホ』
『ご無沙汰しています、ヘル・イェンクナー』
バルヒェット・イェンクナー、バイエルンのアジア地域を統括している最高執行責任者の一人。
『是非、我が社に。貴女が望む最新の機材と研究施設をご用意いたしますよ』
表向き、黒の組織の解体は終わったが、彼等と接触のあった人物、企業、組織を逮捕または解体するには時間がかかるし、社会への影響も馬鹿にならない。
ホワイトフェザー社は救済されたが、潰れた会社もある。
世界規模で活動している多国籍企業ほど、末端が知らず浸食されていたりして、膿を取り除くために社内調査と立て直しに奔走している。
志保が黒の組織に属していたシェリーとは知られていなくても、今まで表舞台に出ようとしなかった天才が、莫大な利益をあげそうな新薬を手に現れたのだから、彼らが獲得に動くのは当然だった。
すでに鈴木系列と契約をしているなら、それ以上の条件でと意気込む彼等に、志保は苦笑を浮かべる。
黒づくめだった護衛達の醸し出す独特の空気に比べて、安室や降谷の護衛はさりげないうえ、緊張して人目を避けるようだった志保が、ずっと表情豊かに華やかな装いで表に出てきたのだ。
これは好機とばかりに人が集まってくるのも当然だった。
「宮野」
名を呼ばれて「工藤君」と志保が振り返る。
周囲はこの子供は誰だという目で新一を見るが、志保が友人で恩人だと紹介すれば、一応納得したようだ。
「モテキ到来だな」
「茶化さないで」
本気で困ってるんだからと、志保が新一を睨む。
日本を出るならパスポートや就業のビザのこともあるから、早めに準備をした方がいいのだろうが、もうしばらくは学生を楽しみたいと志保が言えば、そうだよなぁ、焦って決めることもないよな、と新一が頷く。
いつの間にか料理を取りにいっていた沖矢が志保に料理を取り分けた皿を差し出し、安室はカットされたフルーツでノンアルコールカクテルの『シンデレラ』を作って差し出す。
グリムの『灰かぶり』は、魔法使いを待つのではなく、自分の足でお城に向かった女の子だ。彼女のドレスは12時になっても消えることはなく、自分自身の力で未来を選び取る。
だから、このカクテルは志保に合っていると、オレンジ・レモン・パイナップルの果汁を合わせたロンググラスを差し出した。
「私、甲斐性なしで思慮に欠ける王子に人生預けるほど人生捨てて無いのだけど」
舞踏会で素性も知らない相手に一目ぼれして結婚と言い出す頭も心配になるが、靴に足が入ったからと灰かぶりの姉を連れて帰ろうとし、靴に足をいれるために指と踵を削ったと血に染まった靴下を指摘されるまで気がつかないのはどうなんだと。
逆に、片や足の指を切り落とし、片や踵を削って靴に足をねじ込む、玉の輿に懸ける姉達の執念を凄いと思ったが。
二人が差し出す料理ののった皿とグラスをうけとったが、二人とも、自分の分と志保の分だけで、相手のことは態と無視して白々しい笑みを浮かべてみせるので、志保はあからさまな溜息をついた。
新一の後を追いかけてきた蘭と園子は少し距離を取り、真純は志保と沖矢に話しかけているが英語だ。
園子は鈴木財閥の令嬢として見られることが嫌だった。両親と財閥の名前で周囲が園子の顔色を窺い、ちやほやするのに苛立った。
だからこそ、普通に接してくれる蘭や新一を特別に思ってきたのだが、志保と彼女に接する周囲の大人達を目の当たりにしてショックを受けた。
側で見れば、繊細で豪奢なアンティークレースと、ドレス生地の艶に溜息が出そうになる。レンタルなどではない、一点ものとして作られたドレス。
自分達の年ならこれぐらいが相応と選んだドレスも決して安い作りではないけれど、かけた手間が違い、値段の桁も違うと一目でわかる。
それなのに、宮野さんは自然と着こなしている。テレビで見かけるような著名人ではないけれど、鈴木財閥が配慮をする程度に影響力を持つ人達が、宮野さんに身をかがめて挨拶をし、会話をしたがる。
自分と年は変わらないのに、他人が傅く様を受け入れ、慣れている様子に園子は戦慄さえ覚えた。
園子は肩書ではなく自分のことを見てほしいと、嫌だ嫌だと言いながら、鈴木財閥の娘である特権は当たり前のように行使してきた。
自分では普通の高校生だと思っていたが、金銭感覚や対人に対する態度は、やはり【お嬢様】が滲む。新一は両親がともに有名人であり、一般家庭とはやはり環境が違い、蘭は幼少期から新一と園子と一緒だったので、これが普通と思っていた。
だから、クラスメイト達はたまにならともかく、あまり園子や蘭と一緒に遊びに行かないのだが、園子と蘭は互いがいると思ってしまい気づかない。
「宮野さんのドレス、すごく綺麗ね」
「ええ、お金も手間もかかっているわね」
どこか羨ましそうな蘭の様子に、園子は溜息をつく。あれは志保に合わせて仕立てられたドレスだ。仮に借りたとしても、蘭には合わないし、着こなせない。
実際、このドレスは重い。裾にたっぷりと布を使っているのもあって、20kgほどあるのに、足が一番綺麗に見えるからと履かされたのは7センチヒール。
せっかくフサエが贈ってくれたのだからと、姿勢を崩す訳にもいかず、志保は笑顔を浮かべながら腹筋と背筋、根性で上体を支えて立っている。
ただ、ドレスに対して、首元を飾るチョーカーがバランスを崩していた。
銀杏をモチーフにしたデザインのチョーカーは、フサエブランドではあっても比較的リーズナブルな価格帯の商品だ。
拘りぬいたオートクチュールのドレスとは、釣り合いが悪い。
真純が言葉を選びながらそれを指摘すると、志保は笑った。
「フサエさんは貸そうと言ってくれたのだけど、私の年でハイジュエリーは分不相応だし、欲しければ自分で買うわ。これは【お守り】なのよ」
この場合のハイジュエリーは数百万円単位の品をさすが、若い肌に大きな石は似合わない。だから上質のメレダイヤをあしらったネックレスをフサエは用意していたのだが、志保がこれで良いと言ったのだ。ヴェルベットに金色の銀杏のトップをあしらったチョーカーで、フサエのスタッフは難色を示したのだが、お守りだからと譲らなかった。
胸元の銀杏を指で揺らして笑う志保に、新一が顔を赤くして手で隠すように覆った。
新一はコナンの時、志保に今まで協力してくれたお礼にと、チャームや財布などをプレゼントしてきた。安くはないが、まったく手が出ないような値段でもない。そのあたりを要求する志保にちゃっかりしていると思ったこともあったが、小学生の哀が持っていて不自然ではないのはそのあたりの小物だった。口では前のお礼をもらっていないと言いながら、新一の頼みを断ることはない。志保も本気で小学生のコナンに買えるとは思っておらず、言葉遊びのような、お約束のようなものだった。
そんな新一が迷いに迷って贈ったのが、このチョーカーだった。ディスプレイに並べられている新作バッグは無理、これが限界ですと差出した。
一応、金メッキではなく、18Kで普段使いできるとお店の人にも勧められたのだ。
小学生の子供が働いている姉に贈るプレゼントを探していると思われていたようで、ブランドとしてはかなり安めの、小学生には高めな数万円クラスのアクセサリーを出してくれた。
中身を見た時、哀は目を見開いて驚いた表情で。顔をそらしてもその耳が赤くなっていたから、照れているんだと解って、コナンも笑った。
その後、見かけることがなかったので、どこかに仕舞い込んだのかと思っていたのに、ここで身に着けるとか、それも「お守り」だと言われてはどんな顔をすればいいのか解らない。
新一の態度と、どこか面白がるような嬉しそうな志保に、新一のプレゼントだとわかった蘭は複雑な顔をした。そして、そんな二人を微笑ましいという風の周囲の人達の様子に、気持ちがざわつく。
自分だって新一からプレゼントをもらったことぐらいある。そう思うけれど、蘭が身に着けて新一に見せたとき、彼はあんな顔をしなかった。
『あのチョーカーは宮野さんに似合っていないじゃない。新一ってばもっと考えて贈れば良いのに』
とっさに蘭はそんなことを思った。
「お代わりをもってきましょうか?」
そう声をかけた沖矢に、「僕のもお願いしていい?」と真純が声をかければ、「いいですよ」と笑った。
新一が側にいるからと、沖矢が料理を取りにビュッフェのテーブルに向かおうとした時、ある意味、志保達が聞きなれた男の悲鳴が聞こえた。
その悲鳴を聞いた安室と新一は走り出し、沖矢と真純は志保の横にさり気なく位置を変えたが、蘭と園子は慌てて新一を追いかけていった。
志保はやっぱりこうなったか、と大きな溜息を付き、沖矢に向かって「今のうちに沖矢さんと世良さんも食事をしておいた方がいいわよ」と、お代わりとデザートを取ってきてと告げた。