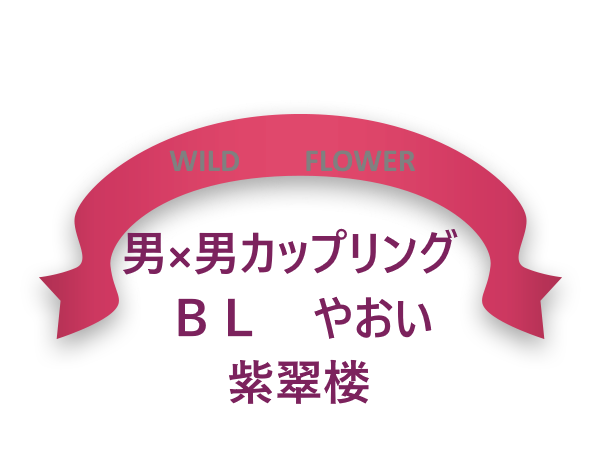触れぬ指先 恋の淵2名探偵コナン
新一×志保
黒の組織との対決は、警視庁主導ではなく、全国の都道府県警察の公安部からピックアップされた捜査員を警察庁の警備企画課が指揮した。
これはCIAとFBI、ICPOを通じて世界規模での一斉検挙と殲滅を目的としており、日本国内の拠点は特に重要施設だったので、国際テロに準じた扱いで警視庁だけでは捌ききれなかったのと、公安が情報の漏えいを嫌ったせいだ。
もちろん、警視庁幹部からの反発はあったが、ここまで来るのに犠牲をはらってきた公安は一歩も譲らなかったため、現場警察官は詳しい情報は知らされず、大規模一斉検挙とは知らず、公安の指示するタイミングで個々に捕縛に向かう形になった。
これは犯人逮捕ではなく、組織壊滅に賭ける思いと危険に対する警戒の強さが、末端の警察官と公安では違い、その違いが大きいというのが今回指揮を執った降谷の判断だった。
たとえ政治家だろうが邪魔はさせないとばかりに、捜査令状は各地別々に申請し、法務省と外務省の大臣にすら事後報告で、警察内部だけでなく霞が関にすらかなり情報を制限して一斉検挙に踏み切った。
各地での銃撃戦にくわえ、爆発事故などもおこり、マスコミを完全に抑えきれず国際テロ組織を宗教や国家を超えた各国連携で捕縛殲滅を行ったと、政府筋を通して発表になった。
もちろん、公安部だけでは人手が足りず、警視庁から目暮警部なども駆り出されたが、民間人の避難誘導と包囲した建物から出てきた人物の逮捕捕縛が任務で、建物内に踏み込むのは別の部署だった。
逮捕よりも殲滅を優先したため、通常の警察官では対応できないと判断されたからだが、秘密主義な公安に対しての不満は出た。
ただし、実際の組織突入で日本国内だけで2桁に近い死者と、3桁を超えない怪我人が出たことと、鬼気迫る公安メンバーの顔つきに、面と向かって非難できる者はいなかった。
実際、押収された資料の分析なども、関係者以外には徹底して秘匿され、一捜査員には全容もはっきりとわからない。
それでも、相手は銃だけでなく、爆弾や毒ガスに匹敵する武器を所有していたことは開示されたため、銃撃戦が警察の行き過ぎた捜査だという論調は抑えられた。
新一と志保は、公安ではなくFBIのオブザーバーとして参加し、公安で日本担当の指揮をとった降谷とその直属以外には会わない様にしていた。
目暮警部はなまじ面識があるため、コナンの正体を知られると今後の関係が難しくなるという心配と、緘口令を指示されても蘭や小五郎に確認される可能性が捨てきれなかったからだ。
外見が子供の宮野志保は、灰原哀として本部突入に同行した。
これは両親と自分が生んだAPTX4869の研究データを回収処分するため、それが無理なら破壊するためだった。黒の組織ではなくとも、権力者の抱く欲望の行き着く先は不老不死。若返る薬などどんな騒乱をおこすか考えるまでもない。
戦闘要員ではなく、あくまでもデータ分析要員だと、渋る新一を説得し、赤井の言うことは必ず聞くことを条件に参戦だった。
新一は日本の本部突入部隊の指揮を担当し、降谷は日本各地の一斉検挙の統括と、同じタイミングで突入をする他国とのパイプ役だった。
突入する部隊は無線として使える博士の作ったバッジの改良版が配布され、警察無線とは違う回線を利用する徹底ぶりだったが、日本語だけではなく英語混じりの数十の各担当からあがってくる情報を瞬時に判断して指示を飛ばす降谷と、それに互するような新一の適格な状況判断と指示に見た目から不安視していた者達も態度が変わった。
降谷達公安や赤井達FBI、一人の民間人より国家を優先する内閣情報調査室とCIA、違う国、違う価値観を持つ組織同士が手を結んだのは、それだけ黒の組織が脅威であり、面子に拘っている場合ではなくなったからだ。
監視するだけで良いただの暴力組織ならともかく、恐怖と資金で国のトップを操作して世界を動かす、その脅威を降谷や赤井が繰り返し説明し、ようやく浸透したからこその合同捜査であり、一斉検挙だった。
大を生かすために小を殺す、降谷達が当然とする価値観を新一は飲みこめなかった。切り捨てて良い命などないと、そう訴える新一に、命に優劣は無いというなら、一人を助けるために十人を危険にさらすことに正統性はあるのかと、等しい重みだからこそ被害の総数が少ない方法を選ぶと降谷は冷徹な表情で言い切った。
誰でも顔も知らない他人より、身内が大事だ。だが、その他人にも死にたくない理由や心配する者がいるというなら、指揮官は命に優劣をつけるのではなく、助かる総数で判断すべきだと。
「身を挺して他人を助ける、美談ではあるかもしれないが、数字で見れば変わらない。他人が死んでも自分が死んでも、死者は一人だ。他人を救うためなら、自分が死んでも良いというのはただの自己満足だろう」
100人死ぬかもしれないところを10人に減らすために、誰かを生かすために誰かに無理と犠牲を強いる。その覚悟がないなら、こちら側には来るな、と釘を刺された。
「奴らの罪を明らかにして、罪を償わせたいとは思うけど、彼らを捕縛するために捜査員に死ねという気はないよ。犯罪者の命より、捜査員の命の方が大事だからね」
自分だって人間だから、命に優劣はつけると降谷が口の端を上げて笑う。
新一も覚悟を決めた。
志保が自分の不始末の片をつけると覚悟を決めたように、自分もまた己の未熟さで失った命に対する償いと、己の技量も弁えず好奇心から首を突っ込んだことに対するけじめとして。そして、組織を壊滅させなければ、一生彼らの陰に怯えて暮らすことになってしまうと。
だから、自分の手でケリをつけたいと申し出た。
薬を使用されたのか、それとも自暴自棄になったのか、死兵と化した黒の組織側は投降の呼びかけには答えず、一人でも多く道連れにすることを選んだような反撃に出て、新一や降谷の予想を超えた行動に公安やFBIに死傷者が出た。
それでも一般人に被害がなかったのが不幸中の幸いと言う降谷に、そうじゃないだろうと悔し気に新一は言葉を振り絞り、後悔をその両手で握りつぶす。
マップ上に点滅する捜査員を示す青と、マイクから拾う各階層の状況、それで敵側の動きを予測判断して指示を出し続け、命を預かるそのプレッシャーに耐えたのだから、恥じることはないと降谷だけでなく、赤井も言ったが、ボロボロになって戻った哀の存在を見て、コナンの姿で新一は縋るように抱きしめ、哀も「大丈夫」と繰り返しながら、その小さく震える背中を優しく宥めるように何度も叩いた。
二人には肉体的にも精神的にも休息が必要だと、コナンと哀は家族の都合での転校が告げられ、優作が用意したセーフティハウスへと移動し、2か月ばかり静かに過ごした。
その間、優作は新一達が静かに過ごせるように、後始末に奔走していた。
黒の組織にかかわっていたと、明らかにすれば問題になるいわゆるVIP達の捕縛が難しかった。罪を明らかにすることで、彼らの所属する企業や政党がダメージを受ける。多少ならば自浄作用を促すだろうが、倒産や政治的不安定は一般市民が被る被害が大きすぎると判断されたが、現政権や利得権益を守るために隠ぺいされるのでは納得がいかないのが現場で血を流した捜査員達で、表だって公表される情報以上に後始末の方が大変な騒ぎになっていた。
新一と志保、コナンと哀の存在は公表しない。実際、死者がでるような捕縛に未成年がかかわったというだけでも問題なのに、見た目小学生が主要メンバーだったなどと言えば、どんなフィクションだと笑われるのがおちだし、彼らのもつ情報を得ようと、権力者たちの争いに巻き込まれるのも避けたかった。
特に黒の組織でコードネームを持つシェリーであった宮野志保の知識は、公安だけでなくアメリカ側も諦めきれていない気配があり、かなり優作がその人脈をフルに使って介入した。
ゆっくりと心身を癒しながら、志保は解毒薬の開発に没頭した。
資料がなく記憶だよりで阿笠邸で隠れるように研究していた時とは違い、志保とその後を引き継いだ研究のデータが手元にある状況は解毒薬の開発も格段に違った。
それに、薬に関する情報を抜いた後、メインのコンピュータはジンたちが仕掛けた自爆の起動のせいでハードの欠片も修復できない程木っ端みじんになった。
幸か不幸か、このメインデータを保管しているサーバーはネットに繋がっておらず、建物内だけで運用されていた独立型だったので、流出の心配は格段に減ったのがありがたい。
政府関係機関や企業の研究所は後が怖くて使えない志保のために、優作は個人向けパソコンでも並列処理することでスパコン並みの処理速度をたたき出すシステムを構築して志保に与えた。
なまじ優作本人が有名人で、その行動は他人の視線を集めるため、今まで表だっては動けなかったが、情報は集めて準備だけはしていたことが伺え、新一も素直に礼が言えた。
解毒薬が完成し、二人元の姿に戻ったが、急激な身体の成長は負担が大きく、しばらくは経過観察のための入院だった。
どこが特に、という訳ではないが、全体的な内臓機能の低下と骨密度が危険域で、通常の生活はともかく、激しい運動は禁止された。
APTX4869と解毒薬の服用で、これ以上の薬の使用はどんな副作用を招くのか、過去に症例がないため予想がつかず、極力自然治癒を選択した病院の医師達を能力不足と責めることは出来ないだろう。
新一は復学に向けて、志保は『宮野志保』としての生活基盤を整えたのだが、これだけはと新一が譲らず、阿笠の勧めもあって新一と同学年で帝丹高校に編入することになった。
志保としては、普通に目立たず高校生活を送るつもりだったのだが、新一にすれば今までどおり志保に『相棒』のポジションを望んでいた。
確かに、コナンだったとき、小学生だということの不利はあった。
それでも、自分の思考を説明しなくても理解してくれる、全面的にサポートを任せることができる人間が側にいる生活に慣れてしまって、今更志保がいない生活を想像できなかった。
思考を言葉にするときは説明ではなく、自分の思考を整理させながらの答え合わせで互いの確認でしかない。
雑談にしても、捜査方法にしても、志保の理論の組み立てが新一には理解しやすくて楽だった。
守ってやると言いながら、事件が起こればどんな無茶ぶりをしても応えてくれる、それにすっかり慣れて甘えている自覚はあるが、志保が目の届かない場所に行くのは我慢できなくて、一緒に普通の高校生活をしようと言い張った。
黒の組織に関する情報と引き換えにアメリカで保護証人プログラム適用になれば、高校生の新一では追いかけることが出来ないと解っていたから、お前は『宮野志保』だろう、逃げるなと。
今回の事件も、普通であれば高校生を呼び出すなど捜査一課の刑事としては忸怩たるものがある。
それでも、部屋の住人以外が死んでいる状況で、部屋の中はまるで信仰宗教のような祭壇と、意味深なメッセージ。膨大なノートに書かれた化学式に使用された形跡のある実験器具が押し入れで見つかって、これはまずいと警鐘が鳴った。
とにかく、犯人と思しきこの部屋の住人の確保を急がなくてはと思ったからこそ、せめてメッセージの意味だけでもと復帰したと聞いた新一に連絡をとったのだ。
以前と変わらぬ風貌だが、雰囲気が変わった印象のある新一が姿を見せると、初めてみる女性を同伴していた。
部外者は、と止めようとした高木刑事に、新一が「彼女はオレの助手で化学と薬学に詳しいから、今回は入れてほしい」と説明する。
そして志保は慣れた仕草で手袋をすると、一番新しいノートを繰って化学式を確認し、持参した鞄からいくつかの試薬を持ち出し、目暮警部に断ってから机や床の反応を確かめ、外傷のない遺体から血液を採取するとこちらも試薬で反応を確かめる。
「申し訳ないけど、検死官じゃないから、正確な死亡推定時刻はわからないわ。ただ、この遺体が吸い込んだのが何か、おおよその検討はついたので意見を言っても良いかしら」
『速い』それが目暮達の感想だった。
きちんと専門機関での分析を、と言いながら、判断の根拠をきちんと示す。
年が若くても、確かに専門知識と分析能力を持つ相手なのだと理解した。
コナンとなっていたことで、新一も認識が大きく変わった。
捜査権は警察にしかない。現行犯でなければ、一般人では逮捕できない。
実績をつみ、試験に受かり、推薦をうけた優秀な現場エリートの集団が警視庁の精鋭であり、無能であるはずがない。新一は彼らのやり方をまどろっこしいと、迂遠だと思っていたが、一つ一つ可能性を潰していくのは冤罪を防ぐためだと今ではわかる。
状況証拠だけで逮捕すれば裁判で争うには弱い。だからこそ、思い込みではないと消去法でつぶしていくのだと。
推理ショーで犯人を当てる、それだけでは逮捕起訴できないのだと、あの頃はわかっていなかった。
そして、警察の限界。被害者がいなくては加害者の犯罪を立証できず、被害がおこってからでないと動けない。第二の犯罪を未然に防ぐために動けるのは、第一の犯罪が起こってから、疑わしいだけで捜査はできない。
シャーロックホームズに憧れ、誰も解けない謎を解く探偵になりたかった。今は、被害者を出さないために、事件になる前でも動けるから、探偵の仕事に意味があると思える。
どうしようもない、人間の屑のような加害者がいる一方で、誰かに気づいて止めて欲しかったと吐露した加害者もいたことを覚えている。
「目暮警部、犯行予告という前提で解釈してみました。候補は三つ、至急捜査員を派遣してもらえますか?」
探偵は誰かを裁くためにいるのではなく、助けを求める依頼人を守るためにいるのだと、ようやくそう思えるようになった。
翌朝、クラスに現れた新一にクラスメイトは注目する。
「あれ?宮野さんは一緒じゃないの?」
昨日、あれほど当然とばかりに連れ立って出て行ったのにと問えば「宮野は遅れてくる」との返事。
「えっ?何かあったの?」
「ちょっと検察に寄ってからくるから」
硫化水素系の薬品による無差別殺人はどうにか未遂で犯人を逮捕できたが、容疑者が黙秘をしていた。志保は容疑者につく弁護士に対して反論するために、心神喪失では生成などできないと、明確な意思をもって材料を揃えて生成したのだと現場に残された購入履歴から薬剤等材料を特定し再現実験を行った上でレポートを担当検事に提出した。
そして、「随分効率の悪いやり方をするのね?まあ、素人なら仕方がないわ」と最高学府の理学部を卒業した容疑者を煽った上、不備を指摘しまくってプライドを抉れば「馬鹿にするな!素人はそっちだろう!」と激高した容疑者は自身の生成手順を滔々と説明しだした。説明を終えてどこか自慢げな容疑者に対して「私を素人呼ばわりするなら、これを使えばどうなるか、わからなかったとは言わせないわ」と普段よりも低いトーンで告げると、バンッと机の上に数枚の写真を乗せた。
緑がかった黒っぽい皮膚に断末魔を物語る苦悶の表情の死体が写っている。
「どのあたりが『楽』に死ねるのかしら?」
目を見開き、無言の相手に志保は射貫くような視線を向ける。
「心神喪失、なんて言葉で逃がさないわ。あなたはこうなると知っていて、『化学』を使ったのだから」
取調室の中にいた刑事だけでなく、マジックミラー越しに中の様子を伺っていた捜査員達は志保の態度と言動に目を見張った。
ただの綺麗な学生ではない、少しばかり知識のある素人ではない、今まで遊びで捜査を引っ掻き回すなと新一の介入に否定的だった者ですら、新一が連れてきた彼女が警察に対して犯人を起訴するためにここまで協力しているのだと理解した。
そして、無知だと刑事を馬鹿にし、志保の外見から見くびっていた容疑者は、取調室での録画を許可していたことを思い出して、蒼白になった。
コナンの時とは違う、どこか距離を感じる目暮警部達に寂しさを覚えはしたが、以前の自分のふるまいを考えれば、仕方がないとも思った。
学んだ知識を独善的な理由で人殺しに使おうとした犯人に対して、志保は激怒し、絶対に罪を自覚させると生成手順のレポートを書き上げ、突発的な思い付きで準備は出来ないと添えて検察に提出し、警視庁に向かったのを見送ってから学校に登校した新一だ。
以前のようなマスコミの前で推理ショーを披露する気もなければ、志保がメディアの前に顔を出す気がないのもわかっている。
だから、昨日の事件のこともクラスメイト達にはっきりとは言えない。
それでも、晩のニュースですでに殺人犯逮捕と無差別殺人未遂事件は流れていたし、多分これからメディアでの取材と報道が過熱するだろう。
授業内容はあまり頭に入って来ず、午後には志保も登校してくるだろうかとぼんやりと考えていた。
昼休み、やはり手の込んだ料理がつまったランチジャーを広げ、おいしそうに食べる新一に、クラスメイトは何とも言えない顔をした。
以前は蘭との関係を『夫婦』とはやして揶揄ったクラスメイト達だから、蘭からの弁当ではないのに『愛妻弁当』などと茶化す訳にもいかず、それでも手のかかったと解るおかずと品数は義務感で作っているようにも見えず、そして新一本人は何の疑問も持たずに食しているので余計に判断に困った。
「ちょっと、工藤君!」
教室の入口で仁王立ちして新一を睨む園子に、弁当を食べ終わった新一が視線を向ける。
「なんだよ、園子」
「あの宮野志保って女子とはどういう関係なの?」
蘭という者がありながら、そんな言葉が聞こえてくる口調だが、周囲も気になっていたことなので新一の返答に注目し、教室のざわめきが止まった。
「宮野はオレの相棒で、運命共同体だけど」
迷いのない新一の言葉に、園子は「何よ、それ!今まで蘭のこと放っておいたくせに、自分は綺麗な子にフラフラしてたってこと?」と怒る。
「どうしてそうなるんだよ?」
呆れたような口調で新一が座りなおした。
「蘭は大事な幼馴染で、あいつを待たせてるから、絶対に戻ろうと思った、オレにとっての『日常』だよ。だからこそ、あいつは『非日常』には向かないし、関わらせたくない」
「どういう意味?」
「宮野は探偵のオレにとって『非日常』のパートナーなんだよ」
「そんな言葉でごまかす気?傍から見れば、二股かけてるようにしか見えないわ」
「だから、どうしてそうなるんだって言ってる」
「蘭を不安にさせないでよ。やっと恋人が帰ってきたと思ったら、隣に綺麗な女の子がいて、その子を優先させるような態度を取られたら、不安に思うのも当然でしょうが!」
「恋人って…オレと蘭はそんな関係じゃないぜ?」
「何を言ってるのよ。照れくさいのはわかるけど、ちゃんと言わないと、ますますあの子が不安に思うじゃない!」
「園子、いい加減お前の勝手な思い込みでオレを責めるのはやめてくれ。確かに告白はしたさ。でも、オレはその返事をもらってない」
「えっ?」
「OKもNOも聞いていない。一か月ぐらいはやきもきして気にしたさ。二か月もたてばどうして返事をよこさないのかと腹がたった。三か月を過ぎれば、蘭にとってオレの言葉、俺の価値はその程度の認識なんだと諦めた。そのあと、抱えていた事件の方が大詰めになって気にしていられなくなった。なあ、園子の認識だと告白したらオレは蘭の恋人なのか?」
「それは…蘭も工藤君の顔を見て返事がしたかったんじゃ」
自分でもいささか苦しいと思ったが、蘭が新一をずっと待っていたのを知っているから、蘭をかばってしまう。
「そうかもしれないが、オレはそのことすらも聞いていない。厄介な事件を抱えて帰れないと言ってるのに、まだ帰ってこないのか?どうして帰ってこないのか?そんなメッセージしか聞かされていない。オレは側にいないのに、助けてって呼ぶから、オレの代わりに蘭を守ってくれって頼んだ小学生のコナンに随分と負担をかけて、それで両親からも怒られたよ」
「新一…」
「半年以上、何もなかったことにされて、それでOKの返事を期待して待っていられるほど、おめでたくねぇよ」
教室の入口に顔色を失って立ち尽くしている蘭に、新一が苦笑を浮かべて見せる。
「蘭、今でもお前はオレの大事な幼馴染だよ。でも、オレは『探偵』なんだよ。お前の望む『王子様』にはなってやれない」
「そんなこと!」
「蘭が望むのは、いつもお前の側にいて、お前の望みを叶えて、いつでもお前を守ってくれる『王子様』だろ。だから、オレが『探偵』なことを否定する。小五郎おじさんが、警察を辞めて『探偵』になって、英理さんと別居してるから、『探偵なんかやめて、ちゃんと働いて』って言う。そうすれば、二人が元に戻ると思ってるから。探偵を続ける小五郎おじさんが悪いんだと」
「違うわ!お父さんがだらしないから怒るのよ!真面目に働いて欲しくて!探偵なんて収入も不安定で、先がわからないじゃない」
「うん、そうだな」
どこか寂しげな顔で、新一は蘭を見た。
クラスメイト達が新一と蘭を『恋人』と認識して『夫婦』とからかえば、そんな関係じゃないと否定する。そのくせ、新一の側に女性の影が見えると浮気かと騒いで悋気をみせる。自分の方が蔑ろにされていると思えば、相手の立場や状況を考えることなく、新一をひどく責めた。
このあたりは、母親である妃英理の影響じゃないかと思う。
小五郎はアナログな人間だ。刑事だった頃も足で捜査したタイプだったろう。拘束時間に比べて、英理より収入が多いということはなかったろうし、家のことは何も出来なかったんじゃないか。家のことは何もしないし出来ない、事件のやりきれなさに飲みに行けば、酔いつぶれて帰ってくる。
べつに小五郎を擁護する訳ではないけれど、母親である英理からマイナスの言葉しか聞かされていないなら、情けない父親としか見れなくても仕方がない。
英理にすれば、歯がゆさからの憎まれ口だったかもしれないが、幼かった蘭にそれが理解できるはずもない。
賃貸収入があるからこそ、小五郎はいざというとき勤務に自由がきく探偵業を選んだだろうに、英理が個人事務所をかまえて負け知らずの弁護士として活躍している姿をみれば、同性である蘭からみて母親の方が輝いてみえるだろう。
母親への憧れ、家庭への憧れ、両親から放置されたと思って過ごした幼少期、いつも側にいて守ってくれる新一へ投影される理想。
蘭の『助けて!』という言葉は『どうして私が大変な時に側にいてくれないの!』と自分を一番大事にして欲しいという訴えだ。
「確かに、昔のオレは推理ショーを披露する自分に酔って、自信家で馬鹿だったと思うよ。だから『探偵ごっこ』をしていたオレは蘭の言う『大馬鹿』ってこともあながち間違いじゃない。でも、さすがにオレも学習した。オレより優秀な人はたくさんいる。信念に人生賭けて仕事している人も大勢いる。一人でできることは限界があって、誰かの力を借りる必要があることも。そして、被害が発生していなくて警察が動けず、助けを求める依頼人を救えるのが探偵だと思ったから、オレは『探偵』になりたいんだよ。だから、蘭とは友人ではいられても恋人にはなれない」
それは新一から聞かされる初めての線引きであり、拒絶だった。
「蘭には無理だろ。依頼人が女性だったら、二人で会うたびに浮気だと決めつけて怒るだろ?内容は話せないと言っても納得しないだろ?町中でオレを見かけたら、大声でオレを呼んで、返事がなければどうして無視するのかとオレを責めるだろ?オレが調査中だろうと関係なく、自分を優先しないのは許せないだろ?」
「私だって、ちゃんと理由を聞かされていたら、理解して我慢するよ。でも、新一は何も言ってくれないから、不安になるんじゃない!」
「言っても聞いていないだろ?」
必死に言い募る蘭に対して、新一のそれはひどく冷めた口調だった。
「確かに蘭の空手はド素人には有効だ。でも、本格的に近接戦闘を身に着けた相手に素人の学生空手は通用しない。それなのに、相手の技量を見誤って突っ込んで何回危険な状況になった?仮に非力であっても銃を持ってる相手に勝てる程、蘭は強いのか?周囲の状況も見ずに勝手に判断して行動して、警察の手配を台無しにしただろ?誰かを助けたいなら、最低限自分自身は守れないと意味がないのに、何度助けを呼んだ?」
「言い過ぎだわ、工藤君。蘭は普通の女子高生よ」
「だから、蘭には無理だと、探偵のオレにかかわるなと言ってる」
今まで園子や蘭が聞いたことのない、冷厳な響きだった。
「それじゃ…それじゃ宮野さんはどうなのよ!彼女だって普通の女子高生じゃない!蘭と何が違うのよ!」
「宮野を蘭と一緒にするなよ」
どこか呆れを含んだ声に、園子はギリっと歯を食いしばった。
園子にとって、蘭は大切な友人だ。確かに無謀なところもあるけれど、根は優しくて、いつだって助けたいと思ったから行動したのだ。それなのに、側にいなかった新一が一方的に非難するのは納得がいかなかった。
「あいつの専門は薬学だけど、データの解析や成分分析もこなす一人科捜研なんだぜ?公的機関に分析を依頼するのが難しいオレにとって、あいつがいないと見動きとれねぇよ」
「普通の女子高生じゃないの?」
「あー普通の高校生生活を体験してほしくて、オレが誘ったというのが正しい」
志保が学校では新一と距離をおきたがっているのは知っている。有名人である新一との関係をあれこれ詮索されるのは煩わしいと思っているし、蘭に対して申し訳ないと思っているのも知っている。
普通の高校生生活を送って欲しいと思ったのも本当だ。
だけど、新一は志保が自分の横にいないのは嫌で、声をかければ届くすぐ後ろにいて欲しいのだ。だから、全ての事情を説明できないが、志保が側にいられるように、いるのが当然だと周囲も認めるように外堀から埋めていく。
「どういう意味?」
「あいつ、まともに学校行ってないからさ」
「えっ?不登校とか引きこもりだったの?」
「不登校の引きこもり!」
園子の言葉に新一は思わず噴き出した。白衣を着た志保が地下室に籠っている様は、たしかに引きこもりと言えなくもない。
「何よ!だって学校に行ってないならそういうことでしょう!」
「悪ぃ、逆だよ。あいつの亡くなった両親が科学者で、あいつもその才能を受け継いだ天才だった。だから、英才教育って言えば聞こえが良いが、会う相手も情報も制限されて、研究と化学式だけを与えられて飼い殺しにされてたんだよ」
「そんなこと…」
「あいつ、アメリカの大学卒業して博士の資格もってるぜ?その代り、最初に会った頃なんて笑いも泣きも怒りもしない。他人にまるで興味を示さなくて、なんて冷たい奴だと思って、結構言いたい放題に責めたな」
どこか苦さの混じる口調でそういうと、新一は前髪をかき上げた。
「他人に興味がないんじゃない、研究以外で興味を持ったものは取り上げられて壊されていたから無関心を装うようになったんだと、辛辣な口調で他人を遠ざけるのはあいつなりの気遣いで自己防衛だと知ったのは、随分後だ」
「そんな人と、どうやって知り合ったのよ」
高校生の世界はけっこう狭い。学校と家庭と塾やバイト先。お嬢様である園子は鈴木財閥を通して見られる事を嫌がって、自分自身をみてくれると親友の蘭に傾倒した。
だが、新一は光だけでなく闇の世界も垣間見た。事実は一つ、でも真実は人の数だけ存在する。だから、園子が蘭の味方をするのはいいが、それで志保を攻撃するのは許せない。
「あいつがオレを探して訪ねてきたんだよ。それなのに、オレはあいつの表面だけ見て、ちゃんと話しを聞いていなかった」
新一の声に後悔が滲んでいた。
「幼い時に両親を亡くした子供が親の研究を完成させたいと、同じ研究を選ぶのは別におかしな話じゃない。ただ、あいつは両親の才能を色濃く受けついでいたから、施設に預けられることなく、両親が属していた研究所が引きとって英才教育を施した。ただし、実の姉に会うのも制限されて、本当に研究以外は許されなかったから、いろいろバランスが悪いんだ。ただ、両親の残した研究を完成させることだけに没頭して、開発途中の副作用のひどい薬を研究所が外に流したと聞いてあいつは激高した。まだ治験にも出せない未完成品など、薬じゃなくて毒薬だと、初めて逆らってハンストしたらしい。あいつの姉は研究所が宮野を食いつぶしてしまうと、研究所から連れ出そうとしたのがばれて、犯罪者に仕立て上げられて殺された。あいつはオレに姉を助けてくれと、周囲の大人が信じられないから、だからオレに助けを求めてきたのに、オレは、あいつの姉さんを助けられなかった。ヒントはあったのに、オレは毒をばら撒いた連中の仲間だとしか思わなくて、見るべきことを見ていなかった…結局、オレの力が足りなくて、被疑者死亡で送検されたよ。最後の身内を失って、あいつを守る大人はいなくなった。オレはあいつの姉の明美さんに宮野のことを託されたんだよ」
「だから、新一は宮野さんの側にいるの?」
死んだ人との約束だから、新一は彼女の側にいるのだと、そう思いたいというのが透けている蘭に、新一が苦笑いをする。
「それもある。でも、今はあいつがオレの相棒だから側に居て欲しい。最初は結構ひどかったんだぜ?事件の調査が進まなくて八つ当たりも随分したし、みっともない姿も見せた。あいつは自分の薬の副作用が人を殺したって自虐がひどいのに表面上は平気な顔してる上、言葉も足りないから、随分こじれて険悪だったりしたんだけどな。それでも、研究所と研究所を支援してる連中をこのままにはしておけないって、それで共闘することになって……一緒に過ごしてるとさ、楽だったんだよ。『探偵』のオレと一緒にいる時は、言わなくても察してくれる、オレの動きを読んでサポートしてくれる、頼むの一言で理解してくれる。蘭の前だと恰好悪い自分は見せたくなかったけど、あいつの前じゃ大概みっともない姿さらしてたから、無理して格好つける必要もない。オレが無茶すれば怒ったけど、それでもオレを止めない。無茶ぶりが過ぎると文句は言っても、オレが頼んだ資料とデータは揃えてくれるんだよ。蘭には嫌われるのが怖かった。好かれたかった。でも、あいつには嫌われようが好かれようが、別に良いよ。喧嘩してる最中でも、事件がおきれば、後は頼むって一言で、仕方ないって溜息をついてオレを助けてくれると思えるからさ。あいつが誰かと一緒にいて、他人のフリをするなら、何か理由があるんだろうと思う。オレを罵倒して遠ざけようとするなら、オレを守るためだと思える。好きだ嫌いだの一言で切れるような、そんな脆い繋がりじゃない。あいつはオレの信頼を裏切ったりしない。あいつはオレの『相棒』で『運命共同体』なんだよ」
新一の言葉は、まるで志保は恋人以上の存在だと、誰よりも自分を理解している人間だと言っているように聞こえた。
今までは蘭は自分が一番新一を理解していると思っていたし、そうだったはずだ。
ずっとそばにいて、一緒に過ごしてきた時間の積み重ねは、誰よりも大きかったはずなのだ。それなのに、新一は出会って一年もたたない相手に最高の賛辞を贈る。
どうして、そんなことを言うのかと、悲しくて悔しくて、言葉に詰まった。
ガラッと音をたてて教室の後ろの引き戸が引かれる。
疲れも見せず、涼し気な表情の志保が姿をあらわすと、クラスの視線が集中して思わず何事という風に志保が目を見開いた。
「もう良いのか?」
「ええ、起訴するのは検察、量刑に見合う罰をくだすのは裁判所、私の仕事は終わったわ。何かあったの?」
軽い口調で声をかけてきた新一に、異様なクラスの雰囲気を伺うように志保が尋ねる。
「いや?オレと蘭は別に恋人じゃないって園子に説明していたところ」
「まだなの?ようやく戻ってきたのに何をぐずぐずしてるのよ、早くしないと誰かに取られるわよ?」
「だから、オレは半年以上も前に告白して、無かったことにされたと言っただろ?」
「あら、一回で諦めるの?」
顔を顰める新一に対して、志保は何をやっているのかと呆れる態度だ。
「あの!宮野さんは新一とつきあってるんじゃないの?」
「付き合う?それは恋人としてってことかしら?」
「そうよ」
「ないわ。彼がどんなに毛利さんのことを心配して、あなたの元に戻りたがっていたか知っているもの。何か誤解させたのならごめんなさい」
新一との仲をきっぱりと否定して、申し訳なさそうな志保の表情は本心に思えたから、そして志保から新一が蘭のことを心配して帰りたいと想っていたと聞かされて、蘭はまだ間に合うんじゃないかと思ってしまった。
「それじゃ、宮野さんは、工藤君はどう思っているの?」
園子はただ、確かめたくて志保に尋ねた。新一から聞かされた志保の生い立ちは、まるで小説の中のようで実感がなく、ずっと新一を待っていた蘭の思いが報われてほしくて、新一は志保を特別に思っているのは間違いないが志保は新一をどう思っているのかと。
「私にとって…恩人かしら。あとは、『相棒』だわ」
「恋人じゃなくて?」
好きなんじゃないの?という意味を込めて問えば、志保は小さく笑う。
「私は彼の『恋人』になるより、『相棒』が良いのよ」
二人が言う『相棒』という言葉が、『特別』という響きに聞こえるのはなぜだろう。
「随分と荷物が多いんだな」
学生カバンだけでなく、2WAYの黒いリュックを降ろした志保を見て新一が言う。そんなに検察に持っていく資料があったのか?と。
「はぁぁ、これは救急キットよ。どこかの誰かさんが、すぐに事件に巻き込まれて怪我をするから。止血剤、増血剤、強心剤、解熱薬、麻酔、抗生物質他いろいろ。人体実験に使われたくなかったら、怪我しないように注意して」
本当は市販の薬ではどんな作用があるか分からないから、慎重に成分を吟味する必要があったので、志保が調合したのだ。
新一は「怖ぇなぁ」と笑っているが、そこまで用意するのかと周囲は驚く。
付き合っている訳じゃない、恋人じゃないと言いながら、それじゃこの二人の関係は何と言うのだろう。
『相棒』だという、その言葉の重みが分からなくても、込められた思いは伝わってきて、クラスメイト達は複雑な表情で、普通に会話をしている新一と志保の二人と、立ち尽くしている蘭と蘭を不安げに見ている園子の二人を交互に見ていた。