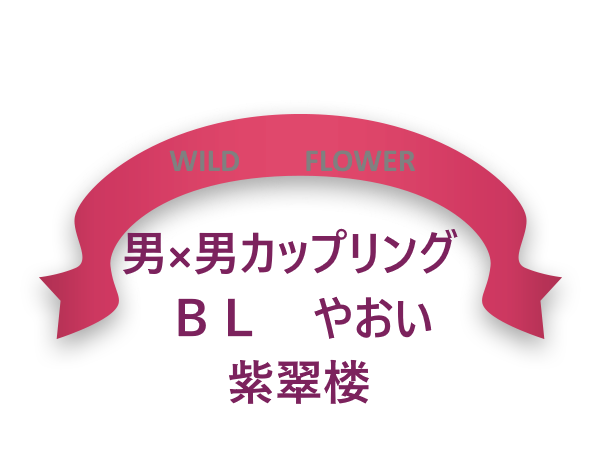触れぬ指先 恋の淵1名探偵コナン
新一×志保
帝丹高校は進学校だ。
進学率は99%を超え、卒業生のほとんどは大学進学を選ぶ。
推薦を狙う学生ならば、2年までの成績を意識するし、そうでなくてもカリキュラム上、3年1学期までに高校生の授業内容は終え、受験を希望する大学に即した選択授業をとる。
国公立を選ぶ者と私大では受験科目や内容が違うので、英語一つでもセンター向けの英語、長文読解と英作文を重視した内容、外国人教師による英語のみ授業でのヒアリングと英会話重視など、受験する大学にそった授業を選択することを求められる。
だから、2年になるとクラスの皆が揃うのはHRぐらいで、あとはそれぞれ受験する学部や大学に合わせた授業を選択して教科書を抱えてクラスを移動する。
机にもたれて眠そうな者、朝練に参加してパンをかじっている者、問題集を解いている者、友人と雑談に興じる者、登校した生徒達が思い思いに過ごす教室のそんなざわめきは、帝丹高校では当たり前の朝の光景だ。
ガラリと教室のドアが開いて、担任が姿を見せる。
「おはよう、HRはじめるぞー」
そんな言葉に、皆が席に着くと、ぐるりと出席者を見回して、奥の窓側の空いている席を見つめる。
「今日は、転校生を紹介する」
担任の言葉に教室がざわめいた。この時期にと誰もが思う。
「家の都合で、アメリカから日本に戻ってきたそうだ。出身はイギリス、幼少の頃、日本にも滞在していたことがあるそうで、日本語も問題はない。というか、編入試験での古文、漢文のセンターレベルはパーフェクト。漢字や熟語にも不自由はしていない。イギリス英語、アメリカ英語の使い分けもできるらしいから、外大狙う奴は教えてもらえ」
そんな紹介で、どんな秀才が来るのかと入口に皆の視線が集中する中、ガラッと音をたてて扉が引かれ、入ってきたのは見知った顔。
「工藤!」
「工藤君?」
「工藤、お前戻ったのか?」
クラスの生徒が驚きの声を上げるのは、学校でも高校生探偵として有名だった工藤新一だった。
「よお、久しぶり」
片手をあげて挨拶する姿に、「なんだよ、戻ってくるなら連絡よこせよ」「なんだ、転校生ってお前か。学校にも忘れらてるんじゃねぇの」「元気そうでよかった」と口々に声をかけられ、苦笑いをする。
「心配かけてわりぃ、WEB授業と課題に追われててさ。なんとか進級と復学を認めてもらえたよ」
登校拒否向けのWEB授業と確認テスト、レポート提出で履修したことにしてくれた学校に感謝だと笑った。
パンパンと手を打った担任が、「気持ちはわかるが、話は昼休みにしろ。転校生が入れないだろう」と声をかけられ、『えっ』と皆が入口を振り返ると、そこには入りにくそうに佇んでいる女子生徒の姿があった。
慌てて席についた生徒達は入ってきた転校生を見る。
血管が透けそうな白い肌と紅い唇。長い手足に翡翠色の瞳は、西洋の血を感じさせ、柔らかく波打つセミロングの明るい色の髪も、カラーやパーマではなく地毛だろうと思わせた。
化粧もしていないのにくっきりとした目鼻立ちは整っていて、『身近なアイドル』より綺麗な顔だが、どこか近寄りがたい雰囲気をもっていた。
「宮野志保です。日本の高校は初めてなので、いろいろ教えてください」
高くない、落ち着いたトーンの声は、転校という緊張を感じさせず、淡々とした印象だった。
「それじゃ、席は宮野が窓際、工藤は廊下側」
担任に指示された席に真っすぐ向かい座った。
授業は国公立向けの現国で、二人は真新しい教科書を開いた。
昼休みになると、他クラスからも新一に会いに生徒達が押し寄せた。
「いっぺんに言うな」と手を上げる新一に対して、思い思いに声をかける。
そして、ガラッと大きな音をたてて扉を引き、蘭が姿を見せた。
「本当に新一…戻ってきたの?」
「ああ、蘭。やっと戻ってきたぜ」
「戻ってきたなら、どうして連絡をよこさないのよ、このバカ!」」
「いや、課題が終わって登校決まったの昨日でさ。うちもバタバタしてたし」
「それでも、電話の一本ぐらいできるでしょ!」
「心配かけて悪かったよ」
怒りと安堵の入り混じった蘭の様子と、宥める新一の様子に周囲も「これからは心配させんなよ」「無事でよかった」と笑う。
「工藤、学食行こう。事件の話聞かせろよ」と声をかけた生徒に「悪い、弁当もってきてるんだ」と返す。
ドンと机の上に置かれたのは、コンビニ弁当などではなく、黒のランチジャー。
中身は温かい味噌汁の具材はジャガイモとアスパラ。ご飯は五目飯。おかずは野菜の肉巻き、魚の甘酢漬け、野菜たっぷりのスパニッシュオムレツを一片、温野菜とかぼちゃのサラダに根菜の煮物。デザートにリンゴのヨーグルトかけ。
「何、それ」
どう見ても出来あいではない、思いっきり手の込んだ弁当を広げる新一に周りは茫然とした。
「なにって、弁当だけど」
「弁当はわかるが、誰が作ったんだよ」
今日新一が学校に来ることを知らなかった蘭ではないだろう。
「誰って…おい、宮野!オレや博士にはフライもの禁止とか言って、自分はエビフライ食べるなんてずるくないか?」
窓際の反対の席に座っていた志保も、数人のクラスの女子に囲まれ、弁当を広げていた。
ちょうど箸で挟んでいたエビフライを目にした新一が文句を言うのに、志保も周囲も固まった。
席を立った新一が志保の側に寄ると、その小さな女性用のお弁当をのぞき込む。
「すくねぇな、足りるのか?なんか『お弁当』って感じだけど、エビフライにポテトフライにチキンナゲットって博士やオレに禁止してるやつばっかじゃん」
言外にずるいというニュアンスを滲ませる新一に、志保の頬が引き攣る。
この男は、人がわざわざ中身を変えたというのに、何を言ってくれるのか。騒ぎに巻き込まれたくないから、初対面で通すつもりだったのに。
チキンナゲットに手を伸ばす新一に「ダメ!」ととっさに叩いた。
「これは全部お弁当用の冷凍食品。あなたや博士の料理に比べれば、電子レンジ1分のお弁当よ」
「そうなのか?」
「最近の冷凍食品は出来が良いのよ」
「でもさ、別に一緒で良いだろ?わざわざ分けなくても」
「…そうね、明日からそうするわ……」
今更、他人のフリなんてさせねぇよという意味を込めて笑う新一を睨んでから、志保は諦めたようにエビフライを食べた。
「えっと、工藤君。このお弁当って宮野さんが作ったの?」
「そう、正確に言えば三食宮野が作ってくれる。昨日はオムライス作ってくれた。フワトロじゃなかったけど」
「まだ、言うか…あなたが食べたいっていうから、パンプキンパウダーで作ったんでしょう」
「だってさ、元太…小学生には店みたいなフワトロオムライス作っただろ。だったら、あれにデミグラスか自家製のトマトソースがかかって出てくると思うじゃないか」
「何を言っているのかしら?普通の一般家庭で出されるオムライスは、チキンライスを薄焼き卵で包んで、市販のケチャップをかけたものよ。うちはカフェじゃないと何度言えばわかるの?これ以上、メニューに文句言うならかぼちゃとレーズンのサラダ山盛りにするわよ」
『何、この二人の会話?』と周囲が固まったが、蘭があえて新一に向かって声をかける。
「だったら、私が新一の好きなもの作るよ!明日からお弁当作ってくるから」
「それは…」
「ありがとう、毛利さん。だったら米花東総合病院に献立と使う食材をg単位、調味料は0.1gまで記載して提出してくれるかしら?できれば一週間単位ぐらいで」
「えっ?どうしてそんなこと」
蘭の申し出に困ったような顔の新一に対して、蘭に向き直った志保が説明するように言葉を綴る。
「工藤君、元気そうに見えて内臓機能が低下しているの。それで、食事制限がかかっているのよ。塩分とカリウムだけでなく、血糖値も注意しなくてはいけないの。機能の数値が回復するまではタンパク質やビタミンも必要な栄養を必要なだけ摂取する必要があるの。好きな物を好きなように食べていたら、肝硬変に腎臓病、糖尿病に動脈硬化を発症させるリスクが一気に高まるのよ」
お前もだろ、と視線を投げれば志保は知らぬ顔をして無視する。
「毛利さんが工藤君にお弁当を作るなら、病院で確認してもらわないと、彼の夕食が点滴とサプリになるわ」
「お前なぁ!」
自分は冷凍食品の弁当を食べて、サプリですます気だったのかと腹を立てるが、志保は「何よ」と睨んでくる。
学内で有名な工藤新一のこと、二人が知り合いと知られたら、面倒になる。転校初日で騒ぎになるのを避けようと思っていたのに、他人のフリは許さないと新一がちょっかいをかけてくるから周囲に対して説明に困る。
「という訳だから、気持ちだけもらっとくよ、蘭」
「だったら、どうして宮野さんは良いの?」
「ああ、それは…」
「私、一応栄養士の資格を持ってるの」
「そうなのか?」
「そうよ、だから病院から食事を任されているの」
「まあ、博士の食事もつくってるしな」
「言っておくけど、博士のは1300カロリーのダイエット食、工藤君のは1800カロリーに計算された必要栄養素を逆割りしたメニュー、見た目は似てても中身は違うから」
「感謝してます」
手間がかかっているのだと言う志保に、パンと両手を合わせて拝む仕草を新一がすると、良いわよと素っ気なく返す。
APTX4869の解毒剤は完成させたが、十代後半の高校生と小学生、急激に成長させた後遺症はやはり出た。骨密度も危険水域で、サッカーなどしたら間違いなく骨折すると注意を受けている。
強いAPTX4869の解毒剤を服用した後なので、投薬治療よりは食事療法を中心とすることを病院は採用し、文字通り電子計で一々計って料理するのを志保は引き受けた。
自分の分だけではなく、新一の食事も三食作ると志保が請け負ったので、二人は入院ではなく、通院での経過観察を認めてもらえたのだ。
薄味ではあっても、不味い料理はプライドが許さないのか、今まで出されたことはない。
そして、普通はそんな料理はとても負担であることも、新一は理解していた。
「新一と宮野さんは知り合いなの?」
「まあ、いろいろと…」
「いろいろ?どういうこと?」
不審げな蘭の様子に新一が困ったような顔になる。説明がいろいろ難しい。
「工藤君というより、工藤君のご両親である優作さんと有希子さんのお世話になったの。金銭的なお礼は受け取ってもらえないから、しばらく工藤君の食事指導を兼ねて私が料理をすることになったのよ。数字の改善がみられないなら、改めて治療法を相談して専門家に依頼することになると思うわ」
志保にすれば蘭が心配しているような、好意からくるお弁当ではないと強調したつもりだったが、治療の一環だと言われれば素人が作ったお弁当を食べろとは言えなくなる。
「でも、それじゃ一緒に店いったりできないな」
「あー、俺の担当は優秀だから、週一ぐらいなら、一番シンプルなハンバーガーとコーヒーとか、ブラックコーヒーだけとか、桜餅とほうじ茶とかなら付き合える」
同級生の言葉に新一は笑って答える。
ただし、志保に報告した上で、きちんとカロリーと食材がわかっている店に限るが。
内臓機能の低下は間違いなく自分の責任だと、悲壮感すら漂う雰囲気で、検査の数値を見ていた。
だから、必死でメニューを考え、新一の機能を元に戻そうとしているし、出来るだけ普通の生活をと望んでいることもわかっているので、こと食事に関しては新一は志保に文句をいうつもりはない。
「早く食わないと、時間がなくなるな」
時計を見て自分の席に戻ると、食事を再開する新一に、蘭は言葉に迷い、志保は溜息一つついて、しなっとしたフライドポテトを口に入れた。
高校では穏便に暮らしたかったのだけど、無理そうだと思いながら。
タイミングが良いのか悪いのか、午後の授業の休憩時間に新一のスマホが鳴った。
着信の名前を見て、新一の眼の色が変わったのに志保が気づき、小さく溜息をつく。
「はい、今は大丈夫です。…はい…わかりました。すぐに向かいます」
鞄に教科書を突っ込み、志保を振り返った新一が「宮野!」と呼ぶと、志保は「気を付けていってらっしゃい、遅くなるようなら連絡をして」と答える。
そんな志保の返事に新一が顔を顰めて「何言ってるんだよ、早く支度しろよ」とツカツカと寄ってくるのに志保は舌打ちをしたい気分になる。
「何馬鹿なことをいっているの?私なんかがついていったら邪魔になるわ」
普通の高校生は事件現場になんか向かわない。転入初日から授業をさぼるなんて、教師に目をつけられたらどうしてくれると、志保がジト眼で見上げると、新一はスマホの画面を志保の前に突き付け「頼む、力を貸してくれ」と一言告げた。
スクロールされる写真に志保の顔つきが変わる。
そして、仕方ないという風にわざとらしい溜息をつくと、自分のスマホを出してタクシーを呼んだ。
「宮野?」
「簡易検査のキットを取りに戻らないといけないのよ」
「警部に言ってパトカー、回してもらうぜ?」
「馬鹿いわないで、パトカーのサイレンを鳴らしながら乗りつけたら、近所の人たちに何事かと思われるじゃない」
ただでさえ、『発明家』をうさん臭く思う人もいるのに、どんな噂がたつことか。
「写真そっちにも送る」
「ええ」
鞄に教科書を片付け、タブレットで写真を確認しながら、志保は口元に手をやる。
「すぐにこのノート以外に書かれた化学式がないか調べてもらって。部屋に何か機材があればむやみに動かさないように。ネットショッピングの購入履歴と近所にホームセンターがあればそこの購入履歴、あと筆跡鑑定でこの化学式を書いた人がその被害者のものかどうかも」
「ヤバいのか?」
そっと身を寄せて、囁くように新一が尋ねると、「どこまで生成したかによるけど、作ったとなるとかなり。念のため両隣の住人を避難させるように依頼して」とこちらも小さな声で囁くように答えた。
新一から転送されてくる写真を繰る志保の表情は真剣だ。
「わかった」と一言、新一は折り返しの電話をかけ、鞄を掴むと「悪い、俺と宮野は早退するって先生に伝えておいてくれ」と手を挙げて挨拶もそこそこに志保と二人で教室を後にした。
連れ立って出て行った二人の様子に、クラスメイトは最初茫然としていたが、我に返るとどういうことかとざわめきだした。
工藤一人なら、以前にもあったことだが、その彼が転入生を連れて行ったのが理解できなかった。
「知り合いってだけじゃないの?」
「だって、一緒に行くのが当然、みたいな態度だったよね?」
「うん、宮野さんが行ってらっしゃい、って感じだったのに、工藤君は『どうしてついてこないんだ!』みたいな」
「工藤の奴、宮野さんに手伝ってくれって言ってたよな?」
「化学式がどうとか…」
「宮野さん嫌々っぽかったけど、なんか慣れてもいるような…」
教師が入ってきて、一旦クラスは静かになったが、クラスメイトの頭にあったのは『あの二人ってどういう関係?』ということだった。