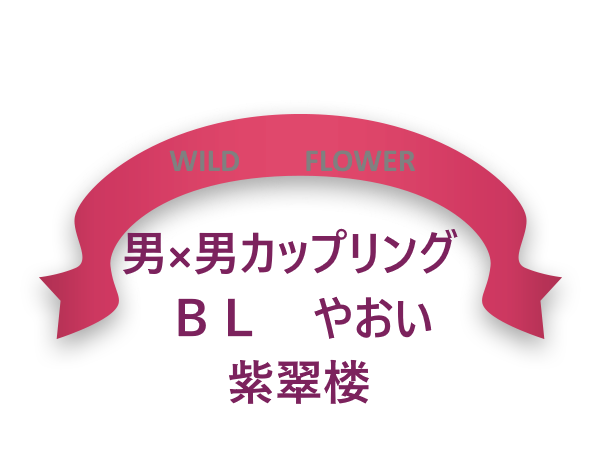華香る 沈丁花3月のライオン
島田×あかり
大分、日が落ちるのが早くなったと、島田と桐山が住宅地のアスファルトにのびた影を追うように歩いた。
昼間がまだ暑い日もあるが、日が落ちると肌寒く感じるようになった。
ジャケットを着ても暑いとは思わなくなったなと、島田は制服姿で隣を歩く高校生を見る。
その右手にはスーパーの買い物袋。随分と主婦業が似合う高校生だ。
三日月堂に贈答用の菓子の注文があったのだが、発注ミスがあり、納期が半日早くなり、数もありがたいことに100個ほど増えたものだから、今、お店はあかりとひなたも手伝っている状態で、モモのお迎えと買い出しを頼まれたらしい。
子供の喧騒が聞こえてくると、二階建ての白い壁と赤い屋根の幼稚園が見えてきた。
事前に連絡が入っているのと、「れいちゃん!」と嬉しそうに駆け寄ってくるモモの存在で、お迎えにきた身内だと幼稚園のスタッフにも認識された。
ただ、桐山の隣にいる長身の男の存在に、訝し気な表情になるが、これもモモの「あにじゃもきたの?」という台詞で知り合いなのだと理解した。
「あかりさんとひなちゃんはお店の手伝いで忙しいんだ。晩ご飯買っておうちに帰ろうか」
小さなモモに視線を合わせるようにしゃがんだ島田に、モモが「アイスかってくれる?」と問うから、「一つだけだよ」と島田が笑う。
「あの、晩ごはんって」
「これから作るんじゃしんどいだろうから。焼肉か手巻き寿司の具材でも買って帰れば、あかりさんの負担が経るだろう」
夕方だから、生鮮食品は安くなっているだろうしと島田が言葉を重ねる。
「アイス」と喜んだモモが、ふと島田を見上げ、そして頭から足先まで見てから、不満げな顔をする。
「どうかした?モモちゃん」
「あにじゃ、おさむらいとちがう」
「お侍?」
意味が分からず、首をひねる島田に、園の保育士が笑った。
「『あにじゃ』さんは『おさむらい』なのだと、モモちゃんが話していたんです」
「えっと、島田さんが着物を着ていないということかな?」
「着物?」
「ええ、モモちゃん、僕達が棋士だと説明できなかったらしくて。それで、『お侍』だと」
「ああ、なるほど」
祖父の相米二が見る時代劇と同じ格好をした島田を見て、『お侍』と言ったのだろうと理解した。
まあ、一般の人からすれば、メディアに出まくっている宗谷ならともかく、A級とはいえタイトルをもたない島田の顔はあまり知られていないし、職業としてのプロ棋士は想像しにくいだろうし、語彙が足りない普通の園児に説明は難しい。将棋をする人と説明できれば良いほうで、それでも職業ではなく趣味だと思われるに違いない。
「『お侍』かぁ…切られてばっかで、格好悪いけどな」
「そんなことないです!島田さんは凄く格好いいです!」
「ありがと。桐山にそう思ってもらえるように頑張るよ」
力を込めて反論する桐山に、島田が苦笑する。本当にこの後輩の前で無様な対局だけはしたくない。
「モモ、嘘つきじゃないもん。あにじゃはおさむらいだもん」
「うん?」
ムウッとした顔で、島田は『お侍』だと繰り返すモモに、島田が再び首を傾げる。
「隣の組の貴文君とケンカというか、言い合いになってしまって」
困ったように笑いながら言う保育士の言葉に、桐山もしゃがんでモモの顔を覗き込む。
「その貴文君はモモちゃんを嘘つきって言ったの?」
「『あにじゃ』なんておかしいって。おさむらいなんかいるわけないって」
「貴文君、モモちゃんのことが好きで、イジメているんじゃなくて、ちょっかいをかけているというか」
その貴文君をかばう保育士に、島田よりも桐山のほうが複雑な顔をした。
その子に悪気はなくても、モモが辛い思いをするなら、それは許されることではない。
「正装した七五三の写真をモモちゃんに見せびらかしたのに、「あにじゃとれいちゃんとはるのぶさんのほうがずっとずっとかっこいいもん」って言ったものだから、ムキになってしまって」
元々、癇癪を起すと「ぼくのおとうさんはえらいんだから、ぶちょうなんだから」と言い出して我儘を通そうとする。
多分、あの母親の口癖がそれなのだろうと分かる。
あかりが銀座で働いていることに眉を顰める親もいる。叔母の店だと言っても、水商売のお家なのねと蔑む。両親がいないことも、モモやあかりのせいではないのに、育ちが悪い家の子はと陰口をたたく。親達と違ってまだ幼い子供はその意味をしらないまま、悪意に満ちた言葉をそれと知らずに口にする。
「あにじゃやれいちゃんだってえらいもん。ボドロのほうがずっとずっとかっこいいもん」
ムウッとした表情は変わらず、しゃがみこんだままでグズるモモの頭に桐山が手を置く。
「大丈夫、モモちゃん。そこらの部長程度なら、島田さんの所得の方が上だから。ずっと稼いでいるから。島田さん社長だから」
「桐山…社長って、赤字スレスレの零細企業だよ。それに社長なんか、銀座にいけば幾らでもいるだろ」
何を張り合っているのかと、島田が脱力するが、零は本気だった。
「そうだなぁ、今度、皆で着物を着て、お写真撮りに行こうか」
「おしゃしん?」
「そう、桐山と坊もお侍の格好をして、あかりさん、ひなちゃん、モモちゃんはお姫様の格好をして、お写真を撮るんだ。それを貴文君に見せてやるといい」
「モモ、おひめさま?」
「そう、うんと可愛いお姫様」
『お姫様』の言葉に機嫌が直ったモモが、おかばん取ってくると、教室に駆け出した。
「島田さん、僕着物もってませんけど」
「俺のを貸してやるよ。写真ぐらいなら袴の裾を直せば着れるだろう。対局用のは、多分幸田さんあたりが用意したいだろうから、練習用と思え」
「えっ、でも…」
「もう着ないやつだから、汚しても気にしなくて良い。どうせ坊は持ってるだろうし、皆で写真撮影と言えば、モモちゃんも着やすいだろう」
女子は三歳と七歳、男子は五歳にお参りするものだったが、最近は特に区別なく晴着を着てお参りする者も増えた。
ならば、モモが着物を着て、加護と成長を願って参っても良いだろうと、島田が言う。
帰り道、スーパーで3割引きになっていた手巻き寿司用の刺身のパックを3つ程と、プリンを買って、三日月堂へ戻ると、店の工房では最後の追い込みの最中だった。
買ってきたと、島田が差し出した買い物袋に恐縮しながら、あかりは助かると礼を言い、5合ほどご飯を炊いて酢飯と錦糸卵、キュウリの千切りを刺身に添えて、すまし汁を鍋に作り、従業員の分まで夕飯を用意した。
一区切りと、皆で包んで食べる手巻き寿司は賑やかで、モモもあかりにツナやトマト包んでもらってご機嫌な顔で食べていた。
食後のデザートに出されたアイスをスプーンで掬いながら、思い出したモモがあかりの手を引っ張る。
「あのね、あにじゃがみんなでおしゃしんとりにいこうって」
「え?写真?」
「うん。ももとひなちゃんとおねぇちゃんがおひめさまで、あにじゃとれいちゃんとはるのぶさんがおさむらいのしゃしんなの」
「え?」
どういう意味かと、あかりが島田に目をやると、苦笑いで島田が幼稚園でのことを説明する。そして、祖父である相米二を見て「どうせなら、今度の定休日でも、皆で写真を撮って、お参りにでかけるのはどうかと」と誘った。
「そんな、ご迷惑でしょう」
「いえ、ちょっとこの前ポスターに使われた写真がひどくて。まともなデータを渡したいですし、桐山と坊も着物姿の写真があって困ることもありませんし。俺達だけ着物というのも、いかにもでバランスが悪いでしょう?どうせなら、七五三の写真でいいんじゃないかと。平日であれば、そんなに混んでないでしょうし」
「いいんじゃないか?モモちゃんが三歳の時は、家の中がバタバタしてて、ちゃんとお祝いできなかったんだし。綺麗な恰好で写真撮れば」
「そうだよ、相米二さんや美咲さんも着物着てさ。こんな機会でもなければ、ちゃんと写真撮ることもないんだし」
そう三日月堂の従業員も言葉を添える。
父が出て行って、母が倒れた。そして母が逝けば今度は祖母が。あかり自身、成人式には参加していないし、モモの三歳のお祝いも、祖母が倒れていたので、いつもよりちょっとだけ余所行きの格好で神社に行って千歳飴をもらってきただけだ。
「知り合いに頼むんで、衣装代も値引きしてもらえますし」
やっぱり、モモちゃんが嘘つき呼ばわりされるのは気分が悪いですしと、島田が言葉を重ね、穏やかな口調と態度で、島田に押し切られて渋々という風にあかりが頷いた。
「それじゃ、次の定休日に」
いつもの笑顔でそう言った島田に、モモは「モモ、おひめさま?おねぇちゃんも、ひなちゃんもおひめさま?」と腕を引っ張るので、「そうだよ、皆の可愛いお姫様の写真撮るから、貴文君にも見せてあげるといい」と笑って答えた。
「やっぱり、こっちの方がおちつくなぁ」
「あかりさんに会うと癒されます」
「うん、やっぱり気ごころ知れてる店の方が良い」
「あら?」
スミスこと三角あかりに惚れている一砂、久しぶりの横溝が、カウンターになつきながら水割りを注文するのに、ママである美咲が乾きものであるナッツとチーズを盛った皿を出す。
「なんだよ、お前らこの間、藤本に六本木のキャバクラ連れていってもらったんだろ?」
面白そうな顔で、神宮寺が二人を眺めながらグラスを揺らす。
「ええ、藤本さんが島田さんに負けて、奢れと財布代わりの島田さん引きずって六本木に」
「シャンデリアとかすげぇキラキラしてて、女の子も可愛かったんですけど、なんか落ち着かなかったです」
「もう、藤本さんのテーブルと島田さんのテーブルの差が凄くて」
「俺たち、島田さんのテーブルだったんですけど、席に着く女の子皆、俺たちに気を使ってて、いや島田さんに気を使ってよ、みたいな。島田さんに出した水割りもなんか聞かない名前だし」
「藤本さんの方はすごい賑やかで、こっちは静かというか」
「まあ、そうなるわな」
「結局、藤本さんの飲み代以外は、島田さんが出してくれたんですけど、女の子達凄い勢いで島田さんに名刺渡して、次も是非って」
「いくら支払ったの島田さんだからって、あれ酷くないですか?」
今まで、島田よりも自分達に気を配っておきながら、財布が島田だとわかって営業をかけるのは露骨すぎないかと、スミスが不満顔を見せる。
島田に出したという酒の名前を聞いた神宮司が苦笑いを浮かべた。
「それ、国内の小さい醸造所で作ってるやつで、あんまり出回らない酒よ」
「え?」
「その子たち、店側に発破かけられたかね」
苦笑交じりに神宮寺が言えば、スミス達は意味が分からないという顔で問い返した。
「お前たちが行ったの、六本木の『ビジュー』だろ?」
「はい、そうですけど」
「その店、新宿の方にグループ店があるんだよ。で、今はもうないんだけど、系列だった『ブロッサム』っていう店にいた愛ちゃんって子、島田が接待でよく使ってた子でさ。ほら、あいつ聞き上手だけど場を盛り上げたりとかできないし、将棋以外の話題しらないから、接待のとき場がもたなくてさ。愛ちゃんそのあたりのフォローうまくて、物産展の担当者とかにあいつの所の塩野クラブの商品とか山形の物産とか売り込んでくれる子で、島田が接待のたびに指名してた子なの。まあ、気配りとかすごく出来る子だったから、固定客もついて、上の店に行って、そこから銀座の方に引き抜かれて、今はたしか雇われでちいママやってる。金ためて、小料理屋やるのが夢で、店を出したら、店に下す野菜の仕入れで、島田に地元の農家紹介してくれって言ってたな」
「はあ」
「島田は、一回で大金おとす太客じゃないけど、金を落としてくれる客を連れていくのよ。それにいつもニコニコ現金払いでツケ払いもしないし、酔って騒ぐとか暴れたりしないし、色恋営業求めないし、女の子だけじゃなくて店にとっても良い顧客な訳。愛ちゃんが銀座に移って、固定客もごっそり持っていったから、店側にしたら、『うちにも良い子がいるんで、また客連れて来てください』ってことだろう」
「そういうことですか」
キャバ嬢の営業メールで舞い上がって女の子に注ぎこむ藤本と違い、島田は自分が苦手な接待を代わってしてくれる子が欲しくて女の子を呼ぶ。
だから、島田は自分ではなく、同伴した者に気をつかってくれる子を選ぶ。
「あれは、島田さんに対するアピールだった訳ね」
「そういうこと。島田は若い子にちやほやされたい訳じゃないから、自分を助けてくれる気にいった子をずっと指名するし、同伴した客にも紹介する。気に入ってもらえれば長く指名が取れると、店側も本気で上目指してる子とか、店もちたい子とかに発破かけたんだろう。あいつはその場だけの頑張ってとか言わない。本気の子はちゃんと応援するからさ」
それも下心なしで、と言葉を継ぐ。
「そう、言われれば…島田さんが、店に入ったとき、『シークレット・ガーデン』に似てるなぁって言ったら、店のスタッフの顔つき変わったような」
「それ、新宿の上位店。愛ちゃんがいたところ。あっちじゃ島田と愛ちゃん結構有名なのよ」
「そうなんですか?」
「そうなの。愛ちゃんが『シークレット』に移った後、島田が『ブロッサム』の方に行ったことがあってさ。ずっとあいつが愛ちゃん指名してたことを知ってる店側が困ってさ。こちらじゃなくて、あちらにとか遠まわしに言うんだけど、島田が今日はやってないの?とか素で尋ねるし。案内されてもスタッフが気まずい感じで。で、10分ぐらいで愛ちゃん飛んできて、島田に文句いう訳。なんでうちに来てくれないんだと。お店変ることお知らせしましたって。島田が見てないとかいうから、『私、島田さんにちゃんとハガキ出しました』って真っ赤な顔で怒るのよ。あいつ、対局で本当にハガキのこと忘れてただけなんだけどさ。でも、同席してる俺達とか店のスタッフにすれば、ここで痴話喧嘩されても困るよね、みたいな。結局、島田が謝って、『シークレット』に席を移したんだけど、さすがに席につけばちゃんと接客してくれたよ」
まあ、女の子が店を移るとき、顧客を引っ張ってきてくれることを店側も期待するから、島田が前の店に顔を出したとなれば、飛んでくるのもわかるのだが、なんだろう、同じ下手に出て、女の子に謝るのでも、島田と藤本で印象が違うのは。
「見た目冴えないし、リシャールとか高価なボトルいれるわけでもない島田のどこが良いの?って愛ちゃんに聞いたことあるんだけどさぁ。月末、お店の売上厳しくて、発破かけられて店に来て欲しいって島田に営業電話かけたことあるんだって。そしたら、開店すぐに客を連れて店にきてくれて、二度目後輩連れて来てくれて、三度目一人で来てくれたって。いままで営業かけてこなかったのに、電話してきたってことは本当に困ってるんだろうって。高い酒ポンといれられないから、これぐらいしかできないけどって言われて、ボロボロ泣いて、困らせたって言ってたわ。来て欲しいっていう月末の営業電話一本で、一日に三度店に来てくれたの、後にも先にも島田だけだって。愛ちゃんが島田の大ファンだってお店じゃ有名だった」
「ああぁ、お店の女の子相手でも良い人なんだ、島田さんって」
なんなのそれ、惚れるだろうと一砂がわめく。
「藤本の場合、完全に鴨葱扱いされてるけどな」
藤本本人がそれを理解していないところが哀れを誘うというか、憎めない感じになるのだが。
「やっぱり藤本さんと違って、変な下心がないせいですかね」
「う~んそれもあるけど、接客のプロとして扱うからじゃね?自分にはできないから助かるって、礼を口にするとも聞くし、店の黒服とか新人の子とかにも人気よ、島田のやつ。知ったかぶりではなく、基本的なこと教えたりするから。自分も愛ちゃんに教えてもらったとか笑って言うから、あんまり押しつけがましくならないみたいで。まあ、もともと人当たりが良くて聞き上手だし、金払いも綺麗だから、玄人さん受けはいいよ」
神宮司の話を聞いて、スミスと一砂が突っ伏す。
これがA級との差なのかと、枯れてると言われる島田だが、年寄や子供だけでなく、ちゃんとモテてるじゃないかと。本人無自覚ポイが。
「藤本みたいにころころ店変えたりしないしさ。たいてい数人の客連れて行くし、威丈高な注文したり色恋営業要求しないし、必ず現金で払うから売上確定するし、店としても、女の子としても良いお客なんだろ。島田と『シークレット』行くと扱いよかったもん。あいつ前よりも収入増えたし、変なところで人脈はあったりするから店としては島田にまた来て欲しいんだろうけどなぁ。まあ、島田なんか接待を愛ちゃんに丸投げして、相槌うつだけなんだけど、愛ちゃん場がしらけないようにどうにかしてくれるし、タクシーに手土産の手配までやってお見送りするしで、かなり頼ってるからそうそう変えない気もするけど」
「えっと、お付き合いとかは?」
「どうだろうねぇ、仲は良いけど男女の仲って感じじゃねぇなぁ。島田が愛ちゃんに頭があがらない感じはするけどさ」
あいつはお前達と違って、店の女の子に恋愛求めてないから、と神宮司が言うと、そういう人だよなとスミス達がうなだれた。
自分達があかりの気を惹きたくて、この店に通っている自覚はあったからだ。
あかりが天然なのと、美咲のガードが固くて、カウンター越しに手を握ることすら出来ていないが。
「おかわりはいかがですか?」
「お願いします」
「僕も」
「じゃあ、俺も」
つい薄めに作りそうになった水割りを、きちんとスミス達の好みの濃さに変えてステアし、テーブルに置いた。
あかりさんは今日も綺麗だと、あかりに向かって言うスミスや一砂に対して、あかり本人はいつもの社交辞令を並べ立てていると「ありがとうございます」ただ微笑む。
本当ですよと、眉尻を下げた情けない顔で、男達があかりの様子を窺うのに、叔母である美咲は、これで自覚していないから質が悪いわねと思った。
スミス達の話を聞いて、やっぱり島田さんはそういう目的で女性のいる店にいく訳じゃないのだと安心する一方で、本人はこんなおじさんはモテないとか言ってるけど、ちゃんとモテてるんじゃないかと思ったり。
自分の父親である誠二郎のような不誠実な人ではないと、ほっとする一方で、島田が通っているという愛という人がきにかかる。
別にあかりは叔母のことも、この店のことも恥じてはいない。客筋も良くて、理不尽な思いはあまりしない。
それでも、モモの通う幼稚園で、両親がいないこと、あかりが大学にいかず働いていることなどで陰口をたたかれていることも知っている。
どうしたって水商売と下に見る人が多いことも。この店は叔母のポリシーで枕営業はしていない。それでも、銀座の店で働いていれば、売り上げのために身体を使うのだろうと下卑た言葉でからかう人も、アフターは幾らだと尋ねてきた人もいる。
島田から、そういう意味での視線を感じたこともなければ、川本家を下に見るようなことも、哀れまれたこともなかった。
今度の定休日にモモの七五三の写真を撮りに行こうと島田さんに誘われたの。
見かけによらず強引でとあかりが言えば、「なんだか嬉しそうね」と美咲が笑った。
あかりの成人式は、父である誠二郎が家を出た後で、母が体調を崩し、店の手伝いやらでとてもそんな気にはなれないと欠席だった。
振り袖も着る機会もないし、汚れたら大変だからと、結局仕立てる事もしなかったが、実際は治療費を気にしてたのだろう。
「良いんじゃない?写真ぐらい。うちも大分落ち着いてきたことだし」
「でも、ご迷惑じゃないかしら」
「どちらかといえば、零君に着物を用意する口実じゃないの?ほら、彼も来年卒業な訳で、そうなると学生服をいう訳にもいなかいんでしょう?」
「そうかしら?」
「モモを口実にしたんじゃないの?」
そう言葉を重ねれば、あかりは何となくで納得した。
多分、モモの七五三が口実なのは本当だろう。ただ、着せたいのは桐山ではなく、あかりだろうが。
定休日はたまたま3連休の月曜日で、川本家は揃って島田に指定された場所に赴いた。
2階が貸衣装、1階が美容室になっていて、零の袴の裾を直してもらう間に、あかり、ひなた、モモは髪とメイクをしてもらえと言われて案内された。
相米二は黒紋付き、美咲は黒留の着付けを済ませ、あかり達の衣装の吟味をしていたのだが、広げられていた薄桃色の加賀友禅に顔を引きつらせていた。
「島田さん、これ本当に貸衣装なの?」
「ええ、そうですよ」
「だって、これ……」
肩から裾まで花鳥の描かれた加賀友禅。刺繍に箔も入っている。色数と繊細な模様は貸衣装のセットで扱うランクのものではない。
「仕立ての注文を受けた後、諸事情でキャンセルになった品で、貸衣装に下ろされた着物です」
そう言って島田が笑った。
髪と化粧で女性の支度には1時間はかかるからと、桐山に合わせて袴の裾を手早くかがり、着付けを行う。
若竹色より薄めの緑に袴は若い桐山にしっくりと似合った。島田は銀鼠色の着物を着ている。茶系だと老けて見えるからと苦笑いをする。
どこかぎこちない桐山に比べれば、やはり島田の方が着慣れた感はある。
あかりとひなたも髪を結い、薄化粧を施して振り袖を着る。
高校生になったばかりで身長がたりないひなたにもよく合わせて、オレンジ色の振り袖に四君子柄の帯をだらり風に結んだ。
モモは7才用の着物を調整して着付け、薄化粧をして紅をさした。
あかりは長い黒髪を結い上げて簪を指し、豪奢な加賀友禅の振り袖に西陣の帯をふくら雀に結んだ。
三姉妹が綺麗な晴れ着を着て笑っている姿に相米二が思わず涙ぐむ。
「見合い写真にも使えますよ」と撮影スタッフに言われる程に、振り袖姿のあかりは綺麗だった。
川本家皆で揃った家族写真に、それぞれ一人づつ、姉妹だけでと撮り、桐山と島田、二階堂も一人ずつ撮ってから川本家と並んで集合写真のような写真を撮る。
「それじゃお参りにでかけようか」
そう言って島田がモモを抱きかかえる。
慣れない草履は痛くなりやすいからと、モモの草履を二階堂に持たせて、ゆったりと歩くのに、モモが島田の腕に抱かれてはしゃいだ。
「ほら、危ないから」
と慌てる島田に、「みんなおひめさまにおさむらいさんね」とモモが笑う。
「そうだね」
二階堂はやはり、自前の着物を持っていた。紫紺色の略礼装だが、その恰幅の良い体型から着物がよく似合う。
零はどこかぎこちないが、オレンジ色の振り袖を着て、薄化粧をしたひなたをまぶしそうに見ているので、酷くわかりやすい。
愛米二は黒紋付き。美咲は訪問着だと店に出るみたいに見えるからと鳳凰柄の黒留め袖。
そのせいか、何やら見合いの席にでも出向くのかという雰囲気になる。
参ったのはお店の近くの神社だったが、休みの日とはいえ着物を着た集団がぞろぞろ歩いていればどうしたって目立つ。
鳥居の前でモモを下ろし、小さな草履を履かせる。
「お辞儀をして、神様にご挨拶」と島田に言われて、ペコリとモモが頭を下げる。
二階堂がモモと手をつなぎ、あかりと島田が後ろをついて境内を歩くと、普通に家族に見える。
相米二と美咲は先を歩く島田とあかり、ひなたと桐山を見つめる。
桐山は斜め上に暴走する時があるが、ひなたへの好意を隠さない。
だが、島田はわかりにくい。あかりを着飾らせたかったのだと思うのに、見合い写真にどうぞとあかり一人の立ち姿と椅子に座った写真を相米二に手渡したりする。
美咲も鎌をかけてみたのだけれど「自分にはもったいないですよ」と交わされてしまった。好意はあっても、あかりと関係を進める気が無いように見えるのがもどかしい。
「今日はありがとうございます。島田さん」
「どういたしまして。俺としても眼福です」
穏やかに笑う島田にドキリとする。
店で聞く島田の評判は、優しくて、面倒見が良くて、温厚。
それでもたまに、華がなくて地味だ、棋風に特徴がない、あと一歩でタイトルが獲れない、宗谷相手とはいえ4タテは情けない、そんな話も聞こえてきた。
そんな棋士仲間の会話に顔を顰めるのも、やはり棋士達で。
「そんな台詞は自分がA級に3年在籍して、タイトル戦出てから言えよ」
と、普段は聞かない低い声で言い放ったのはスミスと呼ばれる三角だった。
「スミスは島田さん贔屓だからな」
と笑った相手に、スミスが冷笑を浮かべる。
「分かってるのか?隅倉さん、土橋さん、藤堂さん、柳原さん、後藤さん、辻井さん、この常連に島田さんが加わってから5年、A級上位7人は落ちていない。あとの3人で残り一枠を争って、毎年1人はA級を1年で降格になってB2に逆戻りのループコースなんだ。B2からA級に上がってもほとんどが8人目の最終枠争いで終わる状況が5年、タイトル戦も上位7人での椅子取りだってこと理解してるのか?せめて、8人目の定位置を獲るか、あのA級の牙城崩してから大口叩けよ」
スミスの言葉に、相手は顔を赤くして、代金を叩きつけるようにテーブルに置いて店を出ていった。
「熱くなるなよ、スミス」
と宥める一砂と横溝に、スミスが顔を顰める。
「島田さんの強さって、隅倉さんや後藤さんのわかりやすさと違うから、すぐに舐めたこという奴等が出てくる」
「タイトルが獲れれば、見方も変わるだろうけどな」
「っていうか、タイトル戦の時の島田さんと対局すれば、あんな巫山戯たこと言えないはずなんだよ!」
別に普段の対局で手を抜いている訳では決してない。それでも、A級同士もしくはタイトル戦の時の島田はあきらかに違う。
炯炯と瞳がにぶく輝き、唇を吊り上げるように薄く笑って指す時の島田は、多分胃の痛みすらも神経を研ぎ澄ませるものでしかなくなる。
勝ちたいと思って指すのは、どの棋士でも同じだが、普段の温厚な印象が強い島田だと、勝ちを獲りに行くときの変貌は別人のようだ。
「あの人の本気って、柳原棋匠とは別の意味で、鬼火背負って見えるよ」
「盤の前に座って死ねたら本望みたいな」
「命削ってるというか、勝つために何か大事な物失っていってる感が」
「本当に、対局終わったあの人見るたびに、ここまでしないとA級になれないなら、無理じゃないかって思うもんなぁ」
A級になりたいと思う。勝ちたいと思う。それでも変人揃い、魔窟とも言われるA級の特に上位組は本当に化け物と妖怪の集まりに見えて、勝てるイメージが持てないのも事実だった。(辻井さんだけは、『悪い辻井さん』だと勝ち目が見える時もあるが、『良い辻井さん』だとあっさりと吹っ飛ばされる)
あかりが知る島田は、いつも穏やかに笑っているか、困ったように笑う。
眦を下げて笑う島田の口調はどこまでも優しくて。
食材の差し入れにしても、上手にあかり達を甘やかす。普段、誰かに甘えるということがないから、戸惑うことも多いのだけど、距離感が上手くて、あかりが断れないようにもっていかれてしまう。
腕を組んで、ゆったりと歩く島田は、落ち着いた年上の男の人だと、その横顔を見て思う。多分、年齢で言えば、自分よりも父である誠二郎の方が近い。
自分が失ってしまった父性を、島田に見ていないとは言えない。島田の側はひどく落ち着くのだ。自分が上手くできない不器用な小娘でも許される感がある。
島田の前だと自分がしっかりしないとと、気を張らなくて良い。
だけど。雑誌で見た島田は、スミス達が語る棋士の島田は、そんな優しい印象とはかけ離れていて。
踏み込んではいけない感があって。これ以上をあかりから求めてはいけないように思えて、受け入れる形でしか、島田の好意に触れることが出来ない。
「ん?どうかしました?」
「いえ」
あかりの視線を感じたのか、島田がわずかにあかりの方を向く。
普段は朴訥と言っても良いような、慣れぬ風情の島田が時折見せる艶。
低く掠れる普段より甘い声。
あれは夢だった。
あんな風に、島田の部屋を訪れた事はない。
それなのに、どうして……
カアァと頬を赤く染めたあかりが咄嗟に顔を背けると、島田が困ったように笑う。
「おねぇちゃん、あめかって」
千歳あめを買ってというモモに、気を取り直してハイハイと笑ってあかりが足を速める。
神社にお参りをして、美容院に戻る途中、たまたま訪れていた外国人観光客に頼まれて写真を一緒に撮ったりしながら、機嫌良く来た道を皆で連れだって帰る。
衣装を脱いで着替えた後、皆でスイーツを食べに行って、バケツのような器にプリンやケーキまで盛られたビッグパフェを食べる女性陣に、島田や相米二達男性陣は目を逸らしながらアイスクリームにコーヒーを飲んでいた。
あかりの体型に口うるさい美咲も、今日だけはとスプーンで崩し、モモも上機嫌で食べている。
「よくまあ、あんなに食えるな」
「まあ、女性は甘い物は別腹だそうですから」
「いや、胃は一つだろう」
これもいつものお約束のように、全部食べ終えて苦しいと言う女性陣に、あれだけ食えばそりゃ苦しいだろうと相米二が呆れ、島田と桐山、二階堂は苦笑いを浮かべる。
皆でお店を出て、腹ごなしに三日月町の家まで歩いて戻ろうと、連れだって歩き出す。
すると、お約束のように空が晴れているのにパラパラと雨に見舞われた。
大変と慌てて軒下に逃げれば、島田が落ち込んだ表情ですみませんとあかりに詫びた。
「どうしたんですか?」
「俺、凄い雨男で。今日だってちゃんと晴れマークだったのに」
本当に野外イベントは向いていないと肩を落とす様にあかりが笑う。
「ちゃんと晴れていますから。それに狐の嫁入りですから、どこかの花嫁狐が幸せのお裾分けをしてくれたんですよ」
キラキラと日差しを受けて煌めく雨粒は、とても綺麗で。それにすぐやむと思うから、そんなに気にしなくてもと、あかりが言えば。
あかりがよく知る、照れくさそうに頭をかきながら島田が笑った。
その笑顔を見て、『ああ、好きだな』と思った。
ストンとあかりの中に、その気持ちが落ちて来た。
そっとそれを両手の掌に包んでみたら、ひどく胸が温かくなった気がして、あかりはニコリと微笑んだ。
好きだから、このままでいい。
この人の負担にならない距離で、この人を応援していられる距離でいい。
光が透けるようなあかりの笑顔を、島田が目を細めて見つめていた。