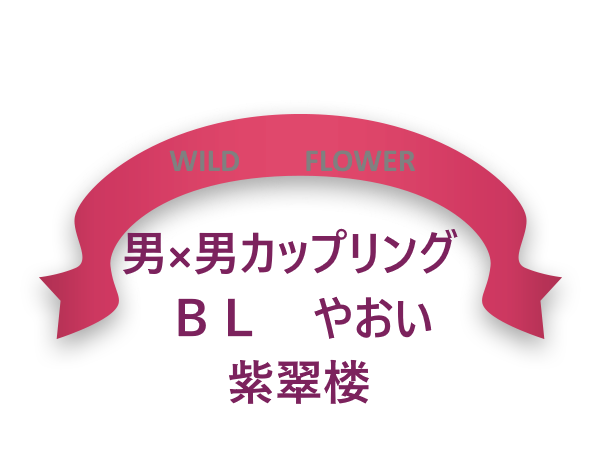華香る 銀木犀3月のライオン
島田×あかり
銀座の店舗ビルの一角にあるバーは、『銀座』という言葉でイメージするほどには敷居が高くない。
テーブルとカウンターは二〇人ほどで一杯になる店内、落ち着いた内装と柔らかな色調の照明で、カラオケこそ流れていないものの、オーナーでありママでもある美咲の他、週二度手伝いではいる姪のあかり以外には化粧こそ若々しいが三〇歳を過ぎたホステスが二人の、どちらかといえばこぢんまりとした店で、お値段も銀座という場所を考えれば良心的だ。騒がしい程ではなく、かといって『銀座のルール』を要求することもなく、初心者向けというか、普通に飲みたい者達には気軽に通える店だった。
カランとベルが鳴り、重厚な木枠とガラスの扉が開き、新しい客が店内に入ってくる。
「いらっしゃいませ、神宮寺様、柳原様」
「今晩は、美咲ママ。響の15年いれて」
「あら」
「島田につけといて」
もう嫌になるとぼやきながら、日本将棋連盟の会長である新宮寺がドサリとカウンター席に座る横に、最年長で棋匠のタイトルを持つ柳原が笑いを浮かべて座った。
「どうしてあいつは勝って欲しい試合で負けて、勝たなくていい試合で勝つの?タイトルに関係ない地方の大会なんだから、若手に譲れよ。島田と藤本って、誰得?なんで二人ともあんなに大人げないの?」
「藤本もタイトル落として仕切り直しだろうし、せっかく帰ってきてくれた細君に良いとこみせたいんだろ」
「だからってさ、またポスター地味じゃん?どうやってあおり文句つけるのよ。島田も山形だからって頑張るなら、タイトル戦で頑張れよ。あいつ将棋やってるやつにはファンが多いけど、地味だから一般受けしないのよ。いっそ桐山とだったら師弟対決とか、新人王とった期待の若手の挑戦で売れるのに、桐山も何あっさり負けてるのよ」
グズグズと文句をいう神宮寺に対して、柳原が苦笑いを浮かべる。確かに、大会の規模から言えば、普段なかなか表にでれない新人を出してやりたいという神宮寺の気持ちも分かるからだ。
停滞が続く者達にこそ、出て欲しかったのだろうが、大人げないA級棋士の二人が蹴散らしてしまった。
聞くともなしに聞こえてきた神宮寺の話に、島田が勝ったのが悪いみたいに言われて、カウンターの内側でつまみの用意をしていたあかりはわずかに顔を顰める。
この前、川本家にご飯を食べに来たとき、島田は嬉しそうに笑っていたのだ。本当はタイトルを持って帰りたかったのだけれどと苦笑いをうかべながら、それでも次勝ったら故郷で対局なのだと嬉しそうに。
これを食って力をつけろと、山形牛のすき焼き用ロース2キロが届いたのですが、一人では食べきれないので、お裾分けですと、保冷バッグごと差し出された霜降り牛肉。
どうしましょうと慌てるあかりに、このままじゃ腐らせるだけでもったいないですからと笑う島田に促され、祖父の相米二と叔母の美咲、零も呼んですき焼き大会をした。
「美味しい~美味しいよ~」と涙目になるひなたを筆頭に、これまで食べたことのない柔らかな霜降り牛肉に、皆が肉の争奪戦を繰り広げる横で、島田は嬉しそうに笑いながらくたくたになった野菜を食べていた。
おなかいっぱいとぽっこり膨らんだおなかをさするひなたの横、祖父の相米二に促されて、島田は指導のために将棋を指し始める。モモはあぐらをかいて座る島田の膝上によじ登り、ちょこんと座って祖父と島田の指す手をじっと見ている。
うんうん唸る相米二を前に、穏やかな顔でパシンパシンと軽やかな駒音をたてて島田が指す。
「やっぱり島田八段の方がわかりやすいな、坊主のは正しいんだがわかりにくい役所の文章みたいだが、八段のほうはかみ砕いた文章というか」
そんな事をいう相米二にあかりが慌てるが、零は困ったようにまなじりを下げて笑った。
将棋の駒をニャー達に例えて絵本を書いた二階堂に負けた時は、どうにも落ち込んでいたようだが、島田に負けた分は納得するらしい。
そもそもプロに直接指導してもらうこと自体が珍しいのに、零も二階堂も、A級の島田ですらも川本家では本当に素人相手でも手を抜かずに教えてくれる。
不意にモモが盤の駒を動かして、「おっ?」と相米二が目を見開く。
ここじゃなかったのかと、島田を伺うモモの頭に島田がポンを手を置くと、その長い指が違う駒を動かした。
そのまま数手駒を動かすと、モモが顔を顰める。駒を元に戻すと「じゃあこっち」と小さい手が駒を動かす。小さな手で動かすと、綺麗な駒音が鳴らない。二階堂も零も、島田も綺麗な駒音が鳴るので、モモは一生懸命駒を鳴らそうと練習している。
モモを膝に乗せながら、少し前屈みで盤を見ている島田の背中を見るともなしに眺めていた。
幼稚園で、大好きな人達を描きましょうと言われてモモが描いた絵。
そこにはあかり達家族以外にも、零と二階堂、島田の姿があった。
誰かな?と問われ、「れいちゃん、はるのぶさん、あにじゃ!」と答えたという。
濃いビリジアングリーンのクレヨンで描かれた島田は、どうやらこの前テレビで見た和服の姿らしい。
棋士だと告げたようだが、幼稚園の先生は「騎士?」と困惑し、「おさむらいのあにじゃ」と言われてますます分からなくなったようだ。
誰なのかと問われ、最近うちによく来てくれるプロの将棋差しの方達です、モモにも将棋を教えてくれてるんですと答えた。
「あにじゃというのは、二階堂君が兄弟子の島田さんをそう呼ぶので、モモもあにじゃと呼ぶようになって」
「ああ、そうなんですね」
と幼稚園の先生は納得したように頷いた。そして、少し困ったような顔で、あかりに謝った。
「すみません、千穗先生が、モモちゃんに「だったら、この『兄者』さんがモモちゃんのパパさんになるのかな?」って言ってしまって。他意はなかったと思うんです。モモちゃんの『兄』なら、あかりさんのいい人かなって」
あかりがモモの母親代わりであることは、この幼稚園に勤めている者達は知っている。まだ若いあかりが、子育てをしながら家の手伝いをしていることも、大変だと思っていて、恋人が出来たなら良いことだと、そう思っての言葉だったのだが。
「モモちゃん、「違うもん。ぱぱしゃんじゃないもん。ずっとモモのあにじゃだもん」って泣きそうな顔をして」
「そうですか……」
モモにとって、自分の側から父親はいなくなってしまう存在なのだ。二階堂が、幼い時からずっと兄弟子である島田が自分のことを気にかけてくれていたと、モモに嬉しそうに話していたから、『あにじゃ』ならずっと一緒だと思ったのだろう。
モモにとって、島田は『あにじゃ』なのだ。大きくなったモモを、あかりは買い物袋を抱えたままでは抱き上げることは出来ない。
細い体躯なのに、軽々とモモを抱き上げて、肩車をしてくれる。祖父の相米二とも十代の零とも違う、モモが初めて身近に感じた大人の男性なのが島田だ。
台所でモモがお鍋をひっくり返して、大惨事になりかけたことがあった。顔色を変えたあかりがモモを叱ろうとすると、島田が「あかりさんのお手伝いがしたかったんだよな」とモモの頭を撫でた。「だけど、台所には危ないものが一杯あるから、勝手に触ったら駄目だ」とそう言って、モモに片付けを手伝わせた。
後日、島田はモモ用にと踏み台と、かわいいピンクの子供用のキッチンばさみとピーラーを持ってきてくれた。
そうかと思えば、ひなたのシュシュを持ち出して、無くしてしまい、知らないと嘘をついたモモには厳しく叱った。
「嘘をつくのは、勝手に持ち出したのが悪いことだと分かっているからだろう?怒られるのが嫌だから、嘘をついて誤魔化していいと、いつ、二階堂や俺が教えた」
手を上げることも、大声で怒鳴るようなこともしなかった。
それでも、いつもの穏やかな空気が一変して、冷え冷えとした声と頭上から重圧がかかるような威圧にモモはごめんなさいと泣きじゃくった。
ちゃんと謝ったからと、夕食後には零に買い行ってもらったトロトロ壺プリンを渡され、モモは恐る恐る受け取った。
その視線は「あにじゃ怒ってる?怒ってる?モモのこと嫌いになった?」と雄弁に語っていて、島田は苦笑を浮かべてモモの頭を撫でた。
「モモちゃんはもう負けるからと、将棋のニャー達をぐちゃぐちゃにしたりしないだろ?ちゃんと最後まで頑張る子だろう?だからズルしたら駄目だ。ズルして嘘をついたら駄目だ」
食べなさいと、柔らかに微笑む島田にコクンと頷いて、モモはプリンを口に入れる。
それは初めて食べる食感のプリンで、「ほわ」と嬉しそうな顔になる。
もう島田が怒っていないとニコニコ顔に戻ったモモが「あにじゃ」とじゃれついた。
美味しかったけれど、一個400円すると後から知って、あかりは目眩を覚えたものだ。
わがままを言っても許される家族とも違う。可愛がってくれるけれど、叱るとき厳しい島田は、モモには分かっていなくても、端から見れば『父親』だった。
こんな風に、あの人もモモを大事にしてくれたら、可愛がってくれたらと、思わない訳ではない。
いらないと、余所の家を選んだあの人は、もう父親じゃないと拒絶した。
それでも、死ぬまで父を思って泣いていた母の姿を忘れられない。どうして自分達はあの人に捨てられてしまったのだろう。何が悪かったのだろう。
将来、モモが父親がいないことを疑問に思ったら、そのときは私とお姉ちゃんがいらないと言ったのだとそう教えるとひなたは言った。
零は「それっておかしくないですか?」と何度でもあかり達の側で言うと、誠二郎の自己愛の身勝手を指摘すると言った。
吹っ切ったつもりだったのに、「あにじゃ、あのね」と島田の膝によじ登って笑うモモを見てると、なぜか胸の奥が痛んだ。
「桜井のやつ、まあた島田に蹴落とされたな。山登りも振られてるとは聞いてたけど」
「客を呼ぶなら、桜井の方が良いんだけどな。あいつ、集客はトップだから」
「でも、島田さんも頑張ってて」
つい、島田をかばう発言をするあかりを神宮寺は「おや?」というような視線を向ける。
「確かに頑張ってるよ、だけどあいつタイトルが獲れないことに引け目を感じて、地元に力入れすぎるから、今はあまり行かせたくないんだよね」
「ああ、塩野クラブね」
「そう、過疎化がすすむ老齢世帯の孤立化を防ぐため、あいつが始めた将棋クラブだけどさ、今じゃ地元の食材で土産物とかにも手を出して、結構な話題な訳。周辺も似たようなものだから、あいつの作った塩野クラブにも視察とかで過疎の市町村が出向いてるとかでさ。週に2回、巡回バスを出して年寄り達を公民館に集めて、帰りにはまとめ買いした食材や日用品を持たせて家まで送ることで孤立化を防いでたんだけど、保存食から地場産業起こして、今じゃそれなりに収入が増えて、じいさん、ばあさん、元気に新しい農具買おうか、新商品作ろうって前向きだってさ。それにあやかって、自分の村にも巡回バス出して欲しいとかの依頼結構きてるって、あいつのコンサルの兄ちゃん言ってた」
「一昨年だったか、えらく雪が降って、村の除雪費用の予算足りなくなって島田が出したんだろ。コンサルの兄ちゃんが島田の口座は村の臨時予算じゃねえって怒ってたな」
「まあ、あの土地で雪に閉じ込められたら死活問題だってわかるけどな。でも、島田が『ふるさと納税』やめたら,あの田舎すぐにひあがるんじゃねえか?」
「巡回バスもそうだけど、村おこしの事業だって、売るとなると食品衛生法に合致した製造所やら、パッケージやら、販売ルートやらが必要な訳で、初期投資全部島田の持ち出しだろ?」
「そう、島田の善意に頼ってるだけじゃ、いずれ行き詰まるって、コンサルの兄ちゃん達が収益があがる仕組みを作ろうと奔走した結果、話が大きくなったらしい。一応、株式会社Kaiの社長よ、島田」
「社長ねぇ」
「まあ、収支トントンみたいだけど」
なんでもかんでも寄付するんじゃ駄目だと、税理士の御神本が島田を説得し、株式会社を立ち上げて巡回バスも会社所有にし、製造所も村に費用負担をかけないことで、土地を無料で提供してもらい、製造所で働いてもらって給料を支払う仕組みを作ったのだ。会社の収益で、巡回バスの運営やら、除雪車の手配やらをしている。
「で、周辺の村々はそれが羨ましいと」
「そ、過疎って地味に廃れていくばかりの村じゃ人口もふえねえし、収入なんて増えねえよ。コンビニも商店街だってないのよ?島田があれこれとやって、ようやく一人暮らしの老人達が暮らしていけるんだ」
寒村には介護施設だってない、緊急コールとて、駆けつけるのは村の年寄りだ。雪が続けば、すぐに村が孤立する。週に二度、食料品が届くようになったが、それとてコストからみれば全然見合わない。島田が損を承知で宅配の手配をしているから出来るシステムだ。
「隣のじいさんばあさんが暖かい公民館で笑ってて、生活も豊かになってきて、人生張りが出たと明るく話してりゃ、うらやましくもなるか」
「予算がないのはどこでも一緒。だったら、島田の『善意』にお願いする連中が増えるわな」
特に、今回の地方の試合となれば、その手の役所の人間が出てくる。だから、あまり近づけたくないのだ。
「あいつもなあ、勝手なことばかり言うな、遠くで応援ってなんだよ、自分が頑張れよ!って言えれば楽だろうに」
年老いてなお、A級でタイトルを保持する柳原がグラスの酒をちびりと飲む。
「あいつも託された期待を捨てられないからな。託された期待があったから、三段リーグ抜けれたっていうのも嘘じゃねぇだろうし」
はあと大きく息を吐いて、神宮寺が琥珀の酒のおかわりを頼む。
「これも島田さんにつけるんですか?」
咎めるようなあかりの視線にも、神宮寺が笑って「今夜の飲み代は全部島田ににつけといて」という。
「ほんと、今のあいつにはあまり余計な話聞かせたくないんだけど」
「そう言いながら、島田に仕事ふってるよね、会長様?」
「しょうがないでしょ。A級の中で外向けの仕事出来る奴、少ないのよ?島田地味だけど、渉外には向いてるのよ。あいつ人を怒らせないから」
「まあなあ」
宗谷は耳が聞こえたり聞こえなかったりという点を差し引いても、渉外には向かない。後藤や藤本は見た目が怖いので初対面の人間は話しかけづらい、他の面子も基本将棋さえ出来たら良いというスタンスなので、スポンサーに気を遣うということをしない。
逆にA級で気遣いのできる島田の方が珍しいともいえる。
「タイトル獲れなくて、結構言われ放題な時もあるのに、あいつ笑って流すからさ」
「それが物足りなくて、わざと怒らせようとするのもいるけどな」
「タイトルが獲れれば、少しはあいつの枷もかるくなるだろうに。そうしたら、胃も楽になるかね」
「どうだろうかね、あいつは痛む胃を抱えてる方がらしいって気もするが」
「だけどさ、桐山がものすごく心配するじゃない?今日だって島田連れてくるはずが、桐山に止められたのよ?休ませるから駄目だって。本当に「おかん」だわ」
「桐山か……懐いたねぇ」
「ああ、予想以上にな」
あかりの知る桐山零とは、真面目で優しい青年だ。どこか人との距離をはかりかねているような不器用さはあるけれど、それでも一度親しくなれば、自分のことはおざなりにしても一生懸命に世話を焼こうとする面がある。
「本当に、甲斐甲斐しく島田の世話をしててさ、もうね、介護かって言ってる連中いるしさ」
「まあな、『いつもすまないねえ』『それは言わない約束でしょ、おとっつぁん』ってのがしっくりくるな」
「年の差からいえばそうかもな」
クツクツと笑いながら、神宮寺と柳原が島田と零の様子を思い出して笑う。
「でもさ、本当にあいつものすっごっっく世話焼きでな、フラフラな島田を寝かせて、服の上着ブラシかけて、ズボンをプレスして、もらった花束水につけて、お茶やらなんやら買い出しに行って、付き人かっていうぐらいまめまめしい。ていうかさ、あいつの食事もっていって、食べれますか?って心配げにしてる姿なんか、もう幼妻めいて、微笑ましいんだか犯罪臭漂うってか……あれじゃますます結婚が遠のくぞあいつ」
心細やかに気遣ってもらって、放っておいて欲しいときは干渉されず、将棋指したいときは相手をしてくれる。
「桐山いたら、嫁いらないじゃん」
「確かに、桐山だといちいち言わなくて良いから、島田にしたら楽だな」
「あいつも、モテない訳じゃないのに、結婚から縁遠いな」
「本人社交辞令だと、モテてるとは思ってないから」
「島田は本当に自己評価が低い。宗谷がいるせいで、確かに話題にあがるようになったのはあいつがA級入りしてからだよ。だけどさ、タイトル持ってない棋士がほとんどだっての。タイトル戦に挑戦しないまま終わる棋士の方が多いっての。あいつだって、A級で5年、タイトルに挑戦するところまでは上がって来てるだろうに」
宗谷を天才だと言い、そして天才だから奢らず弛まず努力を惜しまないと評したという。自分を地面を這って進む亀か虫だというが、歩みを止めなかったのは島田もだ。確かに早くはない。それでも、確実に前に進み、ここまで上がってきた。
また届かなかったと、敵わないと宗谷を見る棋士達の中で、二度三度と挑む相手は少ない。元々複数タイトルを持つ宗谷と戦える者が限られる中、勝ち抜いて挑戦者の権利を得るだけでより数が絞られる。
そして島田は心が折れなかった数少ない棋士の一人だ。宗谷を神に例えるのは、宗谷と戦ったことがない者だ。鬼だと悪魔だと引きつった顔でつぶやくのは、宗谷に喰われ、潰れていった者達。そして、傍観者の方が圧倒的に多い。
「まあ、島田とつきっきりで、将棋指してるなら、桐山もここからは早いだろ」
「そうだな、しばらくくすぶっていたが、最近は確実に強くなって勢いが出てきた。A級入は早いかもな」
「ほう?」
「幸田も悪いやつじゃないが、桐山をA級にあげるには力が足りない。宗谷を前にすることがどういうことか、タイトルを争うことがどういうことか、A級がどういう場所か、あいつじゃ教えてやれないからな」
両親を亡くして幸田に内弟子になったことで、零の才能は芽吹いた。だが、同時に萎縮もしていた。子供なのに少しも楽しそうには見えず、どこか辛そうに縋るように将棋を指していた。
幸田は真面目だが、桐山の才を育てるのは無理だ。
「島田なら、桐山を育てられると?」
「ああ、あいつは宗谷を相手に引かなかった人間だ。桐山の才能に全く嫉妬をしない訳でもないだろうが、桐山を潰すようなことはせんよ。桐山がA級入りするときも、『ようこそ、鬼の住まう奥殿へ』と笑って迎えるだろうよ」
桐山がA級になったら、島田とセットで売れると神宮寺が笑う。
島田が同伴なら、桐山も嫌とは言わないだろう。そして、島田が後ろ盾になれば、いらん雑音も聞こえない。なんせ、島田は地味だが敵が少ない。
あかりは黙って神宮寺と柳原の会話を聞いていた。
この店で、客の棋士達が話す二人とも、川本家で見る二人とも違う島田と零の姿だった。
棋士の零は凄いのだという実感はあかりにはなかった。恐る恐る川本家を訪れる零は、ここにいてもいいのかという雰囲気で、ガリガリに痩せている子供だった。最近ようやく、川本家でくつろいだ表情をするようになったが、それでも遠慮がちだ。
島田は零や二階堂が慕い、モモが懐く優しくて穏やかな大人の男性だった。声を荒げることも、妹たちを邪険にすることも、あかり達を「可哀想な子達」扱いをしない人だった。
父親の誠二郎の『優しさ』とは違う。本当の意味で『優しい』人だった。
零が語る島田の地元への思いと地域貢献も、立場が変われば見方が変わる。
島田は詳しいことは話さないが、出資や寄付を頼む者は多いらしく、コンサルメンバーが防波堤になっているようだ。特に対局前後は話はきかずに自分達に振れと税理士の御神本に厳命されているらしい。
誠二郎のことも金銭トラブルに島本家や零が巻き込まれるのを嫌ってのことだと、わかっている。それでも、何の見返りも求めず、無償で手を差し出してくれたのは、島田が初めてだった。
零のようにわかりやすく守ろうというのではないけれど、それでもあかり達がこれ以上傷つかないようにと心を配ってくれているのはわかる。
どうしてと、問いかけることが怖くて、言葉を濁してしまうけれど、感謝していない訳ではない。
「島田もなぁ、健康管理してくれる嫁さんもらったら、タイトルの一つも獲れるだろうに。まあだ引きずってるかね」
「五年?六年前?A級あがれるかどうかでもがいてた頃だろ?横でもっと身体を大事にしてくれとか言われてもきけねぇよなぁ。自分を見てくれ、自分との時間を大事にしてくれと叫ばれてもきこえねぇよ」
優しい女性だったのだと島田は言っていた。自分がいたらなかったのだと。
「タイトル獲るために、崖を必死で登ってる途中で、背中には地元の期待を背負ってるのに、これで女の手を握ったら身動きとれねぇじゃん。向こうもさ、覚悟がいったんだよ。いくら麓で待ってても、島田は山から降りてこねぇよ。ま、30年もしたら降りてくるかもだけど、あいつの場合、即身仏になってる可能性の方が高いって」
離れたくないのなら、崖を登るあいつの腕でも足でもしがみつくしかない。少なくとも、振り落としたりはしなかったはずだ。例え、一緒に落ちても、しがみついていれば、島田と一緒にはいられた。
「棋士として、盤に向かっているあいつを支えるなんて出来ないんだよ。それでも、好きな男が痛む腹をさすりながら必死の形相で駒を指していて、何を言っても答えない背中と将棋を指す横顔だけじゃ何のために側にいるのか分からなくなったんだろうな」
棋譜を考え続けて、苦しむ姿に何もしてやれないと、どんな言葉をかければいいのかと嘆く身内は多い。ただ居てくれればいいのだと。その言葉が届かない。
「島田と一緒にいたいなら、共に登るしかねぇんだよ。命綱だけつないで、自分も登るしか。落ちかけたらあいつが支えてくれる。そのあいだに体勢立て直して、また登るんだよ。あいつがずっと手を握るなんてできる訳がねぇんだよ。今更、背中の期待を下ろせる訳もない。全部抱えて登るあいつの側にいたいなら、支えるとか考えず、一緒に登れば良かったんだよ」
神宮寺の言葉に、あかりの手が止まった。
「大切に思ってなかったはずがねぇんだよ。気を許してなきゃ、のたうち回ってグダグダな自分の側に置くはずもない。でも、それを分かれというのも酷だったんだろうな……」
「そういえば、周囲に心配かけまいとする島田が、桐山は側において世話を焼かれてるな」
「ああ、桐山のやつも、胃痛のあいつにうどん食わせて、心配だって顔しながら、フラフラのあいつを京都まで連れてきたし、痛みに顔をしかめるあいつと将棋を指してる。だから心配なんだよ~あれじゃ、本当に出来た嫁じゃん。どうすんのよ、島田の老後まで桐山が面倒みるとか言い出したら」
自分じゃ結婚しても相手を家政婦以下の扱いにしてしまうからと笑った不器用な男。
家政婦なら金銭の対価を渡せるけれど、妻になった人にそれ以上の物を渡せるか分からないと、小さく呟いた。
側に居て欲しいとは言い出せなくなった臆病な男に、自分が妹達を育てるのだと他人を頼ることも重荷を背負わせてしまうと一歩引いてしまう女。
別にけしかける訳ではないけれど。好きだという気持ちだけでは『棋士』としての島田の側にはいられない。
島田は将棋以外はヘタレだから、自分から手を伸ばせるとはおもえない。だから、あかりに問う。手を伸ばして掴んだら、離さずにいられるのかと。
なりふり構わず将棋に向かい続ける男の横顔を見るだけの生活に耐えられるのかと。
あかりの中で父を想って泣く母の姿が浮かぶ。
そんな母の姿に嘆いた祖母と叔母の顔も思いだした。
愛していたはずだった、好き同士で一緒になったはずだった。それなのに、あかりの両親は壊れてしまった。そして父は、違う家の人になって、今度は別の女性を好きになってまた逃げようとしたという。
好きになることは簡単でも、それは続かないのだと思った。
同窓会で、所帯じみている、重いと言われたとき、自分にとって大切な家族を軽んじられた気分になって気が塞いだ。
妹達を不幸だなんて言わせない、自分は幸せなのだとそう思ってきたけれど、やはり周囲からみれば、叔母や祖父からすら不憫だと言われてしまう。
幸せな結婚が想像出来ないのだ。恋人が欲しいとも思えない。
島田がいて、零がいて、二階堂がいて、ひなた達家族がそろう食卓が幸せで、それだけで良いのに。
零はひなたと結婚すると言っていた。若いうちの勢いだと思いながらも、そうなったら良いなとも思う。
そして島田は……いつまでうちに来てくれるのだろう。あの穏やかで優しい人は。対局になると零以上に我が身を削る人は、せっかくあかりが食べさせても、対局が終わるとげっそりと頬がこけて痩せてしまう。
心配だと言っても「いつものことだから」「心配かけてすみません」と笑うばかりで結局はこちらの言葉を聞いていない。
そして、零はそんな島田を心配しながら、将棋を指す。「休ませたいんですけど」と言いながら、対局の場に連れて行く。
島田に引かれた一本の線。
その内側にあかりは入れず、零は入れる。入ることを許されている。
ふらつく島田を抱えて歩く零の姿を想像して、なぜか悔しいと思った。
不意に、以前聞いた、夫に浮気をされて子供と一緒に家を出ながら、あなたを幸せに出来ないような相手に譲る気は無いと、そう言い切った棋士の妻の言葉が頭をよぎった。